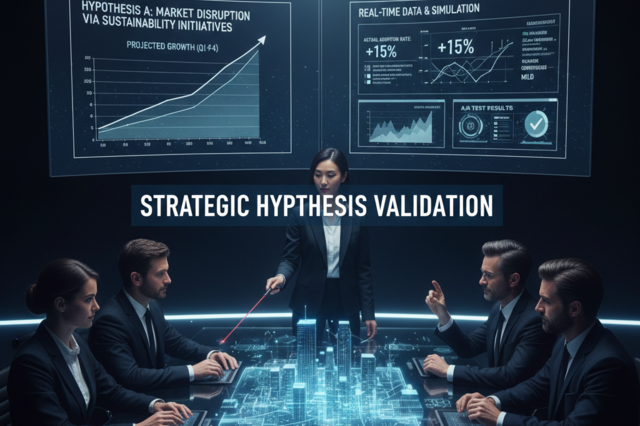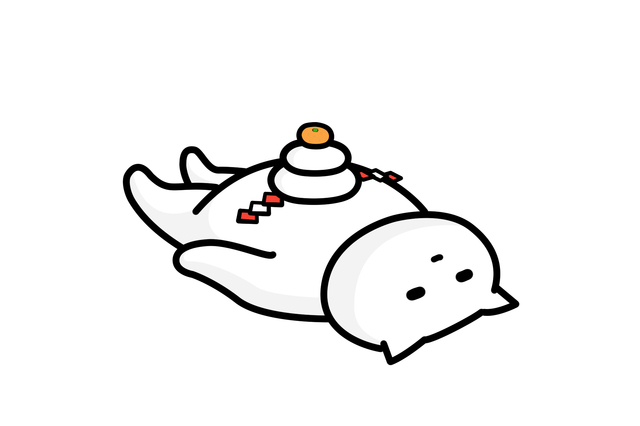仮説検証の必要性について改めて訴える「求められる仮説検証」シリーズの第3弾。前回に引き続き、「戦略仮説の検証」とはどういうことを行うものなのかを具体例を使って紹介したい。
※この時同時に、このメーカーとしては「家電量販店で販売するメーカー独自品ビジネスをいかに急速に広げていくか」という別の課題も追求することになったのは言うまでもない。
この汎用品の需要がこのあと細っていくことは明白だったが、まだまだ主力商品ではあるし、顧客である企業Xとの取引は他にも色々とあるため生産の優先度はそう下げるわけにもいかなかった。C側でできることは限られており、過剰な生産をしない、無駄な在庫を抱えない、という基本方針を固めた上で策(打ち手仮説)を練った。
具体的には、1)(顧客からの需要見通しに頼らずに)自らの需要予測手法を確立すること、2)顧客からの発注頻度を上げてもらうよう交渉すること、3)その発注量に応じて生産ロットを小さくし、生産ラインも順次縮小すること、4)部品在庫も従来以上に厳密に管理すると共に、下請けの部品メーカーには毎月の生産見通しを伝えて影響を最小限に止めること、といった策を次々に決めていった。
これらの打ち手仮説はそれぞれ具体的方策に落とし込む過程で検証・検討を繰り返して、精度を上げていった。小生が特に深く関わったのは、経緯からして1)の「自らの需要予測手法を確立する」という打ち手仮説の具体的な策定だった。
課題仮説の検証としては「需要落ち込みタイミングと量販店の展開時期の一致」だけで十分だった訳だが、打ち手としての需要予測手法はさらに細かい条件をモデル化する必要があり、その前例もない中でかなり悪戦苦闘した。
まず企業Xからのヒアリングが(実績のブレイクダウン以外には)ほとんど役に立たないことは前提とせざるを得なかった。そしてその時点で存在する各地の量販店マップと開店時期、そして量販店ができてからの地域の需要に関する過去の実績数値の推移データは掴めていた。あとはその主要なファクターが何か(複数あるはず)を突き止めれば、ある程度実践的な需要予測モデルができると考えた。
5.打ち手仮説の検証・ブラッシュアップ
幾つか思いつくファクターと実績数値の相関性(統計学でいうcorelation)を片っ端から試してみた。ある程度までの相関性を持っているファクターを組み合わせて需要計測モデルをくみ上げ、各地域での過去の実績数値を当てはめてモデルの有効性を検証することを繰り返した(今なら多分、データサイエンス技術に基づくAIを使ってすぐに適正なファクターと係数を割り出せると思うが、当時はそんな『魔法の杖』は存在していない)。
経営・事業戦略
2025.01.09
2025.01.22
2025.03.05
2025.04.23
2025.05.15
2025.06.04
2025.08.18
2025.09.17
2025.09.24
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る