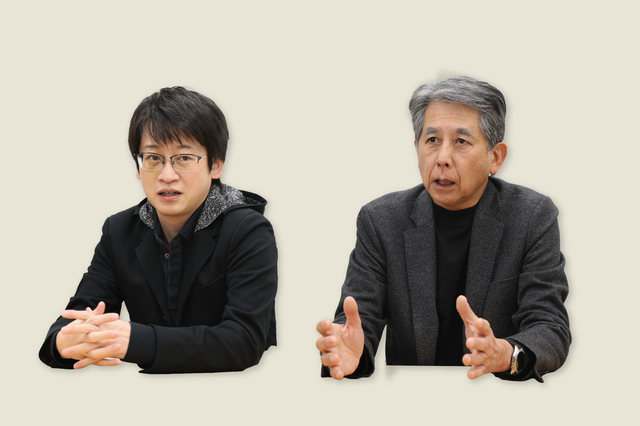AI技術の覇権をめぐる米中間の競争は、その開発に対する政策面でのガバナンスの違いによって新たな局面を迎えている。
現在、生成AIの開発と商業化の分野において、米国と中国が圧倒的なデータ量と資本力、そして人材をもって世界をリードし、激しく拮抗している。
具体的には、米国はOpenAIの「GPT」シリーズやGoogleの「Gemini」に代表される汎用大規模モデル(LLM)の技術革新を牽引し、基盤技術とエコシステムを支配している。これらの多くはモデル構造を非公開とするクローズド型が主流である。
一方、中国はBaiduの「文心一言(ERNIE Bot)」やAlibabaの「通義千問(Qwen)」、そしてDeepSeekが圧倒的な低価格で米国産に匹敵する高性能モデルを実現したことなどで存在感を示している。さらに、中国勢はモデルの重み(ウェイト)を公開するオープン型を主流としており、これが国内外で急速な普及とカスタマイズを促し、エコシステムの急速な拡大を予想させている。
特に画像認識技術や自動運転技術といった特定分野では、国家の強い統制とデータ収集力を背景にした中国が、ここまでの段階では優位性を発揮している。
中国の過去の優位性:国家統制の功罪
中国のAI開発は政府主導で推進され、膨大な国民データへのアクセスと迅速な社会実装が可能であった。監視カメラ網の画像認識や交通データを活用する自動運転技術では、この統制力が開発スピードに貢献した側面は否定できない。
しかし、この強力なエンジンが、生成AIという新たな技術領域では、一転して足かせとなりつつある。
生成AIの真価は、多様な意見や情報を学習し、創造的かつ批判的な応答を生成する能力にある。中国が抱える最大の問題は、「政府批判を許さない」という厳しい検閲だ。モデルの学習データやアウトプットから不都合な情報を排除する作業は時間とコストを増大させ、AIから自由な表現や汎用性を損なう。
これは、表現の自由が保障された環境で多様な情報を取り込める米国と比べ、技術的な競争力、特に創造性の面で不利に働く要因となる。それは普及先の海外ユーザーにとっても潜在的に大きな障害となろう。
競争軸は、単なるデータ量から「モデルの質と多様性」へとシフトしており、「検閲の壁が中国のイノベーションの幅を狭めている」と指摘される所以だ。
米国側の不確実性:政策の不安定さ
一方、米国もまた、異なる形のガバナンスの問題を抱えている。現在のトランプ政権に見られるような場当たり的かつ予測不可能な政策立案のあり方は、長期的なAI投資に不透明感をもたらしている。そもそも、最高指導者の恣意性が政策の予見性を大きく左右するという構造的なリスクが存在する。
経営・事業戦略
2025.05.15
2025.06.04
2025.08.18
2025.09.17
2025.09.24
2025.10.20
2025.11.12
2025.11.19
2026.01.16
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る