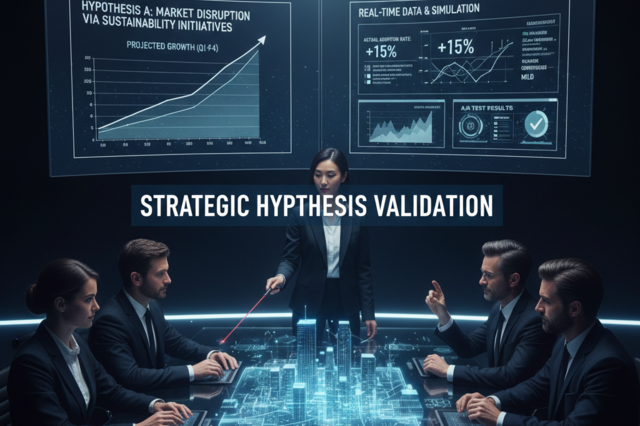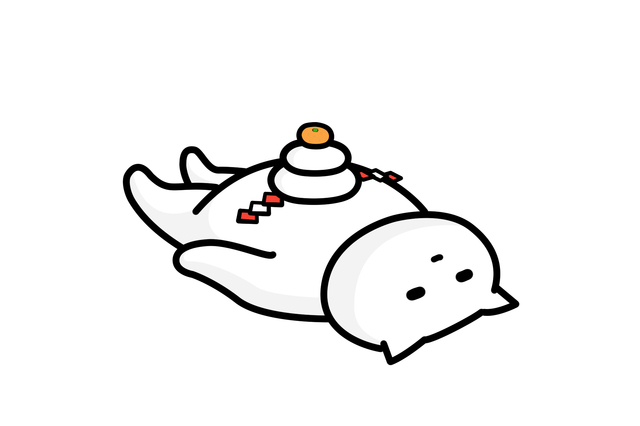仮説検証の必要性について改めて訴える「求められる仮説検証」シリーズの第3弾。前回に引き続き、「戦略仮説の検証」とはどういうことを行うものなのかを具体例を使って紹介したい。
前々回の記事にて「戦略仮説とは」を語り、前回の記事で戦略仮説の検証の具体例を語った。とはいえ一つの例だけではピンと来ない人もいると思うので、今回さらにもう一つの具体例を説明したい。
前回の事例は「クライアントが持つ特有技術を基に新規事業を開発する」という戦略仮説に関わるものだった。今回は弊社のもう一つの得意パターンである「クライアントの既存事業の中核的な問題を解決することで収益を改善する」という戦略仮説とその検証について採り上げたい。やはり当該事例に係るクライアントの固有情報をなるべく伏せながらの解説となることをご了解願いたい。
1.ケース概要
まずこのケースの概要を示す。クライアント企業(以下、Cと呼ぶ)は当時、1部上場のメーカー。全体の売上の3~4割を占めていた主事業は一般ユーザー向けの汎用的な通信機器のOEM製造で、典型的なB2Bビジネス。巨大な企業(以下、企業Xと呼ぶ)を絶対的な販売先とするものだった。市場全体でみても、その企業Xの設計による同社ブランド製品が圧倒的なシェアを占めていた。
当時、市場は大きく変動する「とば口」にあった。各メーカー独自の製品が高機能化かつ多様化し、消費者の人気が急激に高まっていた。その結果、それまで市場を制覇していた企業Xからの汎用製品の発注量は期を追うごとに減っていた。
それまでCは期初に先立ち、その企業Xからの年間販売計画を受け取り、それに基づく年間生産計画を綿密に策定、粛々と生産・納品することで大きなビジネスが成り立っていた。いわば「計画経済」が成立していたのだ。しかし企業Xからの実際の発注量が期を追うごとに減るだけでなく、期中でも期初の販売計画からどんどん乖離するようになり、大きな問題となっていた。
当初Cでは在庫の置き場所の確保や生産タイミングの調整といった小手先の対応に掛かり切りだったようだが、やがて本格的な対策を考える必要があることに気づいた。
まずは顧客窓口である企業Xの調達部門に相談しても、当該部門は営業部門からの注文数を伝えているだけだから先の見通しについて何も分からず、答えようがない。
本社営業部門でも全国の支社からの数字を足し合わせているだけなのは同じで、足元である東京の各支店から上がってくる直近の販売状況が分かるだけましというレベル。期初の販売見通しからの乖離は全国の支社間でずいぶんと差があったのだが、その背景要因はまったく掴めていなかった。
経営・事業戦略
2025.01.09
2025.01.22
2025.03.05
2025.04.23
2025.05.15
2025.06.04
2025.08.18
2025.09.17
2025.09.24
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る