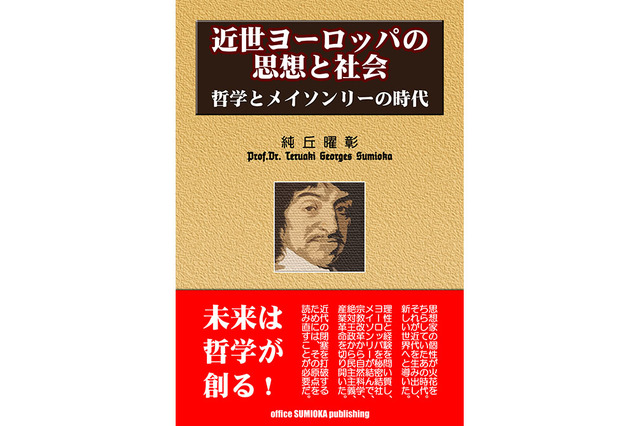/産業革命は、たんなる生産経済の効率化でなく、社会構造を根底から変えた。/
彼は、まずはじめにこの技術を使って小銃を量産することにし、アメリカ軍から一万丁受注の契約を結びました。しかし、なにぶんこのような大量生産など、歴史始まって以来のことです。工場の建設や調整に手間がかかり、二年以上かかってできたのは、わずか五百丁にすぎませんでした。それでもアメリカ軍は、その部品の互換代替性という発想を高く評価し、期限を延長した上に、その代金十三万四千ドルも先払とすることにしました。そして、アメリカがナポレオン戦争に対英参戦した一八一二年には、米軍との二度目の契約で一万五千丁もの受注を取り付け、ホイットニーは軍需産業の一大財産家へと成上がっていったのです。
そのしばらく前の一七九四年、混迷するフランス革命の中、いまだ急進ジャコバン派の砲兵士官にすぎなかったナポレオンは、予想されるヨーロッパ各国との長期戦のために、一万二千フランもの賞金を掲げて食料保存方法を公募します。これを聞いたパリの菓子職人アーペルはこの研究に没頭し、十年後の一八〇四年、真空の瓶詰工場を造り、皇帝となったナポレオンから先の賞金を得て、軍隊用食料の加工を始めます。そして、その後、一八四七年、金属の打抜き技術によって缶が量産され、主流は瓶詰から缶詰へと移っていきます。いずれにしても、この真空保存法は経験的なもので、その原理の解明は、十九世紀後半のパストゥールの研究を待たなければなりません。
ところでまた、ミシンは、一八二九年、フランスのティモニエが発明しました。彼は、さっそくにフランス軍の大量の制服を受注して、そのために八十台の機械を揃え、生産を始めようとしますが、失業を恐れた仕立屋たちの暴力的な妨害を受けることになってしまいました。
しかし、こうして、同じ小銃を持ち、同じ制服を着、同じ瓶詰を食べる軍隊が登場してきます。そして、これこそ、その後の均質的な大衆の姿の原型ではないでしょうか。
このように、工場とは名ばかりの水車小屋の手工業から、煙突から蒸気機関の煙をもうもうと上げ、自動的に製品が量産されてくる今日のイメージの大工場の機械工業の入口へたどりつくころには、すでにもう十九世紀も半ば近くとなってしまっていました。イギリスは、たしかに産業革命の助走において、はるかに先んじてスタートしましたが、産業革命は、農業から工業への産業全体のシフトを要するために、すべての条件が整うころには、他の国々もすぐ後に追いついていたのです。たとえば、一七七六年のアメリカ独立宣言の時にはすでに、アメリカの溶鉱工場の数は、イングランドとウェールズの溶鉱工場の数を合わせたよりも多くなっていました。そして、逆に、一八世紀末のイギリスにおいても、動力機械による工場など、わずかに数えるほどしかなかったのです。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る