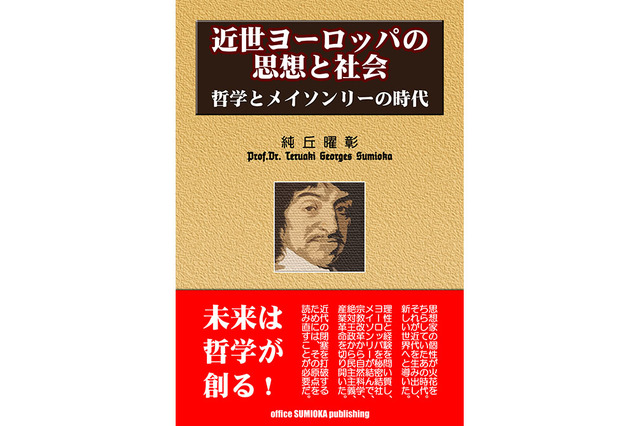/産業革命は、たんなる生産経済の効率化でなく、社会構造を根底から変えた。/
こうして、アメリカでもどうにか企業が成立しますが、イギリスのような社会的分業が可能なほど国内経済が成熟しておらず、製造業者は、運送や小売など、その周辺業務まで一手に担うことを余儀なくされたのです。とはいえ、人々の生活は、いずれも開拓民のそれであり、そこで必要とされているものは、先述のシャベルや斧のように、どこでもほぼ同一でした。このため、彼らもまた、イギリスの産業同様、それぞれに少数品種・大量生産によるコストダウンが可能になったのです。
これに対して、フランスやドイツでは、さらに条件が良くありませんでした。都市部はともかく、地方部では、それぞれの地方ごとに市場が分立閉鎖的で、ましてや、ドイツでは、農民層が貧しく、市場たりえるものではありませんでした。このような状況では、製造周辺業務の社会的分業も、少数品種・大量生産もできたものではありません。もちろん、このような国々でも技術企業家は生れてはいましたが、その不足は、商業者や金融業者が企業家として事業投資することで補わざるをえませんでした。しかし、それは、現場での技術の発展を促進するものではなく、せいぜい、かつてからの問屋制工業の延長のようなものでしかありませんでした。
また、このように事業投資する商業者や金融業者すら不足するドイツでは、まず、事業投資する銀行そのものも、株式会社として資本をかき集めて設立される必要がありました。また、国家として必要不可欠な鉱山業や鉄工業などは、やむなく技術官僚によって国営で管理運営されましたが、このことがまた、事業の自由な発展を阻害する原因ともなっていました。
このようにして、各国の経済状況に合せて、それぞれ独自の企業形態が成立してきます。すなわち、イギリス的な技術企業家の個人単一事業企業、アメリカ的な株式会社の大量製造販売企業、フランス・ドイツ的な商業者・金融業者・銀行・国家の投資事業企業です。言うまでもなく、国際市場が成立し、事業が拡大するにつれて、やがて個人企業家の再投資程度では資本は不足するようになってしまいます。こうして、時代は、株式会社や金融資本の時代へと移っていきます。産業革命は、たしかに個人的な技術企業家に始まりましたが、近代に入って、個人の役割はもはや次第に終わりつつあったのです。
Amazon.co.jp: 近世ヨーロッパの思想と社会(改訂版): 哲学とメイソンリーの時代 : 純丘 曜彰: 本
純丘曜彰(すみおかてるあき)大阪芸術大学教授(哲学)/美術博士(東京藝術大学)、東京大学卒(インター&文学部哲学科)、元ドイツマインツ大学客員教授(メディア学)、元東海大学総合経営学部准教授、元テレビ朝日報道局ブレーン。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る