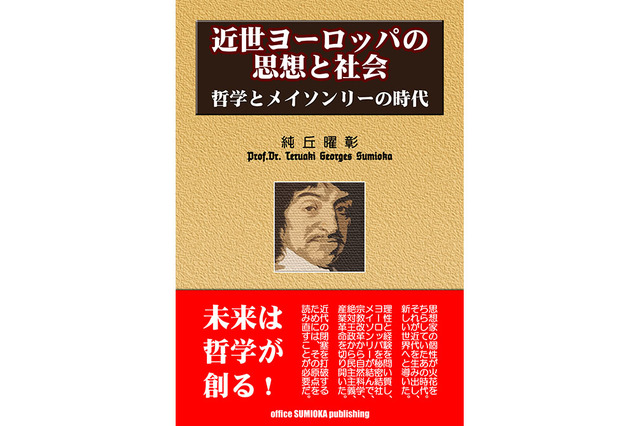/産業革命は、たんなる生産経済の効率化でなく、社会構造を根底から変えた。/
たとえば、「人種のるつぼ」と言われるアメリカにおいても、アイルランド人はカトリックであることをやめませんでしたし、中国人はチャイナタウンで中国語を話し、また、黒人は解放されてもあくまで奴隷扱いで、インディアンは居留区に押し込められました。他人が向上すれば自分が没落してしまう、だから他人を差別する、このように均質な人間ほど他人を差別したがるもの、いや、差別しなければ自分であり続けられないもののようです。そしてまた、それは、誰もが、スクルージのように「自分のやっていることがわかっていたら、他人のことなんか口出ししている暇はないんだ。」と考えている「孤独な群集」の時代の始まりでした。
9 技術企業家
その他大勢の労働者や小市民がこの近代の恒常的革新に翻弄される中、この恒常的革新の波に乗り、波を作った人々は、すでに国際的に活躍をするようになっていました。当時の技術先進国であるイギリスは、一八二五年まで技術者の出国を、一八四二年まで機械や設計図の輸出を法律で禁止していましたが、およそ効果はなく、二五年には二千人以上のイギリス人技術者が国外で働き、四十年の正規の機械輸出だけでも六十万ポンドを越えるほどでした。このように海外でも活躍した技術者の中には、優れた企業家も多く含まれ、たとえば、中ぐり旋盤を考えたり鉄橋や鉄船を作ったりしたウィルキンソンなどもその一人です。また、イギリスのアークライトの工場で修業した技術者サミュエル=スレーターは、二一歳の時にアメリカへ密出国し、かの地での工場生産の基礎を築きました。彼は、記憶を頼りにアメリカでアークライト紡績機を再生したのです。
一方、大陸諸国の企業家たちも、こぞってイギリスへと技術研修に渡航し、また、おおいにイギリス人技術者を工場や学会に招聘しました。また、このような技術吸収には、政府も富国強兵のために協力しました。その第一が、工科学校の設立です。
フランスでは、革命戦争中にあって、生産のための技術者や軍隊のための砲工兵の不足の解消はまさに緊急の課題でした。そこで、国民公会政府は一七九五年、「エコール=ポリテクニーク(理工科大学校)」が設立されます。その資金の不足は、ルーブルの絵画を売却して調達されました。技術というものが、当時それほど必要とされていたのです。そして、その学校の開校直後の名前が「公共事業中央大学校」であったように、いわゆる数学や化学、力学などの理科系学科よりも、むしろ、機械学、土木学、鉱山学などの実学の方が重視されていたのです。そして、この大学校を頂点に、各地に初等中等の技術教育機関が整備され、国家的に技術者の養成が図られました。
歴史
2024.10.21
2024.11.19
2025.03.08
2025.06.12
2025.07.16
2025.10.14
2025.11.03
2025.11.14
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る