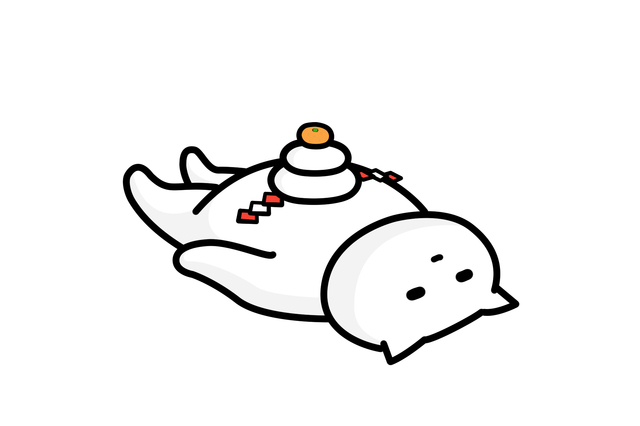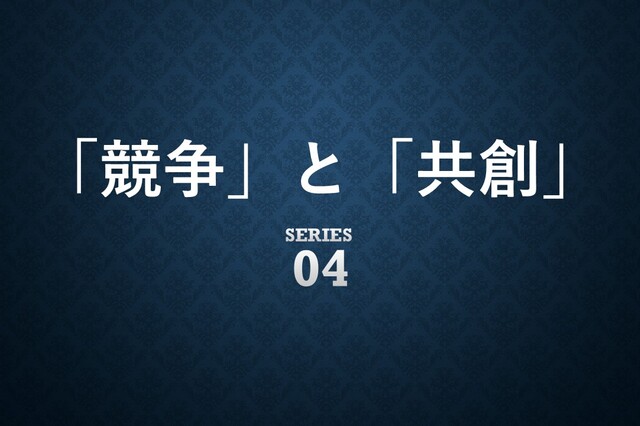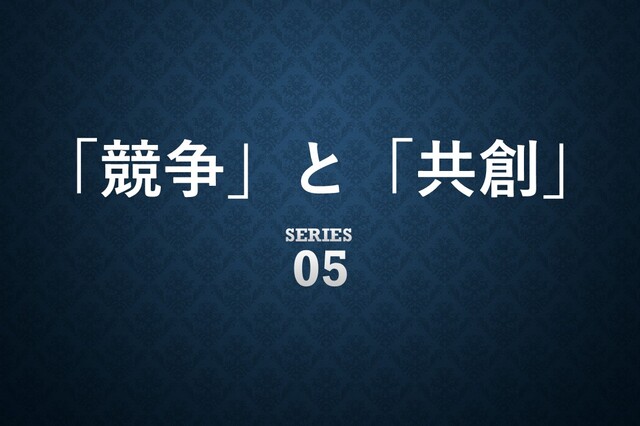仮説検証の必要性について改めて訴える「求められる仮説検証」シリーズの第5弾。「戦略仮説の検証」がどういう状況やプロセスにおいて求められるのかについて述べたい。
こうしたリスクを考え合わせると、「戦略策定のプロセス全般にわたっての仮説検証が求められる」ということが正解であるとお分かりいただけよう。
では、戦略策定のプロセス全般にわたって、どれほどの頻度で(つまりどれほど細かい段階ごとに)検証を進める必要があるのだろうか。
理想的には「仮説が生じる度に」検証を行い、それを積み重ねるのが、「仮説が間違っている場合」のリスクを最も小さくできるのは間違いない。
例えば新規事業なら「この辺りに事業ネタがありそうだ」という思いつきの段階で、「本当にそれほどの市場性があるのか」を改めて調べる、といった検証を行う。そして市場環境分析が少し進んだ3C分析辺りの段階でも、いったん定めた仮説に対し「本当にそうか?」と確かめる検証を行う、といった具合だ(検証方法については割愛する)。
ただ、こういった進め方だと新規事業開発に慣れていない人たちにはとてつもなく煩雑に感じられるだろうし、なかなか進捗せずに途中で嫌になるかも知れない(本当は、やり方次第で意外と素早く検証が終わることも少なくないのだが)。外部コンサルタントに支援を頼む場合でも、通常は余計に時間が掛かるためコスト高になる気がして避けたくなるだろう。
そこで実務的には、ある程度仮説を積み重ねて切りのいい段階に入ったところで、まとめて主な仮説を検証するのが普通だ。具体的には、新規事業なら市場環境分析が終わりSWOT分析等で示唆説を引き出した段階、もしくはSTP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)の検討をしてターゲット市場仮説を引き出した段階辺りだ(典型的な検証方法としては市場に詳しい専門家に分析結果をぶつけるなどだ)。
もちろん、これだけで終わってはいけない。その後も『選ばれる理由』を定めたらその仮説を顧客候補にぶつけて本当に意味を持つのかを検証しなくてはいけないし、マーケティング政策としての4P/4Cを定めたらそれが本当に有効なのかをできる限り机上で検証しなくてはいけない。最終的には市場での試行にて検証することが欠かせない。
新規事業のケースに限らず、既存事業での戦略見直しや課題解決についても同様だ。そもそも、現状をいったん把握・分析した段階で見えている(と思った)課題仮説が正しいとは限らない。
例えば、在庫管理のやり方が稚拙だから生じていると当初思われていた過剰在庫問題が、実は需要の伝わり方に段階が多いことから生じる「ブルウィップ効果」だったというケースはいくらでもある。
経営・事業戦略
2025.03.05
2025.04.23
2025.05.15
2025.06.04
2025.08.18
2025.09.17
2025.09.24
2025.10.20
2025.11.12
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け38年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る