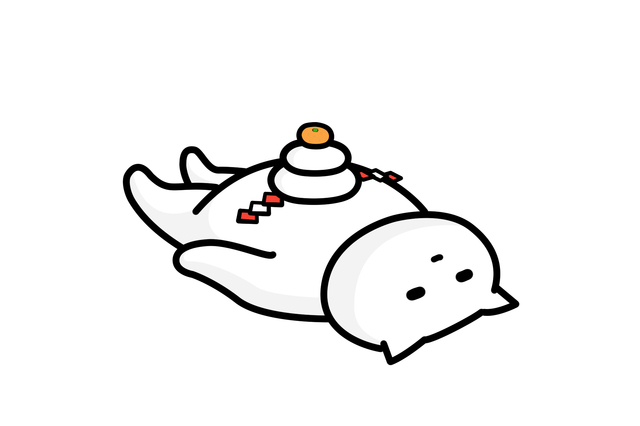世の中にある「折角なのに惜しい!」シリーズの第2弾は、駅などの構内通路での通行方向表示。首都圏と大阪では、右側歩行を指示することはかえって混乱の元。
朝夕のラッシュに限らず人通りの多い首都圏の駅構内やデパート等の通路ではひっきりなしに人が行きかい、初めて見た外国人や田舎から出てきたばかりの人には相当な驚きのようだ(海外で有名なのは渋谷駅前のスクランブル交差点)。「よくぶつからないものだ」と。
でも実際には(スマホ歩きのせいか)うっかりぶつかっている人たちも時折いるし、危うくぶつかりそうになって何とか避けるといった場面を目にすることは決して少なくない。
利用者が多い通路なのに、そうした場面が少ない場所と多い場所があることはご存じだろうか。もちろん、時間帯によって人の流れがほとんど一方通行になるような所だと動線も何もあったものじゃないので、これは除外するとして。
人とぶつかりそうになることが少ない通路というのは、構内動線がよく考えられていて人の流れがスムーズだということだ。こうした所では通勤ラッシュの時間帯でも多数の人の流れに乗っているだけで、混乱なく乗り換えや出入りができるようになっている。
その動線を作るポイントになっているのが、足元や頭上に表示されている進行方向を示す矢印や「ここでは○側通行」という表示板だ。実際、路上や階段にプリントされた矢印はシンプルながら実に分かりやすい「アイコン」だ。
ところが、同じように進行方向を示す矢印や「ここでは○側通行」などがしっかりと表示されていながら人の流れがスムーズでなく混乱しがちな通路が首都圏内には幾つもある。これは動線設計に失敗しているためだが、往々にして通路を右側通行にしている場合の入り口付近や他通路との合流部分で発生しがちだ。
もしくはそれほど多いわけではないが、駅の改札口での人の出入りパターンとその先の通路の通行方向とが入れ違いになっている場合などだ(改札口を出るときは右側通行なのに、通路では左側通行を指示されているようなケースで、小生のよく使う地下鉄のM駅がまさにそう)。
ではなぜ通路を右側通行にしている場合に人の流れがスムーズでなくなるのだろうか。
都心の比較的狭い通路や歩道を通る際、特に何の通行方向指示もない場合には、左側に寄って逆方向から来る人とすれ違おうとする人が多数派だという行動観察結果が幾つもあるそうで、どうやらそれと関係しているようだ。
つまり自然に任せておけば、首都圏の歩行者の多数は左側通行しようとするのに、通路の管理者がその逆方向を指示しているため、表示通りに進もうとする人と、表示を無視して進もうとする人がぶつかりそうになるわけだ。
社会インフラ・制度
2015.05.12
2015.05.26
2014.12.05
2014.12.20
2015.01.29
2015.01.26
2014.09.23
2014.10.01
2014.09.11
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る