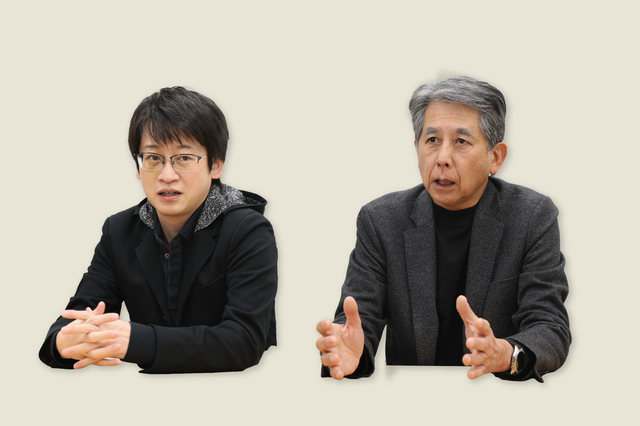仮説検証の必要性について改めて訴える「求められる仮説検証」シリーズの第6弾。これまであまり強調してこなかった「事後検証」について述べたい。
戦略実行時に設定したKPIを、四半期ごとや半年ごとに定点観測し、未達の理由を掘り下げる。数値の達成度を確認するだけでなく、外部環境の変化や社内体制の問題といった、戦略仮説の前提となった背景要因を分析することが肝心だ。
2.アフターアクションレビュー(AAR)
米軍などで行われる仕組みだが、ビジネス向けにも応用できる。
- 当初の計画は何だったか
- 実際に起こったことは何か
- なぜ違いが生じたのか
- 次にどう活かすのか
という4つの質問をオペレーション(作戦行動)実施直後にチームで検討する。短時間で具体的な学びを抽出できるのが利点だ。
3.第三者評価
外部の有識者や別部署を巻き込み、バイアスのかからない評価を行う方法。内部の関係者だけでは見落としがちな構造的な問題を浮き彫りにできる。特に大規模プロジェクトでは有効である。
4.ナレッジ化と共有
検証の結果を「報告書」で終わらせず、知識として形式知化し、社内のナレッジベースに蓄積する。これにより、別部署や次世代プロジェクトにも学びを引き継ぐことができる。
【事例:ある大手企業の取り組み】
弊社のクライアントである大手企業では、新製品投入のたびに必ず「ローンチ後1年間のクォーター(四半期ごとの)レビュー」を実施している。販売実績、顧客フィードバック、サプライチェーンのトラブル有無を整理し、責任者が経営層に報告するのだ。
結果として「不具合が小さいうちに修正する」「次の製品企画に素早く学びを取り込む」仕組みが定着している。担当者にとっては面倒な側面もあるが、組織全体の学習スピードは格段に高まった。
【結び】
戦略仮説の検証は、「事前」と「事後」の両輪で初めて機能する。事前検証で立案の質を高め、事後検証で実行の学習を積み重ねる。この二つを車の両輪のように回すことこそ、戦略の成熟と組織能力の強化につながる。
ここで重要なのは、「事後検証を事前に計画しておく」ことだ。実行直後にレビューを行えば、問題点を迅速に修正でき、組織は同じ轍を踏まずに済む。検証の仕組みを内蔵させることで、「やりっ放し文化」を断ち切り、学習する組織への転換が可能になる。
これまで強調してきた「事前検証」に加え、今回述べた「事後検証」の仕組みを組み込むことで、企業は戦略策定を単なる一過性の儀式に終わらせず、進化し続ける実効性あるものへと育てていくことができるだろう。
日沖 博道(ひおき ひろみち):パスファインダーズ株式会社 代表取締役、経営戦略研究会「羅針盤倶楽部」コーディネーター&アドバイザー。
経営・事業戦略
2025.05.15
2025.06.04
2025.08.18
2025.09.17
2025.09.24
2025.10.20
2025.11.12
2025.11.19
2026.01.16
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長
「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/
 フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る
フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る