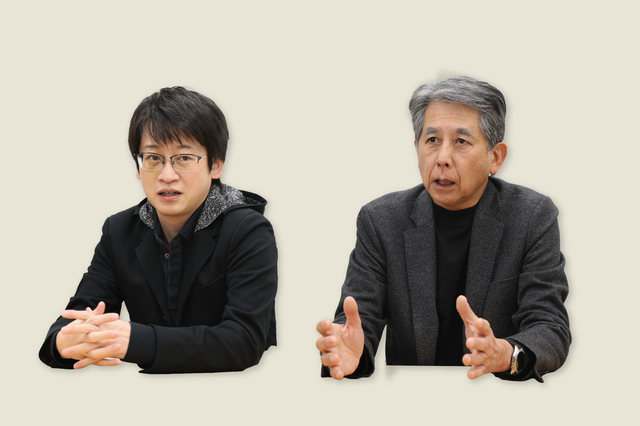2018.06.25
サービス価格競争の抜け出し方 ~日本サービス大賞 受賞事例に学ぶ~ |service scientist's journal
松井 拓己
サービスサイエンティスト (松井サービスコンサルティング)
日本のサービスの生産性が低いことに注目が集まっています。その原因のひとつが、これまでのサービス競争の仕方にあると思います。多くの企業では、スペックや価格での競争ばかり進めてきました。これでは、事業は疲弊する一方で、生産性が低いのも当然の結果といえます。今こそ、自己犠牲のサービス競争から抜け出すべきなのです。
日本最高峰のサービス表彰制度である日本サービス大賞の第2回受賞サービスの発表が6月28日に迫っています。この表彰制度は、サービス産業生産性協議会(SPRING)が主催する優れたサービスを表彰するもので、業種や業界、地域、規模にかかわらず、様々なサービスが表彰の対象になっています。内閣総理大臣賞をはじめ、各大臣賞および優秀賞が隔年で表彰されます。第2回からは、JETRO理事長賞も加わり、日本の優れたサービスのグローバル展開についても注目が集まります。
さて今回は、第2回日本サービス大賞の表彰に向けて、前回の第1回日本サービス大賞を受賞サービスの中から、テーマに合わせた共通点を見出してみたいと思います。テーマは「サービスの価格競争からの抜け出し方」です。
価格もスペックも、自己犠牲のサービス競争
日本のサービスの生産性が低いことに注目が集まっています。その原因のひとつが、これまでのサービス競争の仕方にあると思います。多くの企業では、「いいモノを安く」「いいサービスを安く」と、スペック競争や価格競争を進めてきました。価格やスペックでの競争方法しか思い付かなかったといった方が正しいかもしれません。
しかし今の時代、新しいメニューや機能を開発しても他社にすぐマネされてしまうため、結局はスペック競争も価格競争に追いやられていきます。これでは、事業は疲弊する一方で、生産性が低いのも当然の結果といえます。今こそ、自己犠牲のサービス競争から抜け出すための新たな方向性を持つべきなのです。
旭山動物園とフォレストコーポレーションの共通点
さてここで、第1回日本サービス大賞の地方創生大臣賞を受賞した2つのサービスを紹介します。その共通点から、サービス競争の新たな方向性を見出すことができます。
事例①|旭山動物園
行動展示で、日本を代表する動物園に生まれ変わった旭山動物園。ここはどんな動物園なのかを簡単に説明すると、次のようになります。
――― 旭山動物園には、他のどこの動物園にもいる普通の動物しかいません。しかし、他の動物園では決して味わうことのできない動物との関係性や仕草を味わうことができるのです。―――
動物園の差別化の王道は、動物の種類です。「他の動物園にはいない、珍しい動物がいます。」というのです。最近では動物の種類では、あまり差が付かなくなっています。多額の投資をして、他にはない動物を連れてきて飼育しても、思ったほど来園者数が伸びない可能性が高いのです。そんな中、旭山動物園のアプローチは、サービスの差別化として新たな方向性を示しているといえます。
service scientist's journal(サービスサイエンティストジャーナル)
2022.10.17
2022.10.17
2023.03.07
サービスサイエンティスト (松井サービスコンサルティング)
サービスサイエンティスト(サービス事業改革の専門家)として、業種を問わず数々の企業を支援。国や自治体の外部委員・アドバイザー、日本サービス大賞の選考委員、東京工業大学サービスイノベーションコース非常勤講師、サービス学会理事、サービス研究会のコーディネーター、企業の社外取締役、なども務める。 【最新刊】事前期待~リ・プロデュースから始める顧客価値の再現性と進化の設計図~【代表著書】日本の優れたサービス1―選ばれ続ける6つのポイント、日本の優れたサービス2―6つの壁を乗り越える変革力、サービスイノベーション実践論ーサービスモデルで考える7つの経営革新
 フォローして松井 拓己の新着記事を受け取る
フォローして松井 拓己の新着記事を受け取る