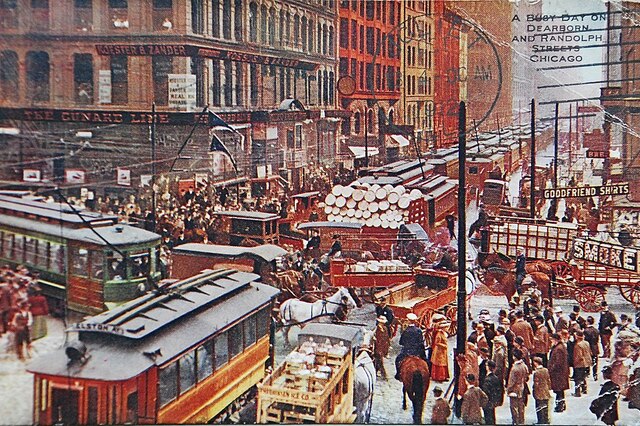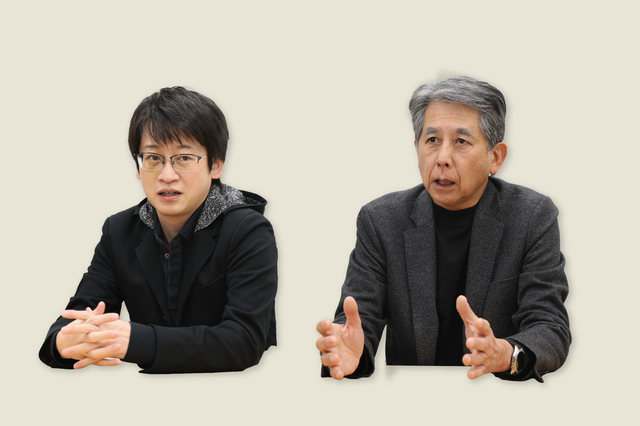/通俗唯物論は、物理的な人種や階級の存在のみを認め、人間の心を否定してしまった。これに対し、文脈や世界観を重視する解釈学が出てきたが、これはこんどは個人の実在しか認めない社会唯名論に陥った。心や社会のように目に見えないものを客観的科学として解明する方法として大きく役だったのは、数学の関数論だった。/
1848年のドイツ三月革命の失敗は、神の摂理と人間の意志を否定し、アナーキズムを「科学的真理」とする通俗唯物論の隆盛を招きました。俗物ライターのスペンサー(35)もまた、実証的研究もなしに、1855年に『心理学原理』を出版しました。その中で彼は、古くさいヒュームのような連想理論によって、人間の心と進化を「科学的に」解明しようと試みました。じつは、彼はこの理論を用いて、骨相学や人種差別を説明しようとしていました。にもかかわらず、この本はやたら売れて、彼の人気を高めました。
「ようするに、スペンサーは、白人と頭の形が違う連中は、みんなバカだ、と言いたかっただけでしょ。庶民は「科学」とかいうのにかんたんに騙されて、いつも差別主義者ほど人気になる」
フリードリヒ・ランゲ(1828-75)は、ボン大学で哲学の私講師でしたが、1864年、労働者のためのインターナショナルができると、その幹事に転じました。しかし、彼は、そこで醜い主導権争いして浅薄な唯物論を振りかざす強引なマルクスに辟易しました。そこで、彼は、1866年にカントを基盤に『唯物論史』を出版し、それが表面的な現象しか扱えない、ことを明らかにして批判し、インターナショナルを去ってチューリッヒ大学の教授になり、新カント主義として多くの学者や学生に影響を与えました。
「労働者であったことすらないような連中が争う労働者協会なんか、だれも本気で奉仕したがらないよ」
ベルリン大学のシュライエルマッハー(1768-1834)はすでに、表現は背景の結果に過ぎない、と述べ、解釈学の必要性を主張しました。その影響を受け、ベルリン大学のディルタイ(1833-1911)も、部分と全体を循環させる解釈学によって、それぞれの背景、すなわち文脈、さらには世界観さえも解釈しなければならない、と考えました。これが自然科学とは異なる精神科学です。どの世界観も自分の絶対的普遍性を主張しますが、じつはそれ自体が多くの相対的なものの一つにすぎません。超越論的な世界観を持たないかぎり、他者の精神の優劣を客観的に評価できず、まして進化の順序で順位付けすることなどできません。
「カント以降のまともな哲学者なら、当然、こう考えるでしょ」
ウィーン大学の元司祭ブレンターノ(1838-1917)は、心理学を解釈心理学と内在心理学に分けました。前者はディルタイと同様の解釈学であり、第三者的なアプローチで、ある人物の様々な客観的なエピソードを集め、その人の内的世界観を再構築します。後者は、人が経験したことの自己説明です。ここで彼は、あらゆる認識は、ある意味では一種の誤解である、とあえて言います。あらゆる認識は対象のみを含むのではなく、つねに自身の世界観に基づく意図としての主観的な判断、感情、あるいは欲求を伴っているからです。
解説
2025.01.23
2025.01.25
2025.07.27
2025.07.31
2025.09.08
2025.09.11
2025.09.21
2025.10.05
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る