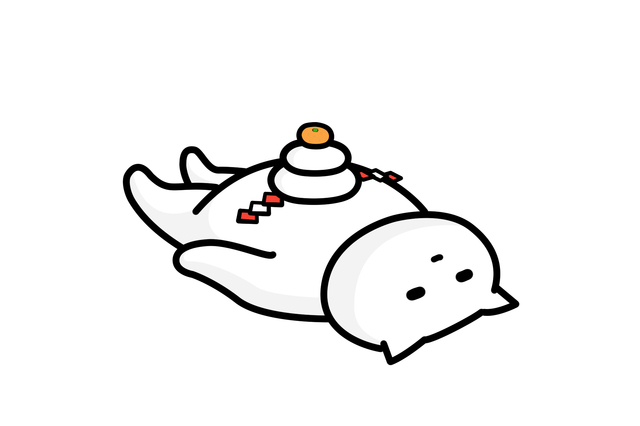/投票率が51%あれば、その政府は支持されている。そして、民選院の議席51%を取れば、それが政権与党である。さらに、その政権与党の中で、51%の議員の支持を取り付ければ、その政権与党の党首であり、その人物は、党の総議席51%をもって首班となる。それどころか、派閥の長の総理経験者、わずか数人の密室談合で、ほぼ決まり。だが、これは、レバレッジを多重にかけすぎだ。だから、政権が不安定で長続きしない。/
昨今、政治学も、原理論ははやらない。国内外、聞屋よろしく、早耳の物知りの方がマスコミでもウケがいい。しかし、諜報機関のスパイでもあるまいに、それって、わざわざ大学で学者がやることか?
とはいえ、根本の政治形態に関してさえ、各国どこも複合的で、おまけに建前と実情にズレがあるせいで、古代以来、百家争鳴。それでもどうにか単純に言えば、独裁政、共和政、民主政、の三つになる。
独裁政は、王様がいちばんわかりやすいが、将軍だったり、総統だったり、メディチ家当主だったり、よくわからない地位でも、ようするにだれかが一人で政治を決められる政体だ。もちろん、この場合も、たいてい合議をする内閣があって、その大臣たちが独裁者に助言する。ただし、この内閣には政治的決定権は無く、そもそも、だれを大臣とするかも、独裁者が任意に決める。
わかりにくいのは、共和政と民主政の区別。どちらも合議政体で、この合議にこそ最終の政治的決定権があり、その議長だろうと、議事進行以上の権限を持たない。民主政は、デーモス(住民)が個別案件ごとに直接に決める。米国の選挙人制度はともかく、本来は国家元首、大統領も国民の直接投票で決めるのが、民主政だ。これに対して、共和政は、専門の政治家たちの政権。貴族院の場合、名家当主が議員資格を世襲する。元老院の場合は、上級官僚経験者が永年議員になる。民選院は、この共和政の議員をデーモスが決める。一般には地域ごとの選挙によるが、いずれにせよ、これは民主政ではなく、共和政だ。「主権在民」とは名ばかりで、共和政議会が最終の政治的決定権を握っている。
日本は、明治維新で、いきなり天皇独裁政とした。江戸幕府ですら、将軍に決定権が無く、実質的には老中幕閣の貴族院共和政だったのだから、いきなり政治経験の無い明治天皇を独裁者に頂いても、かなり無理があった。だから、実際は維新功労者たちの元老院共和政で、これが薩長藩閥の世襲を成し、旧藩主を加えて貴族院となり、また、民選院も開いた。かくして、独裁者、元老院(御前会議)、貴族院、民選院の四つが併設される、という、きわめて不明朗で無責任な折衷政体となった。おまけに、西南戦争から日清日露、第一次世界大戦とともに、元老院の中でも、陸海軍人上がりが勢力を増し、元老院はもちろん天皇さえ、これを制御できなくなる。
これが戦後に至っても整理されず、軍閥に代わって政党が加わり、いよいよややこしいことになった。とくに、戦後、あまりに急激な革命的「民主化」で、単純な民主政、つまり大統領政を採れば、日本が共産化することが確実だったため、冷戦を見据えたGHQ、それに協力する一派は、巧妙に死に票を創り出すしくみを考え出した。
解説
2024.08.26
2025.01.23
2025.01.25
2025.07.27
2025.07.31
2025.09.08
2025.09.11
2025.09.21
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る