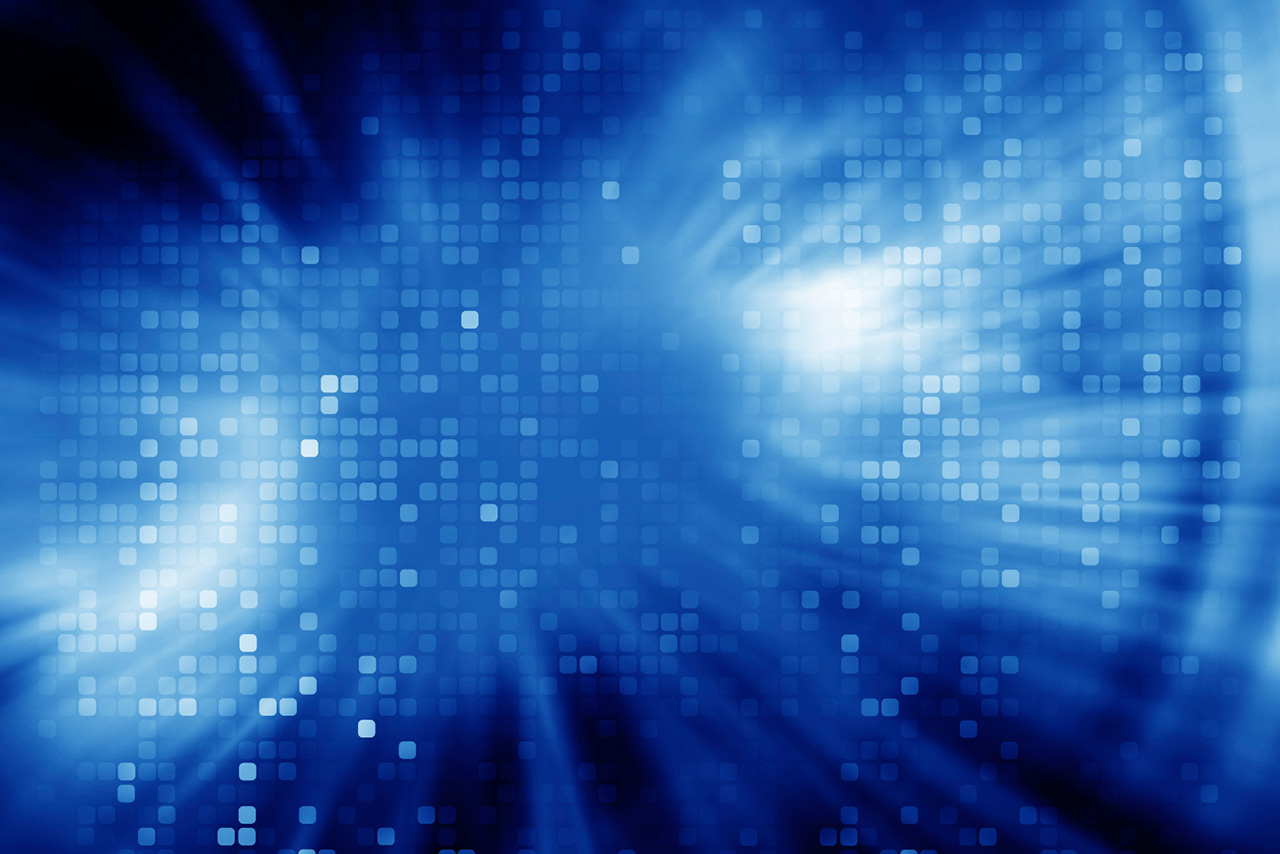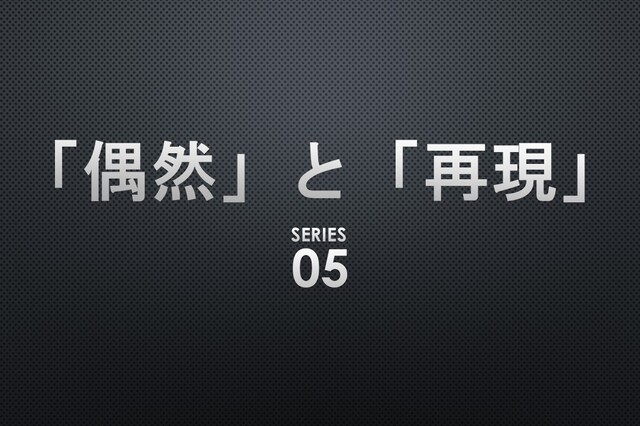日本では、大手原糸メーカーがアパレルや小売店と連携して、消費者に訴求ずくために、マーケティング活動を展開した。マスプロモーション全盛の時代には有効に機能したマーケティング活動も時代の変化と共にポジションが低下していった。
2.日本におけるマーケティング室の役割
日本の「マーケティング」は、紡績や合繊メーカー等の川上の大手メーカーからスタートした。彼らは、最終消費財ではなく、中間素材の供給者である。しかし、大量生産した織物を大量消費してもらうには、直接消費者に働きかける必要がある。そこで、アパレル企業や大手小売店とのタイアッププロモーションを行ったのである。常に、消費者と接しているアパレル企業や小売店にとっては、営業活動や商品企画そのものがマーケティング活動であり、あえて「マーケティング」という専門セクションを必要としなかった。
川上の原糸メーカーは、消費者への直接的なマーケティング活動ができなかったために、自社が行うべきマーケティング活動の内容をアパレル企業や大手小売店に伝える必要があった。それには、大手アパレル企業と連動した百貨店の店頭プロモーションが効果的であった。
また、自社製品をやみくもにPRしても宣伝効果は見込めない。社会性や時代性に訴求するテーマが必要であり、そのためにはビジネス環境、消費者意識の変化の分析、海外トレンド情報の分析等が不可欠だった。こうした活動はアパレル企業や小売店にも歓迎された。大手原糸メーカーが行なう店頭プロモーションや販売促進キャンペーンは同時にアパレル企業や大手小売企業の利益に貢献した。また、社会的ステイタスが高く、学歴の高い優秀な人材が揃っている原糸メーカーが行なう「マーケティング」は、アパレル企業や大手小売企業にも勉強になった。ある意味では、科学的なビジネスを教えるビジネススクールの機能も果たしていたといえよう。
原糸メーカーが行なうキャンペーンは、マスプロモーション全盛時代には非常にうまく機能した。しかし、大手アパレル企業がNB(ナショナルブランド)を展開し、各ブランドが差別化を目指すようになると、次第に原糸メーカーのマーケティングの影響力は低下していった。そして、マーケティング室もプロモーション活動から展示会等の企画運営へと役割が変わっていったのである。
やがて、百貨店にも自らトレンド分析やMD分析を担う商品研究所が作られるようになり、大手百貨店独自の「マーケティング」を展開するようになった。しかし、百貨店ビジネスは大手アパレルの支配力が強く、「マーケティング」も海外のトレンド情報の編集の域を出なかったために、百貨店の「マーケティング」が強い影響力を持つには至らなかった。
大手アパレル企業もマーケティング室を創設したが、その業務内容は、多くの場合は海外トレンド情報の分析、新ブランド開発のための事前調査、プロモーションのための市場調査やアンケート調査等であった。大手原糸メーカーのように他社を巻き込む必要がなかったために、どうしても社内の調整役としての役割に限定され、社会的影響力を持つには至らなかったというべきだろう。(続く)
「中国マーケティングチーム」創設の勧め
2008.04.12
2008.04.12
2008.04.12
2008.01.24
2008.01.24