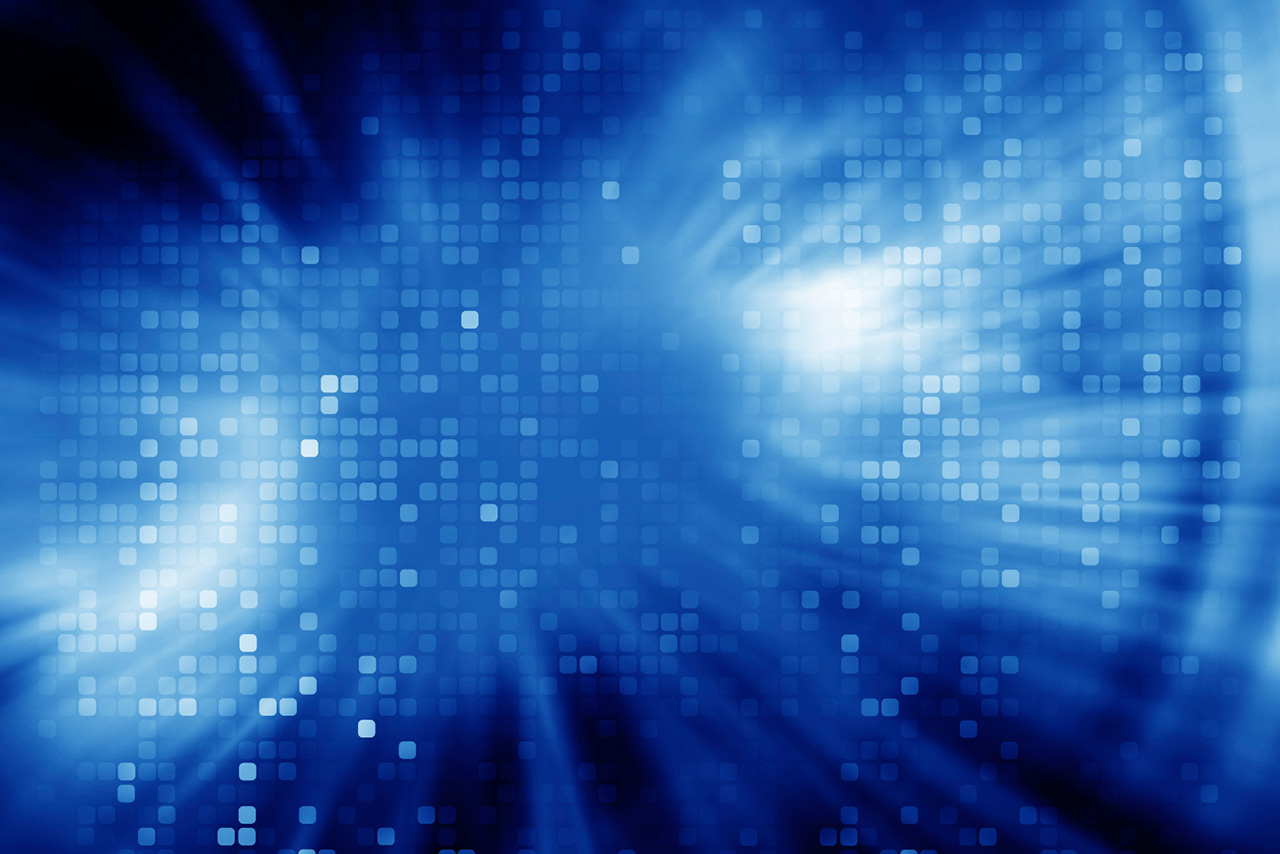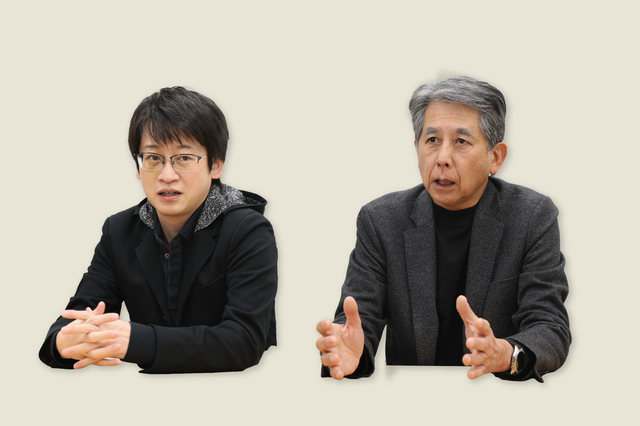最近、開発購買を今後どのように進めていけばよいか、また、データドリブン調達における開発購買の有り方は、どうすればよいか、などの質問を受ける機会が増えています。 これは、昨今、政府の価格転嫁政策に基づく人件費の官製値上げや市況高騰などのコストアップの時代が続き、コスト削減というワード自体が殆ど聞かれない状況が続いているからです。 こういう時代においては、決められたものを(妥当な価格で)安く買うという活動は限界があり、商品企画や開発の上流段階から、コストを作り込み、いかに安いものを買える状況を作っておくか、が必要になってきており、そういう点から開発購買の推進が課題になってます。
最近、開発購買を今後どのように進めていけばよいか、また、データドリブン調達における開発購買の有り方は、どうすればよいか、などの質問を受ける機会が増えています。
これは、昨今、政府の価格転嫁政策に基づく人件費の官製値上げや市況高騰などのコストアップの時代が続き、コスト削減というワード自体が殆ど聞かれない状況が続いているからです。
こういう時代においては、決められたものを(妥当な価格で)安く買うという活動は限界があり、商品企画や開発の上流段階から、コストを作り込み、いかに安いものを買える状況を作っておくか、が必要になってきており、そういう点から開発購買の推進が課題になってます。
開発購買という言葉ですが、開発段階からの購買的な(コストを中心としたQCDの確保のための)活動という定義ですが、この言葉が使われはじめたのは、2002年位からだと記憶しています。
当時は自動車や電機などの、製品原価における外部支出の比率が高い業種を主として、進められていた、原価企画活動と同義だったと言えるでしょう。このような原価企画活動の必要性を、他業種へも
展開していくことや、購買部門が主体となった活動として推進すること、また、提案内容もVEVA提案だけでなく、新規技術や新規サプライヤの提案も含む、など、より包括的な活動として、開発購買が進められ、言葉も定着してきました。
開発購買にかかるコンサルティング支援も、その当時から数年は、たいへん多かったのですが、多くの企業で、その必要性は感じながらも中々上手くいかない状況が続いていたのです。
その理由として、私は2つのギャップを上げています。
1つ目は意識のギャップであり、もう1つは仕組みの適合性のギャップです。意識のギャップは開発部門はコスト削減ではなく、いいものを作りたい、と考えており、購買部門はコスト中心であること。また、もう1つの仕組みの適合性ギャップは、開発部門が欲しい情報がわからない、わかっても提供できていない、提供できても活用できていないなどの格差です。
これらのギャップを埋めるには、仕組みを整備することが必要となります。例えば、開発購買チームのような体制を整備し、開発出身者をチームに配置し、開発部門へ提案活動を行う。開発部門と購買部門を同じフロアに席をおくことで、物理的な壁を取り払う。購買にかかる様々な情報をデータベース化し、それを開発部門に共有する、などの仕組みです。
当時、開発購買にかかるコンサルティングをやっていて、感じたのは、仕組みづくりだけでは、何かが足りない、という点でした。それは、開発購買を上手く機能させるためには、最終的には、人に頼らざるを得ない、という点です。
特に、開発購買を上手くいかせるためには、技術的な知見や経験が、必要となります。中でも、生産技術やサプライヤに関する知見、などは必須であり、それを仕組みだけで埋めるのは、困難です。また、開発購買を上手く推進するためには、これらの知見や経験だけでなく、開発部門に対する提案力やコミュニケーション力、ファシリテーション力など、様々な人間力が必要となります。このような知見・人間力を持つキーパーソンがいないで、単に仕組みだけを整備しても、中々成果も出ず、中途半端な活動に終わってしまうことが多かったのです。
ただ、これからは、新しい方法があるかもしれません。
それは、AIの活用です。
過去に出されたVEVA提案、また、それらの採用可否判断やその理由、効果額などの情報を、データベースに蓄積しておきます。また、ティアダウンによる価値分析なども、データベースに蓄積しておきます。そのデータベースをAIに学習させることで、新たな製品開発や部品開発の時点で、最適な設計思想のアドバイスやVEVA提案、対応可能なサプライヤのリコメンドなどをやってもらうのです。
このように、従来はキーパーソンの知見、経験でしか対応できなかった活動を、AIにサポートしてもらいながら進めることができます。
しかし、知見や経験はサポートできても、人間力は、AIではサポートできません。提案力があっても、それを開発部門が主導して活用してくれなければ、意味がありません。
また、理論上はできそうですが、このようなAIによるユースケースはあまり聞いたことがありませんし、過去の事例をデータベース化できるかどうか、など課題は多く残っています。
このような課題をクリアしながら、数年後にはAIを活用した、新しい開発購買の進め方が、普及し、活用されていくことは、間違いないでしょう。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
調達購買コンサルタント
調達購買改革コンサルタント。 自身も自動車会社、外資系金融機関の調達・購買を経験し、複数のコンサルティング会社を経由しており、購買実務経験のあるプロフェッショナルです。
 フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る
フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る