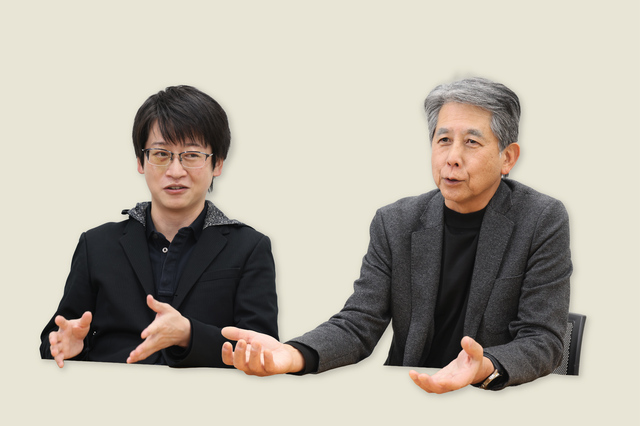事業がうまくいかない時、良からぬブローカーが「バラ色の一発逆転ホームラン的な投機話」を持って来たことはありませんか? 社長なら、会社の財産をどう使おうと文句を言われる筋合いはない、とお考えになったことはありませんか? 実は、大きな大きな”落とし穴”がある場合があります。 今回、「ビジネス・ジャッジメントルール」と「会社財産を危うくする罪」という観点から説明していきたいと思います。
② その事実に基づく意思決定のプロセスが、通常の企業人(経営者)として著しく不合理でなかったかどうか、
といった観点から、経営者の判断が正しかったかどうかを議論するとされています。
会社財産を危うくする罪
しかし、安心はできません。
「ビジネス・ジャッジメントルール」は、あくまで民事上の責任であって、刑事事件ともなれば話は異なります。
世の中の社長さんのほとんどが知らないことなのですが、経営者が「株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分した」場合、会社法963条5項は、実際に「会社の財産」に損害が発生したかどうかを問わず、「5年以下の懲役や500万円以下の罰金」というとてもとても厳しい刑罰を設けています。
通称、「会社財産を危うくする罪」と呼ばれており、投機的な株式の取引や先物取引、また、為替相場などの変動を利用して一時に利益を得ようとする取引などは類型的に見て会社の財産を害する蓋然性が高いことに鑑み、特別に設けられたものです。
会社の財産を使って先物やFXなんかに手を出す経営者が果たしているのか、といった疑問もあるかもしれませんが、実際、平成21年5月、三美電機株式会社の代表取締役(当時)が「会社財産を証拠金として預け、商品先物取引を行って4億円の損失を出した行為」について、横浜地方検察庁が「会社財産を危うくする罪」で立件したという事件があります。
ここで注意しなければならないのは、先に説明した「ビジネス・ジャッジメントルール」は刑事事件には一切適用されないということです。
要するに、
① 「投機的な取引」に関する意思決定をする際、複数の信頼できる専門家の意見を徴収して適切な情報を入手するなど、取引の前提となった事実の認識について不注意な誤りがなく、
② 取締役会を何度も開催し、しっかりと議論をするという意思決定のプロセスを経ていた、
としても、「株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分した」時点で、「会社財産を危うくする罪」に該当してしまうリスクがあるわけです。
なお、この「投機的取引」には、新興国が発行する低評価の国債の購入や、かつてのドバイなどの外国の不動産バブルに乗っかった投資、また、出どころの怪しげな石油発掘ファンドへの投資なども対象とされると言われています。
会社の主要事業がうまくいかない時、よからぬコンサルタントや有象無象のブローカーが、キレイなパンフレットやパワーポイントとともに「バラ色の一発逆転ホームラン的な投機話」を持って来たりします。
このような話には、必ずといっていいほど“落とし穴”がありますし、単に「騙された」だけでは済まず、刑事事件になってしまうこともあります。
世の中の経営者の皆さま、目の前に勧められた「投機話」に対し、今一度、“マユツバ”で臨むとともに、この拙筆を思い出して頂ければと思います。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
弁護士法人ALG&Associates 弁護士・税理士
専門は企業法務ですが、国境を越えた家族問題やマンション管理問題など、幅広い分野に取り組んでおります。 時事ネタをくだいてくだいて解説するのが大好きです。 現在、宮内庁における外部通報業務に奉職中。
 フォローして山岸 純の新着記事を受け取る
フォローして山岸 純の新着記事を受け取る