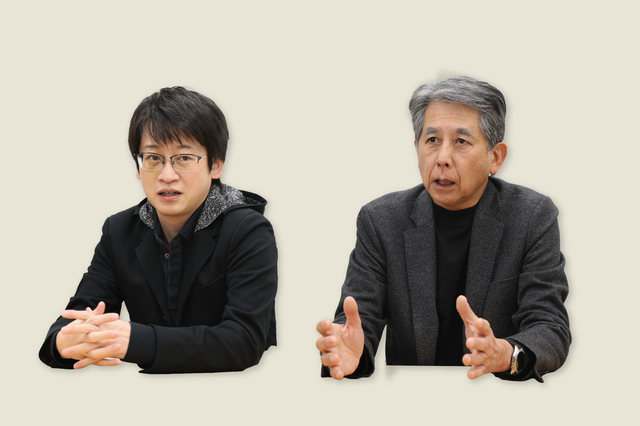世界をまたにかけて活躍するビジネスパーソン、いわゆるグローバルエリートは、「解は外にあり、課題はいつも中にある」と考えています。 この姿勢を全うし、培う力となるのが、「課題発見力」です。彼らはなぜ正しい課題を見抜けるのか。その力はどこで培われているのかを探っていきます。
世界をまたにかけて活躍するビジネスパーソン、いわゆるグローバルエリートは、「解は外にあり、課題はいつも中にある」と考えています。
この姿勢を全うし、培う力となるのが、「課題発見力」です。彼らはなぜ正しい課題を見抜けるのか。その力はどこで培われているのかを探っていきます。
もっとも大事なのは「本質的課題を発見する力」
私がワシントン大学に短期でMBA留学したとき、当時の教授、パトリック・ベティン氏から問題解決について教わったことがありました。ベティン教授に、「問題の解決は誰でもできる。すでにその問題を解いたことがある人に聞けばいいのだから。もっとも大事なのは、自分が最初に取りかかるべき課題は何なのか、課題を発見することだ。解く問題を間違えてしまったら、永遠に解決にはたどり着けない。君たちは、解く問題が正しいかどうかという一点に心血を注いでいない」と言われました。
そのとき、私はこれまで、「それが本当に解くべき課題なのか」と、深く考えてこなかったことに気づきました。エグゼクティブMBAの授業で、受講生は事業会社の社長や経営幹部ばかりでしたが、皆深くうなずいていました。
5000年の歴史を持ち、幾度となく迫害を受けてきたユダヤ人が、世界の人口の0.2%しか存在していないにもかかわらず、ノーベル賞受賞者の4割を占め、世界の富豪の約35%を占めていますが、この経済的・社会的地位を築くに至った背景にも、この「本質的課題を発見する力」があるからだと言われています。タルムード(ユダヤ教の口伝律法と学者たちの議論を書きとどめた議論集)には、本質的課題を見極めることの重要性が繰り返し説かれています。
例えば、ユダヤ系のベンチャーキャピタルと日本のベンチャーキャピタルを比較すると、成功する率自体は、10社に投資して成功するのは3社程度と、実はそれほど変わりません。しかし、「失敗から徹底的に学ぶ」姿勢に大きな違いがあります。日本の場合、成功した3割だけに注力します。成功したのだから当然とも言えます。一方、ユダヤ系ベンチャーキャピタルの場合、失敗した起業家に対して、何が本質的な失敗要因だったのかを深掘りし、課題発見の訓練と知見の共有を行います。つまり、多額の投資のうえ失敗しても、その失敗から学ぶことで、自分たちも投資先である企業も、次の挑戦における精度を高めていくわけです。これこそが、チャレンジする企業を育て、世界に通用する企業が増える理由なのです。
次のページグローバルエリートの強さは「リスクコントロール力」にある
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
ハートアンドブレイン株式会社 代表取締役社長
1968年、千葉県生まれ。東海大学法学部卒業。 英国国立ウェールズ大学経営大学院(日本校)MBA。 新日本証券(現みずほ証券)入社後、日本未公開企業研究所主席研究員、米国プライベート・エクイティ・ファンドのジェネラルパートナーであるウエストスフィア・パシフィック社東京事務所ジェネラルマネジャーを経て、現職。
 フォローして村上 和德の新着記事を受け取る
フォローして村上 和德の新着記事を受け取る