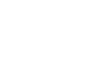DXという言葉は浸透した。しかし、日本企業の多くで「DXは進んだはずなのに、何かが変わっていない」という違和感が残っている。本連載は、その正体を「残念なDX」と定義し、なぜ成果や誇りにつながらないDXが量産されるのかを構造的に読み解く。 著者はDX検定構想者として、また人材育成・経営支援の現場に長年関わってきた立場から、DXをIT導入や業務改善にとどめず、「人」「顧客」「社会」までを変革する営みとして再定義する。 連載後半では、DXを1.0〜5.0の成熟モデルとして整理し、最終到達点を「DX5.0(Super DX+)」と位置づける。AI×人間力×価値創出を軸に、DXを“やらされる取り組み”から“未来をつくる経営”へ転換するための実践的な視座を提示する。
DXは進んだ。
それなのに、なぜ誰も誇らしそうではないのか
DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉は、すっかり日本企業に定着した。
DX推進室が設けられ、IT投資は増え、AIやデータ活用も珍しい話ではなくなった。
にもかかわらず、現場で聞こえてくる声は、なぜか明るくない。
「DXは進んでいる“はず”なのだが、何が変わったのか説明できない」
「システムは入ったが、仕事は楽になっていない」
「結局、現場は疲れたままだ」
こうした声は、特定の業界や企業規模に限られたものではない。
むしろ、日本企業のDXに共通する“空気”のようなものとして、あちこちで聞かれる。
DXは進んだ。
しかし、誰も誇らしそうではない。
この違和感こそが、いま日本のDXを考えるうえで、最初に向き合うべき問いではないだろうか。
DXは失敗しているのか?
まず確認しておきたいのは、多くのDXが「完全に失敗している」わけではない、という点だ。
プロジェクトは走っている。
システムは導入された。
スケジュールも守られ、予算も大きく外れていない。
それでも、胸を張って
「DXは成功した」
と言える企業は、決して多くない。
この状態を、私は 「残念なDX」 と呼んでいる。
失敗ではない。
止まっているわけでもない。
しかし、成果として語れず、誇りにもなっていないDX。
これが、いま日本企業に最も多いDXの姿である。
DXが「フワッとした取り組み」になる瞬間
残念なDXに共通しているのは、技術レベルの低さではない。
むしろ、最新のツールやシステムを積極的に導入しているケースも多い。
問題は別のところにある。
・なぜDXに取り組むのか
・何を変えたいのか
・どこに到達すれば「成功」なのか
これらが十分に言語化・共有されないまま、
「DXは必要だから」
「他社もやっているから」
という理由で走り出してしまう。
結果として起きるのが、
フワッとした取り組みから、フワッとしたものが出来上がる
という状態だ。
現場には「やらされ感」が残り、
経営側は「現場のマインドが低い」と嘆く。
しかし冷静に考えれば、
何を目指しているのかが共有されていないのだから、動けなくて当然なのである。
DXとは、本来何だったのか
DXの原点を振り返ると、その定義は意外なほどシンプルだ。
2004年、スウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授は、DXを
「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」
と表現した。
ここで語られているのは、
IT導入でも、業務効率化でもない。
人の生活がどう変わるのか
社会がどう良くなるのか
その結果として、ITが使われる、という考え方である。
しかし日本では、DXという言葉が
「IT化」
「デジタル導入」
とほぼ同義で使われるようになってしまった。
分かりやすいからだ。
測定しやすいからだ。
予算化しやすいからだ。
その一方で、
トランスフォーメーション(変革)という本質は、静かに置き去りにされてきた。
関連記事
2010.03.20
2008.09.26
人材育成コンサルタント、シニアインストラクター
● 人材育成、DX・IT、コンサル、マーケの経験を踏まえて、人材教育の新たなアプローチを探求中 明大法なのに齋藤孝ゼミ🤣 教免3種ホルダー イノベーション融合学会専務理事 教育研究家、モノカキの時は、「富士 翔大郎」と言います。天才トム・ショルツの「BOSTON」と「マニュアル車」「海外ドラマ」をこよなく愛する静岡県民
 フォローして富士 翔大郎の新着記事を受け取る
フォローして富士 翔大郎の新着記事を受け取る