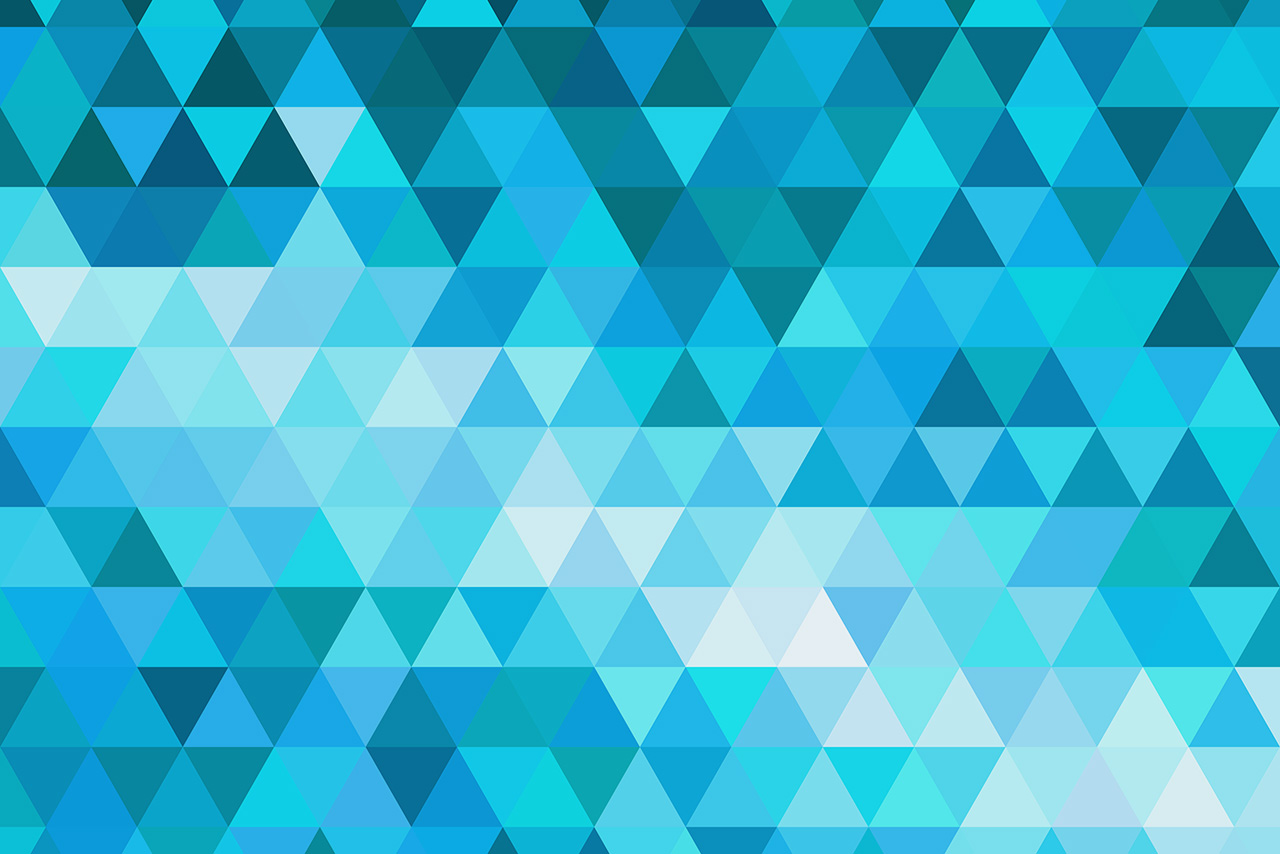かつて、社会で求められる人間像は明確だった。 言われたことを、正確に、素早く、失敗なくこなす人。 知識を多く持ち、スキルに優れ、論理的に物事を処理できる人。 いわば“役に立つ人”こそが、価値ある存在とされてきた。 けれど、今、その前提が根底から覆されようとしている。 ――AIの登場である。 AIはもはや、単なる計算ツールではない。 膨大な知識を持ち、複雑な問題を論理的に解き、精度高く翻訳や文章生成を行う。 「知っていること」や「できること」では、人間はすでにAIに勝てない領域が出てきた。 この変化は、人類にある問いを突きつけている。 “では、人間にしかできないこととは何か?”
周りから慕われ、信頼され、「あの人のそばにいたい」と思われる人もいる。
この違いは何か?
それは、“Doing(何をするか)”ではなく、“Being(どう在るか)”の違いである。
Doingは、表面的な行動や成果。
Beingは、その行動の奥にある、存在の質や姿勢、あり方だ。
たとえば──
同じように部下を叱ったとしても、
「この人に叱られたら不思議とやる気が出る」という人と、
「ただ傷ついて終わる」人がいる。
それは、“言った内容”ではなく、“言った人の在り方”の差なのだ。
■ AIの登場で、Doingの価値が相対化された
今やAIは、文章を書き、計算し、議事録をとり、データを分析し、動画をつくる。
つまり、「何ができるか」という部分は、機械に置き換わる時代に入った。
人間より正確で、人間より速く、人間より疲れない。
この変化は、恐れるべきものではない。
むしろ、“人間にしかできない価値”が浮き彫りになるチャンスだ。
その答えが、「在り方」である。
AIは感情を持たない。
倫理観も、信念も、人格もない。
どれだけ優秀でも、「この人を信じたい」とは思えない。
だからこそ、人間の価値は「Doing」ではなく「Being」に移る。
誰でもできることを“誰がやるか”が、重要になるのだ。
■ 若手こそ、Beingの種を育てる時
若い世代にとって、Doingは手に入りやすい。
動画でスキルを学び、SNSで実績を見せ、テンプレで成果を出す。
でも、だからこそ問われる。
「で、あなたはどんな人?」
「あなたにしかないものは?」
自分に問いかけてみてほしい。
履歴書や職務経歴書には書けない、
「自分の在り方」とは何か?
・誰と関わるときに自分らしさが出るか?
・どんな場で、どんなふうに生きたいのか?
・自分の存在が誰かにどう作用するのか?
それを見つける旅が、「本物の人間力」を育ててくれる。
そしてその旅は、今この瞬間から始められる。
■ リーダーは、「在り方」で空気を変える存在へ
「リーダーは決断力がすべて」
「上に立つ人は、強くなければならない」
そんな常識は、もう古い。
これからのリーダーに求められるのは、“空気をつくれる存在”であることだ。
・話しやすい空気
・失敗しても大丈夫な空気
・挑戦を歓迎する空気
そうした“見えない土壌”をつくるのは、言葉ではなく、リーダー自身の在り方だ。
誰よりも誠実に働き、誰よりも人の話を聴き、誰よりも自分に問いを持ち続ける。
そんな背中に、人は信頼と希望を託すのだ。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
CHANGE
2008.11.08
2008.11.06
2025.09.29
2025.10.22
2025.11.05
2026.02.17
2026.02.08
2026.02.28
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る