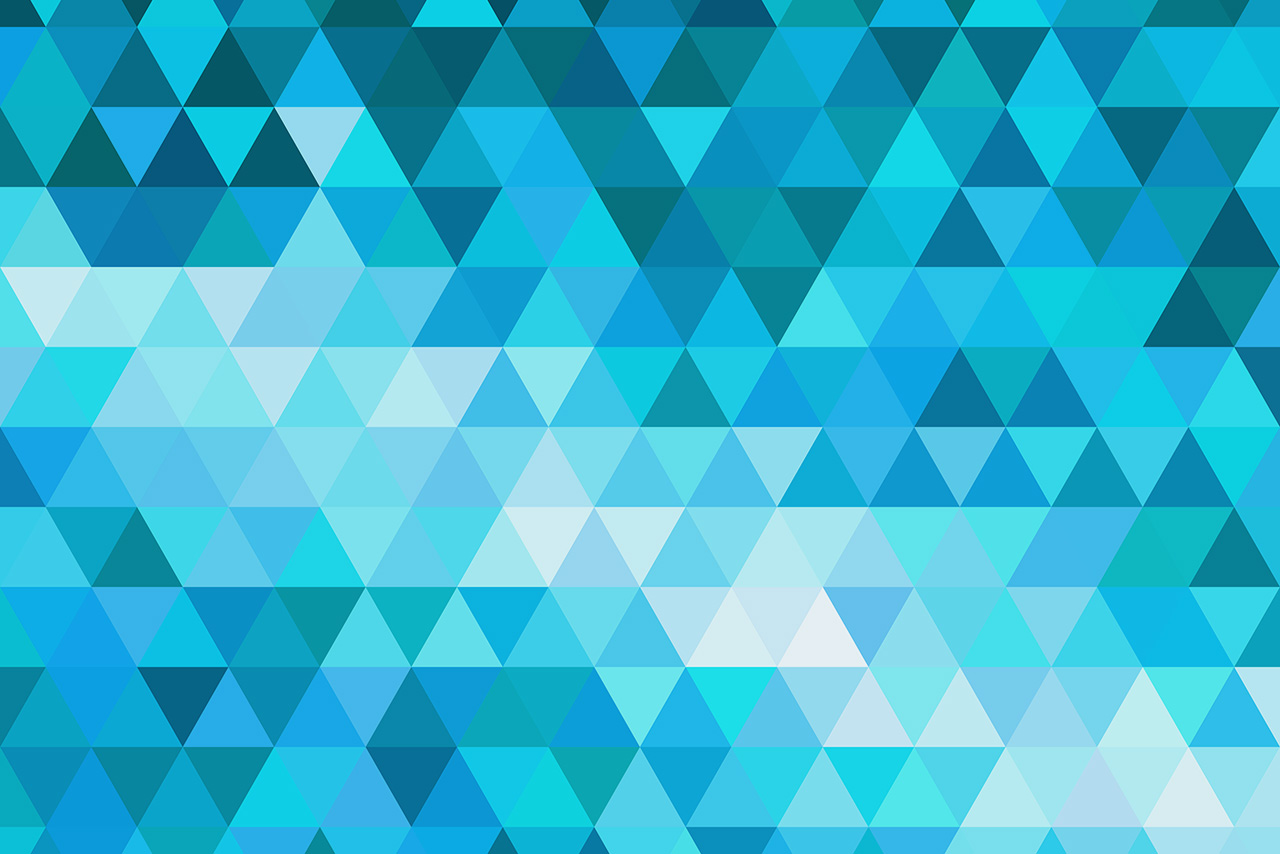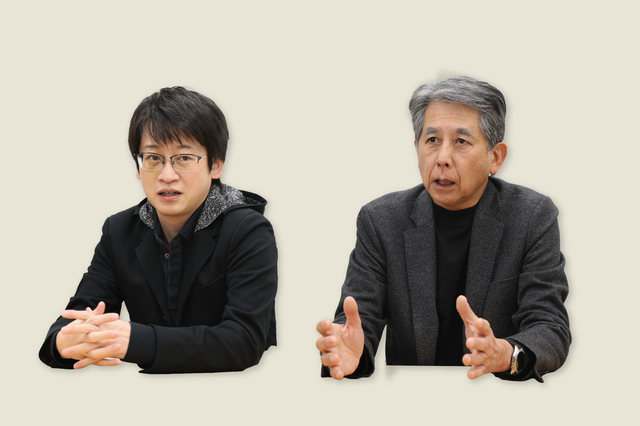“信頼されないリーダー”がもたらす組織の静かな崩壊 あなたの職場に、こんな上司はいないだろうか―― 「人一倍仕事ができる。判断も早い。しかし、部下の信頼はない」。 指示は的確で、成果にもシビア。 だが、どこか空気が重く、チームの会話は少ない。 そして、静かな退職(Quiet Quitting)という現象が生まれる。
未来を創るリーダーは、「人格」から始まる
――人間的合理性がチームを変える
“信頼されないリーダー”がもたらす組織の静かな崩壊
あなたの職場に、こんな上司はいないだろうか――
「人一倍仕事ができる。判断も早い。しかし、部下の信頼はない」。
指示は的確で、成果にもシビア。
だが、どこか空気が重く、チームの会話は少ない。
誰も反論せず、言われたことだけをやる。自発性は失われ、沈黙が支配する。
こうした“成果至上主義”のマネジメントは、いまや限界を迎えている。
部下は黙って言うことを聞いているように見えて、
心はすでに会社から離れている。
それが、静かな退職(Quiet Quitting)という現象だ。
Gallup社の調査(2022年)によると、日本の「熱意ある社員」はわずか5%。
一方で、72%が“やる気のない社員(Not Engaged)”という結果が出ている。
この数字は、アメリカ(Not Engaged:50%前後)や世界平均(59%)と比較しても極端に高い。
つまり、「言われたことはやるが、それ以上はしない」社員が圧倒的に多いということだ。
これは単なる個人のモチベーションの問題ではない。
背景には、リーダーの“在り方”が深く関係している。
なぜ今、人格が問われるのか? ― 結果ではなく、信頼の時代へ
これまでの日本企業は、「仕事ができる=リーダー適格者」と見なされてきた。
管理職への昇進も、成果とスキルを中心に評価されてきた。
しかし今、求められているのは、「人格を備えたリーダー」である。
組織が直面する課題は複雑さを増し、
過去の成功体験や「正解」をなぞるだけでは乗り越えられなくなった。
そして何より、働く人々が「信頼できる人のもとで働きたい」と、
はっきり意思を持って動き始めているのだ。
ここで言う「人格」とは、スピリチュアルな意味でも、倫理道徳の話でもない。
人間的合理性(Human Rationality)、
つまり、「人として納得できる言動」「誠実であること」「傲慢にならないこと」など、
他者との関係性において信頼を育む力を指す。
言い換えれば、「結果」より「関係性」を重んじる力であり、
「支配」より「共感」をベースとしたリーダーシップである。
誠実さが信頼の土壌になる
では、人格のあるリーダーは、どんな特徴を持っているのだろうか。
この問いに対し、近年注目されているのが、
「徳を宿すリーダー(Virtuous Leadership)」という概念だ。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る