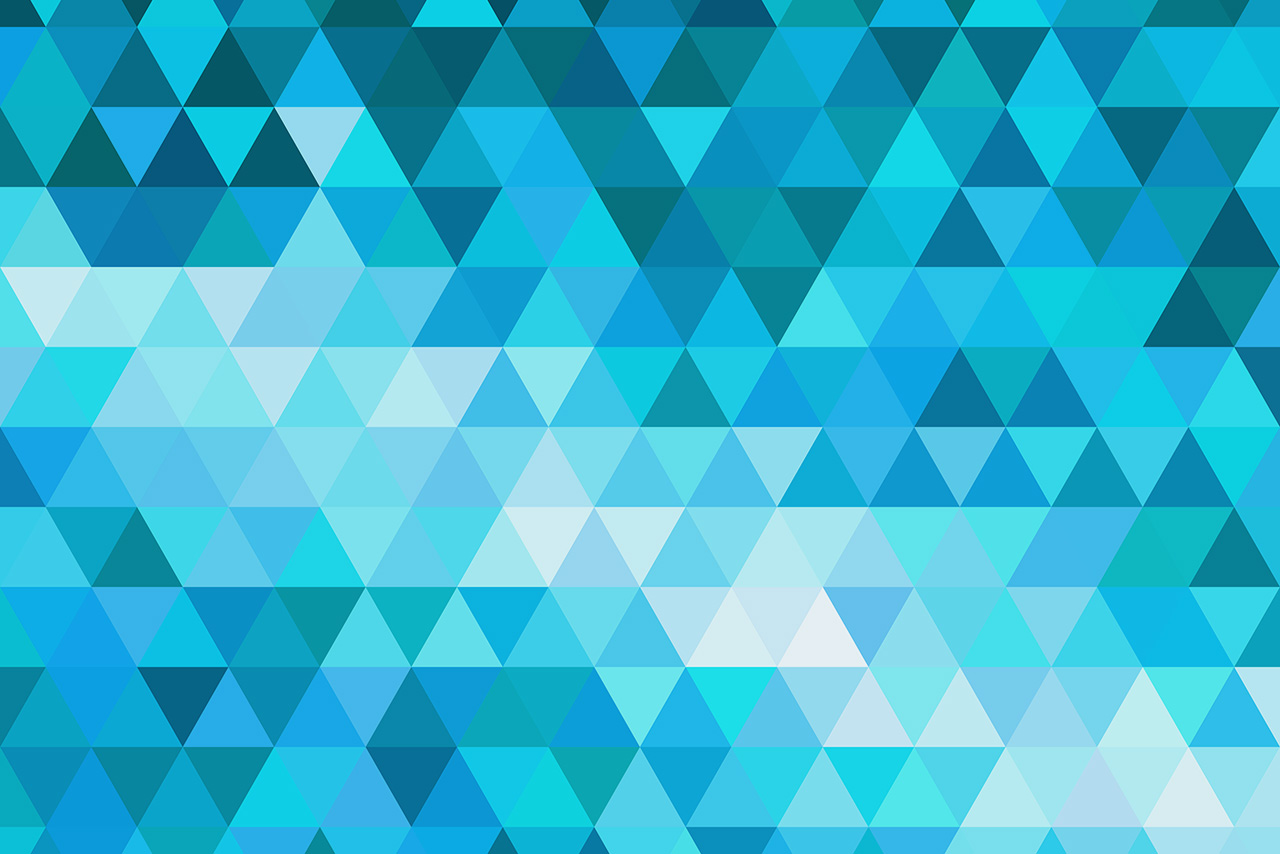今回は、社内にある人事制度が「一社一制度」であることが果たして、その会社にあった人事制度なのか?「運用しやすい人事制度」ではなく、「戦略に沿った人事制度」を作ることについてお話します。
問題になったのは、人事制度です。
事業内容や、それを推し進めるスピード感が違うのは当然のこととして、求める人物像も、必要な能力も大きく違うことが分かって来ましたが、ご他聞に漏れず「人事制度を社内に何通りも作るわけにはいかない」と、統一した人事制度の運用を続けていました。
限界を感じた現場からの要望もあって、検討の結果、モバイルコンテンツのグループだけは、ゼロから構築をし直して、オリジナルの評価基準、オリジナルの評価シートを開発し、給与への反映の仕方に至るまで新しい考え方のものを作り上げることになりました。
その構築の元になったものは、モバイルコンテンツ事業の後発組としての事業戦略です。元々あった専門分野で培ったコンテンツの特異性と魅力を前面に押し出し、スピード感を持って展開していくことになり、それにふさわしい人材を集中することになりました。
ここでは詳しく書けませんが、それに合わせて役職・等級の基準、評価制度の評価基準、評価シートをそれぞれ開発したわけです。
その後数年経ちますが、懸念に反して大きな問題もなく運用が進んでいます。
他部署からの異動者については、関連会社への出向のような形で、事業内容、本人の仕事内容、そしてモバイルコンテンツ事業部で運用されている新しい人事制度が丁寧に説明されるようになっています。
このように、今後は大きく性質の変わる事業部門について、一企業二制度、ないし三制度などが必要になってきていると思います。
【上司が理解できないことは評価されない】
もうひとつ問題があるのは、評価制度の評価項目が、過去の成功事例に基づいた経験則によって構築されている、ということです。多くの人事制度に関する専門書が日常のオペレーションを上手にやることが眼目で作られている例が多く、評価項目もそれに沿っている可能性が高いのです。
言い方を変えれば、上司が理解できることしか評価されない危険性がある仕組みとも言えるのです。競争がますます激しくなる経営環境の中では、オペレーション重視ではなく、イノベーションを起こすこと、未だ誰も目にしたことのないものを生み出していくことが望まれ、そうした動きが評価されなくてはならないのが急務ということも多いのではないでしょうか。
事業に求められることがそのような逼迫したものであるのに反して、人事部が所管する人事制度だけは、まったく別物の扱いで旧態然としたまま、実態にそぐわないことがわかっていても「運用のための運用」という状態になっている企業も少なくないように見受けられます。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
人事制度について
2011.01.18
2011.01.07
2010.12.22
2010.12.15
2010.12.08

今野 誠一
株式会社マングローブ 代表取締役社長
組織変革及びその担い手となる管理職の人材開発を強みとする「組織人事コンサルティング会社」を経営。 設立以来15年、組織変革コンサルタント、ファシリテーターとしてこれまでに約600社の組織変革に携わっている。
 フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る
フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る