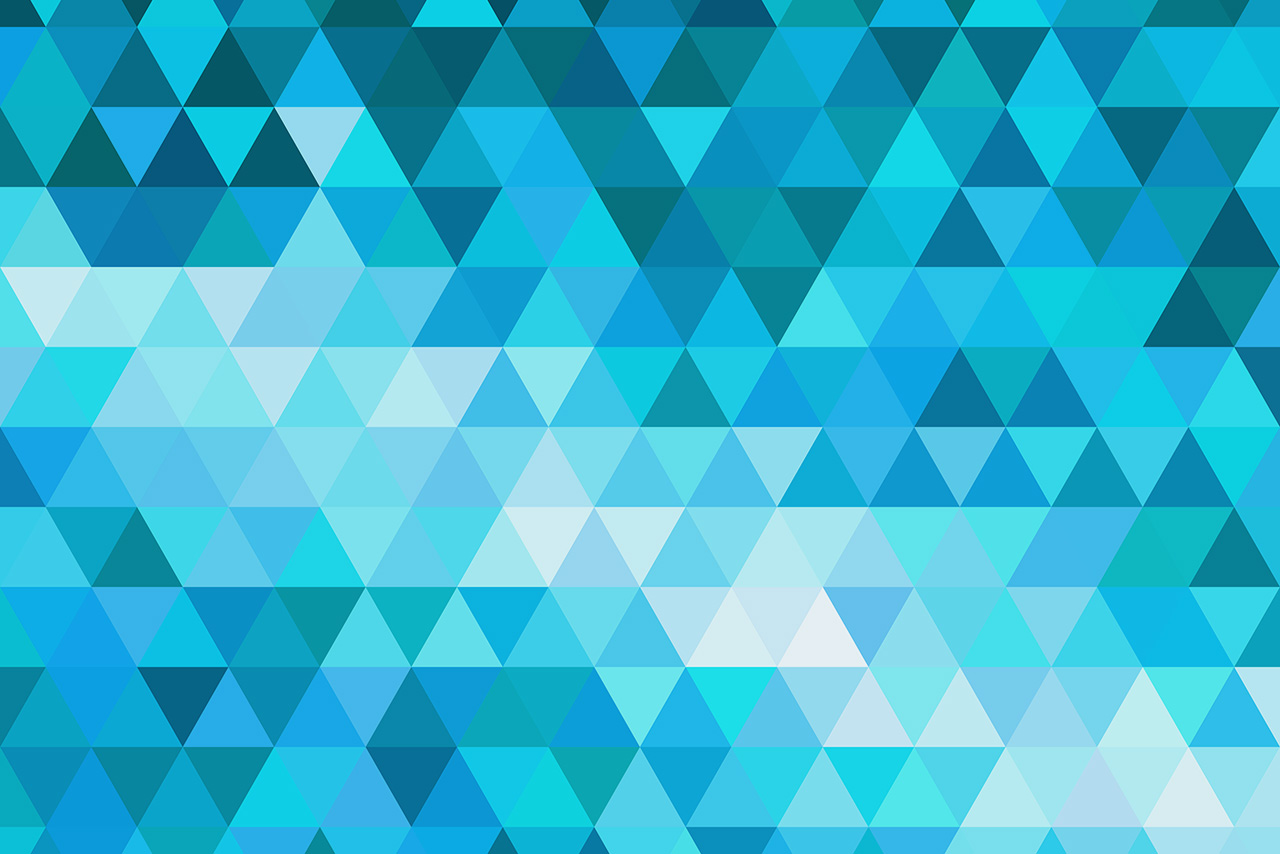今回は、評価制度を構築する際に客観性と主観性をしっかりと使い分ける必要があるということ。そして、その主観性を下に評価する部分については、「誰が評価するのか」が最も重要なポイントになることについてお話します。
【評価を客観的にすることは可能か】
いきなり、結論的に言ってしまいますが、『評価制度』というものは、客観的指標にこだわり数値化したり、指標をシンプル化しようとすればするほど、うまくいきません。うまくいかないという意味は「評価が実態とかけ離れていく」ということです。会社が、そして人事部が客観的指標、とりわけ数値化にこだわるのは、いわゆる「誰が評価しても公平公正に評価できるようにしたい」という大義名分によるものですが、それにこだわればこだわるほど、逆の方向にいくこともあるという事実は、実に皮肉なものです。
誤解を怖れずに言いますと、人が人を評価する限りにおいて、最終的には主観的でしかも定性的評価にならざるを得ない、絶対的に正しい評価など最初から存在しないのだと覚悟する必要があると思います。
人と人との関係において、どうでしょうか?
上司から「人事制度上の仕組みでお前は○点だ。その根拠は・・」とやられるのと、尊敬する上司の場合という注釈つきにはなりますが、「俺は思うんだが、お前のこういう点は実にいいね。強みだと思うからどんどん伸ばしていきたいね。しかし、これこれこういう点は改善の余地があるぜ。このままじゃ駄目だよ」と主観的に言われるのとでは、どちらが納得できるでしょうか。
『評価制度』には、もうひとつ弊害になってしまうことがあると思っています。それは、客観的評価を目指して、精緻に作りこめば作りこむほど、評価者が無責任になっていくという現象です。
その理由は
・ 精緻で分かりにくいので、一人ひとりをきちんと見ることよりも、精緻な評価シートを埋めることが仕事になってしまっている。
・ 精緻な評価項目に沿って、評価を記入していると、それだけできちんと評価できている気になってしまい、自分なりの見方を封じ込めてしまう。
・ 不満が出ても、精緻な評価制度という拠り所があり、そこが逃げ場になってしまう。
【誰が評価者になるべきなのか】
多くの企業が、「役職=肩書き」で誰が評価者になるべきかの線引きを行なっていると思います。「課長代理以上」または、「課長以上」などという具合にです。
しかし、人が人を評価するということの重大性に鑑みると、これはよく考えたほうがよいことかもしれません。
人をきちんと観るという能力は、実務上で成果を上げ会社に利益をもたらす能力と必ずしも一致していない場合が多いのではないか、ということです。
従って、本来は組織に余裕があればということにはなるでしょうが、評価者としてもやっていける見通しを持って昇進を考えて、メンバーを預けるということをすべきなのだと思います。あるいは、人材開発委員会のようにして、評価専門の人がいてもいいのかもしれません。しかしそうすると日常の業務の様子が分からない状態で評価することになるので悩ましいことではあります。
次のページ【客観的評価と主観的評価との兼ね合い】
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
人事制度について
2011.01.18
2011.01.07
2010.12.22
2010.12.15
2010.12.08

今野 誠一
株式会社マングローブ 代表取締役社長
組織変革及びその担い手となる管理職の人材開発を強みとする「組織人事コンサルティング会社」を経営。 設立以来15年、組織変革コンサルタント、ファシリテーターとしてこれまでに約600社の組織変革に携わっている。
 フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る
フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る