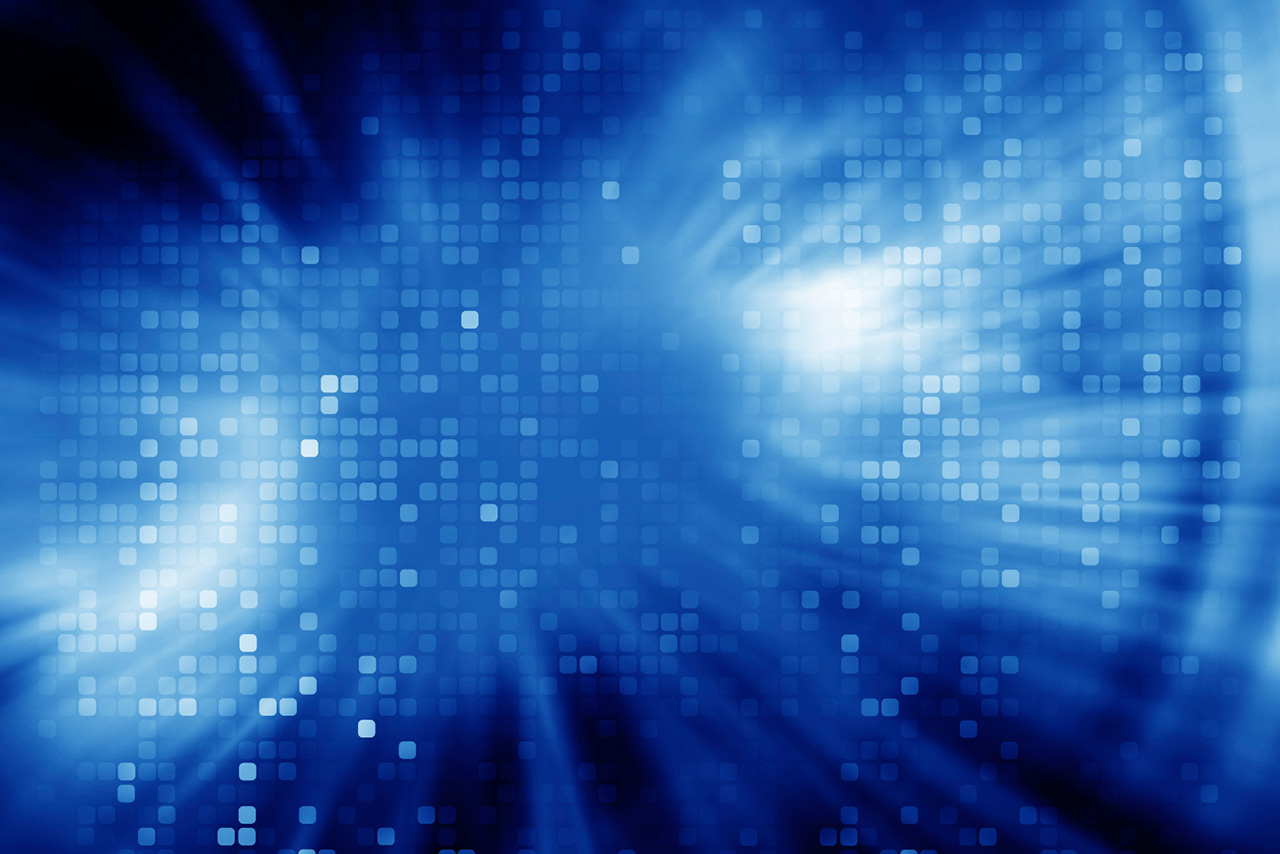「中国企業と連携することで中国市場に進出しよう」というのが、私のコンセプトだが、高齢化した日本企業が若い中国企業とコミュニケーションが取れるのか?と考えると、かなり難しいのかもしれない。
7.「高齢で保守的な経営者」と「若くて柔軟な経営者」
市場戦略とは、それぞれの市場に対応するのが原則である。客観的に考えれば、「現実の市場を見ようとせず、自分の経験を押し通して成功する」と考える人はいないだろう。しかし、現実には、中国の市場を調査することなく、日本の方が中国より優れていると勝手に思い込み、自らの手法に固執している例が非常に多い。
人間を年齢だけで判断してはならないと思うが、高齢者が自身の経験に固執する傾向は否定できないだろう。たとえば30年前に私が就職したデザイナーズブランドアパレルは、当時の平均年齢が25歳だった。今回訪問した中国アパレルの「ホワイトカラー」の社員の平均年齢は26歳。私は、ホワイトカラーの本社を訪問し、当時のDCアパレルが持っていた自信と意欲に溢れた雰囲気を感じた。
国の違いや業種の違いに関わらず、社員の平均年齢が20歳代、30歳代の企業は活気がある。日本でも若いIT企業のオフィスは活気にあふれている。一方、社員の平均年齢が40歳代半ばを過ぎた企業は、どんな職種であろうと、保守的な空気に支配されている。
中国市場は若い。中国企業も経営者も若い。経験不足の危なっかしい点は否めないが、全ては積極的、前向きだ。日本も経験した高度経済成長時代のノリが必要なのだ。中国の第一線でビジネスを実践している若い人達は、日本のような高齢者の助けを望むだろうか。というよりも、高齢者が若者とコミュニケーションを取ることができるだろうか。「中国企業との連携による中国市場進出」という私のコンセプトは、正直なところ揺らぎ始めている。
中国と付き合うには、若いエネルギーが必要だ。その意味では、中国ビジネスは若い世代に託した方が良い。大手企業よりもベンチャー企業が向いているだろう。若い世代に思い切った権限委譲をできる企業でなければ、中国人に権限委譲することもできないはずだ。
また、若者とコミュニケーションを取れない人間は中国ビジネスに適していないと思う。中国の駐在員の若返りを図るべし。逆に言うと、高齢化している企業は中国と関わることで世代交代を進めるべきではないだろうか。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26