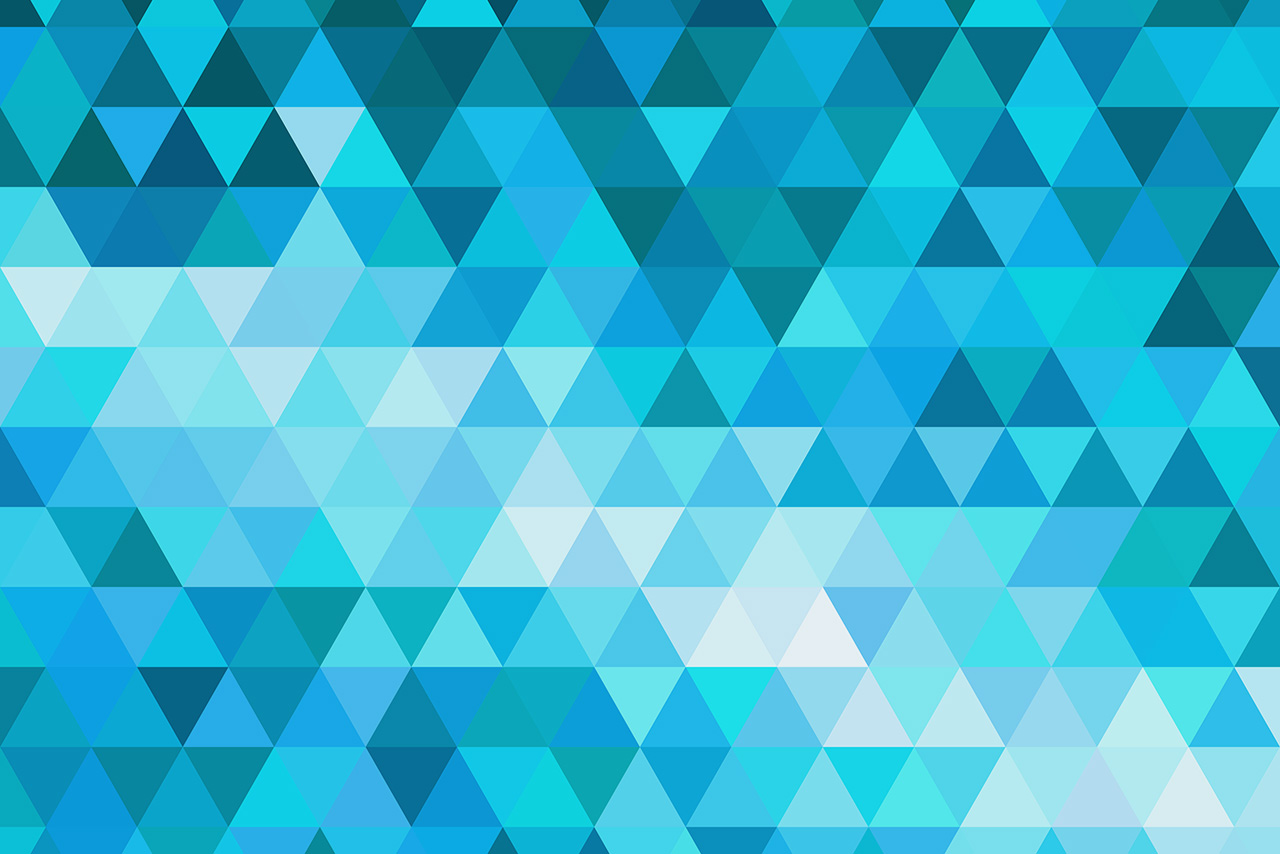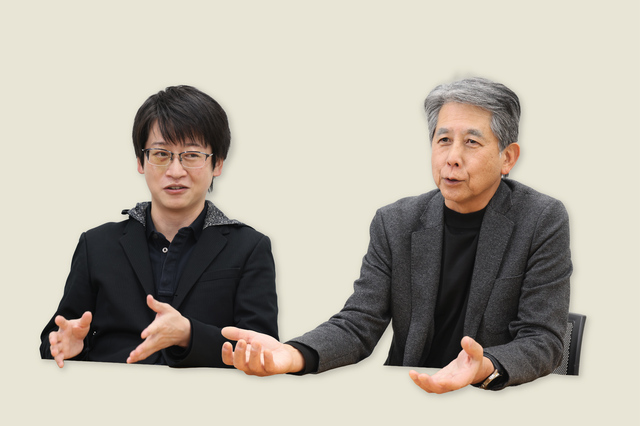内部統制対応の1年目。2009年中に管理部門がやらなければならないものは、統制体制を現場に落とし込むルールの見直し。そして、会社法で定める「法令順守」への対応と「行動指針」の見直しです。
結果として「行動指針」や「行動マニュアル」が重要になるのではないかということに行き着くのです。実際、そんな思いでマニュアルを作成したりもするのですが。
2.会社の形、ルール、約束は社員に伝わっていますか?
東証に上場の際必要な「適格要件」に以下の記述があります。
(5)経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること
(コーポレートガバナンスの項)
あまりにも幅が広いため、人事・総務の観点だけから考えますと、以下の確認・対応プロセスになります。
①会社が法令違反をしていない
②会社が法令違反をしていないことを証明できる
③社員が法令違反をしていない
④社員が法令違反をしないようにルールを定めている
⑤社員が法令違反をしないような体制・対策を講じている
⑥社員が法令違反をした場合の明確なルールを定めている
全ての作業を書いても仕方ありませんが、例えば①では、
就業規則の内容は2009年の法令に対応していて、きちんと届け出ている。もちろん36協定や、付属規程も含めて。
時間外勤務はきちんと管理・計算され法定の上乗せの下、支払われている。
就業規則には解雇要件、休業要件が正しく記載され、運用されている。
就業規則内での表記・表現は、社内で運用されている他の規則・規程・帳票と繋がりがある。
などなど…
就業規則だけ見直すのであれば、社会保険労務士の方に依頼すれば十分にできると思いますが、内部統制対応に後付けで様々な社内ルールを見直す時には、上記2点を注意頂いて、正しく効率的に文書化して頂ければと思います。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
内部統制と管理部門
2009.06.23
2009.06.17