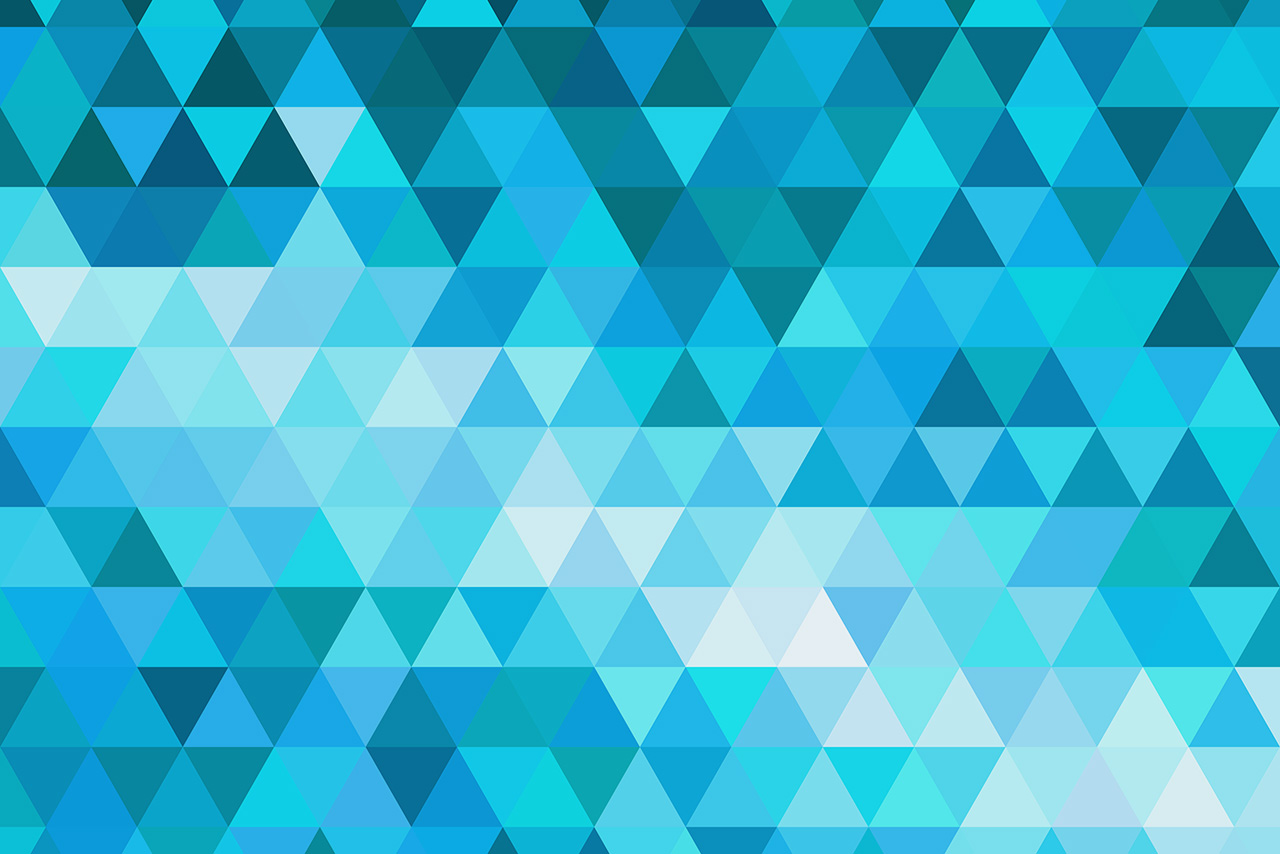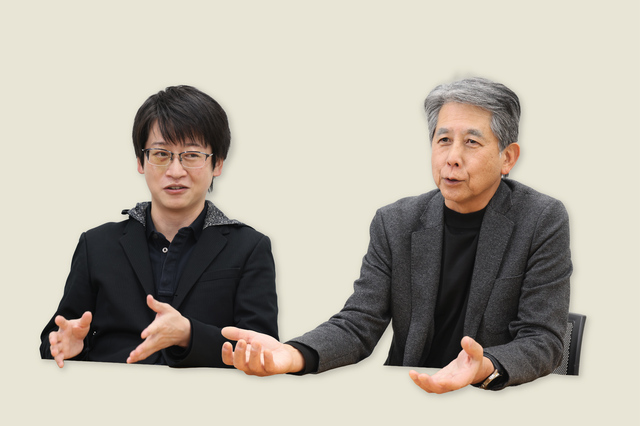フェーズ6になったことで、コンサルティング会社やIT企業が対策ツールの提供に積極的になっていますが、ベースのノウハウが間違っていると、ユーザーは多大な移行プロセスの障害とコスト負担、そして社内の混乱を背負うことになります。
「在宅勤務」とは、基本的に日本国内のほとんどのビジネスパーソンが経験したことのない働き方です。そして、その働き方が抱えるリスクを考えたこともありません。
例えて言えば、入社したての新入社員が社会人としてどのような勤務をするのか分からず、相談したり試行錯誤するような状況と同じだと考えられます。
『日本国内でパンデミックになったら「在宅勤務」に移行しよう』とは良く聞かれる話しではあるのですが、発生の瞬間に移行しようとしても、試験運用をしていなければきっと失敗するでしょう。その場合は、社内ナレッジを集約するシステムが業務報告ではなく働き方相談になってしまうと思われます。
さて、では「在宅勤務」に移行するためには何が必要なのか?ということになりますが。
1.業務分析
内部統制のルールに従い、本当に社外で行って良い業務は何か?
2.業務の見える化
社内で行うべき業務を可能な限りスリム化できないか?
社外で行うべき業務を可能な限り安全にできないか?
3.リスク想定
業務を社外(又はクライアント社外)で行うリスクは何か?
※契約書の内容、情報資産管理の視点、社員の健康管理などから考える
4.そもそも在宅勤務なのか?
社内に集まることで抱えるリスクは何か?
社内に新型インフルエンザウィルスを持ち込まない方法はないか?
社内で部署毎や個人毎に隔離できる方法はないか?
5.そもそも在宅勤務を実施できる業種・業界なのか?
現在の業務が、自宅でできるのか?
6.「明日から在宅勤務に移行します」に対応できるか?
働き方について周知徹底されているか?
労務管理体制が徹底されているか?
労務管理体制について管理職は十分に理解しているか?
情報資産管理の重要性について、社員間で共有されているか?
7.最後に、お客様は、御社の在宅勤務を歓迎しているか?
納期と健康管理のどちらを優先して欲しいと言われているか?
義務と努力義務の差をお客様と共有できているか?
自社の社員に対する労務管理のスタンスをお客様に説明できるか?
なんだかチェックリストのようになってしまいましたが、在宅勤務の移行は人事異動のようなものです。環境に慣れていないままに本格導入をしてしまうと混乱しか生まないでしょう。
やり方を間違うと、休校中の高校生でカラオケBOXが繁盛なんていうニュースの二の舞になってしまいますし「○○社在宅勤務移行によって、××市のカラオケBOX大盛況」なんていうスクープ記事が出てしまえば、本末転倒です。
もし、パンデミック対策に在宅勤務への移行を選択肢として考えている場合には、移行までのスケジュールに加えて、移行に対する社員の意識(在宅勤務移行の重要性とリスクに対する覚悟等)をご確認頂ければと思います。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
2009年 新型インフルエンザ BCP
2009.09.23
2009.07.08
2009.06.16
2009.06.08