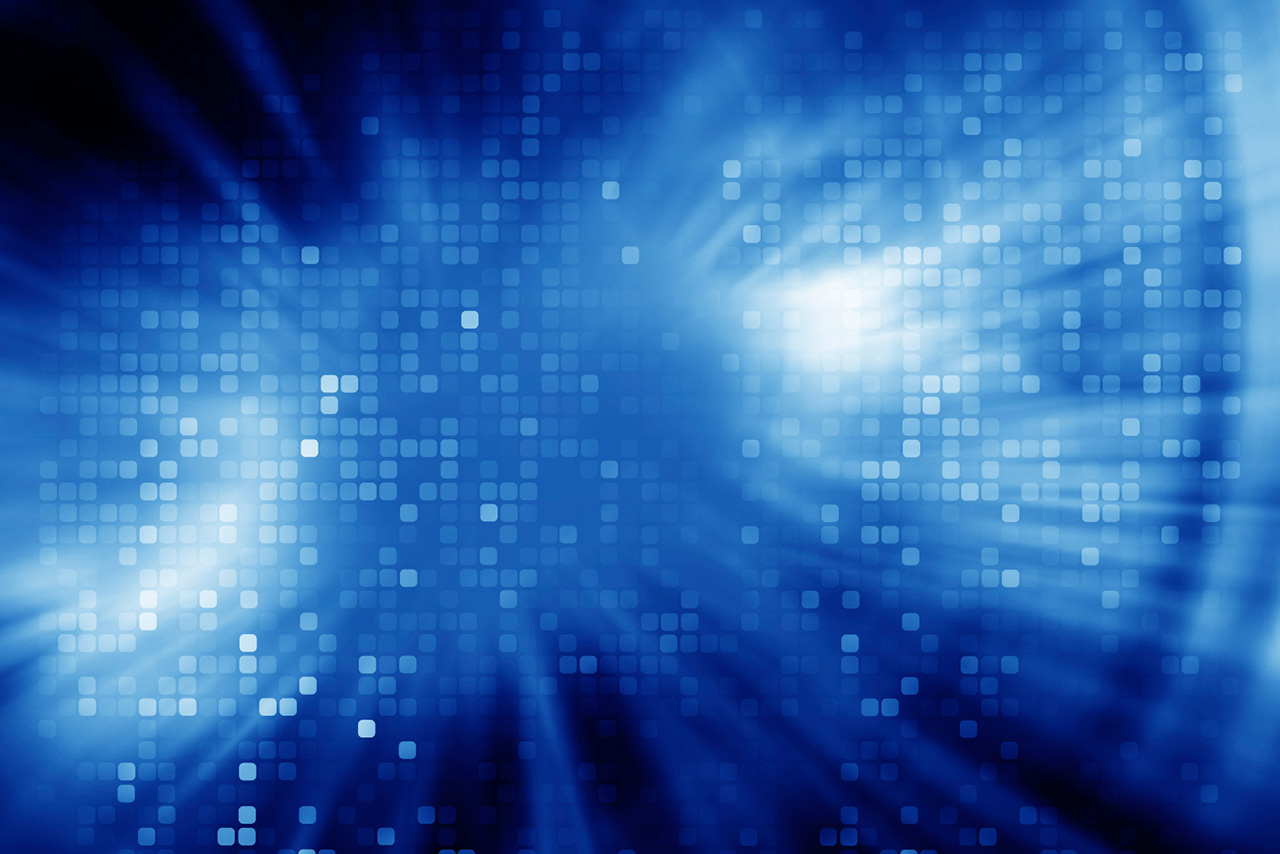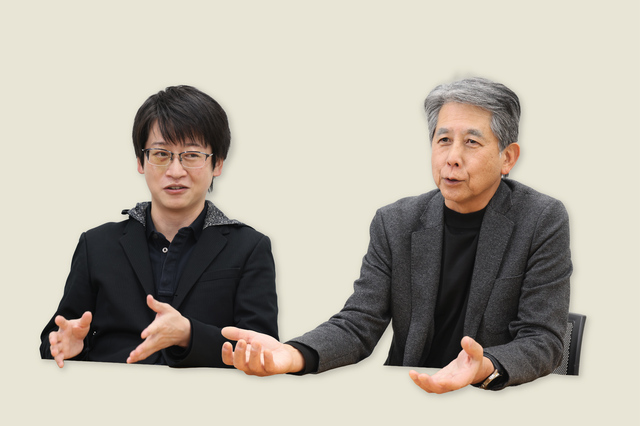ようやく様々なセミナーなどで法令順守や財務リスクの観点からのパンデミック対策が話されるようになってきましたので、IT企業の事業継続について少し気になることを書いておきます。
パンデミック対策のIT企業向け支援やパンデミックセミナーでお伺いしていることの中で、今後大きなインパクトを持つであろうフレーズがあります。
「新型インフルエンザって言っても、季節性とあんまり変わらないんですよね。」
既に7月に入り、この時期にインフルエンザが発生しているという段階で、明らかに季節性とは違うと思うのですが、判断基準が感染力と死亡者数に偏っているため、被害があっても季節性と変わらないだろうという判断に結びついているのだと思います。
そして、IT業界では、様々な仕事が年度計画とは別に、プロジェクト単位で動いています。クライアントか自社か、なんらかの判断基準によって作業期間を設定して、その期間内で、要求に足りる製品・ソリューションを納品することを定めて、契約を締結します。
さて、パンデミックの本当の恐さは、病気の強さ(死に至らしめる可能性)ではなく、集団感染による社会機能や事業運営への影響ですから、これらプロジェクト単位での業務に対しては、かなりのインパクトが考えられることになります。
ここで先に話しを戻すと「新型インフルエンザは季節性と変わらない」という認識が広がれば広がるほど、リスク管理が徹底されていない企業は、契約の不履行に対する訴訟リスクを負い、逆にパンデミック対策ができているところは、その訴訟リスクを回避できるので、財務的なインパクトを薄めて、雇用への悪影響を避けることが可能となります。
一般的に聞かれる「パンデミック対策は大手企業がすることで中小企業は無理。」ということは、大手企業は「ただのインフルエンザ」という認識のままとなりますから、契約に基づいていかなる状況にあっても履行を求めざるを得なくなります。
コンプライアンスの観点からすれば、契約の不履行は行うことも、されることも認められず、結果として「不履行=損害賠償」となる可能性が高くなるということになります。
企業担当者間では、パンデミックのせいだから仕方ないと同意できても、内部統制体制を構築している企業は、仕方ないで済ませるわけにはいかなくなっているということを知っておかなければなりません。
この認識のズレは、対策を講じていない側へのかなり大きなネガティブ・インパクトとなることは間違いありません。
特に、通信関連ではIDCやネットワーク監視、サービスでは金融系システム運用やコールセンターなどの運用、システム開発では人材派遣型開発プロジェクトなどが、このネガティブ・インパクトの対象となるでしょう。
次のページIT企業が対応すべきパンデミック対策のポイント
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
2009年 新型インフルエンザ BCP
2009.09.23
2009.07.08
2009.06.16
2009.06.08