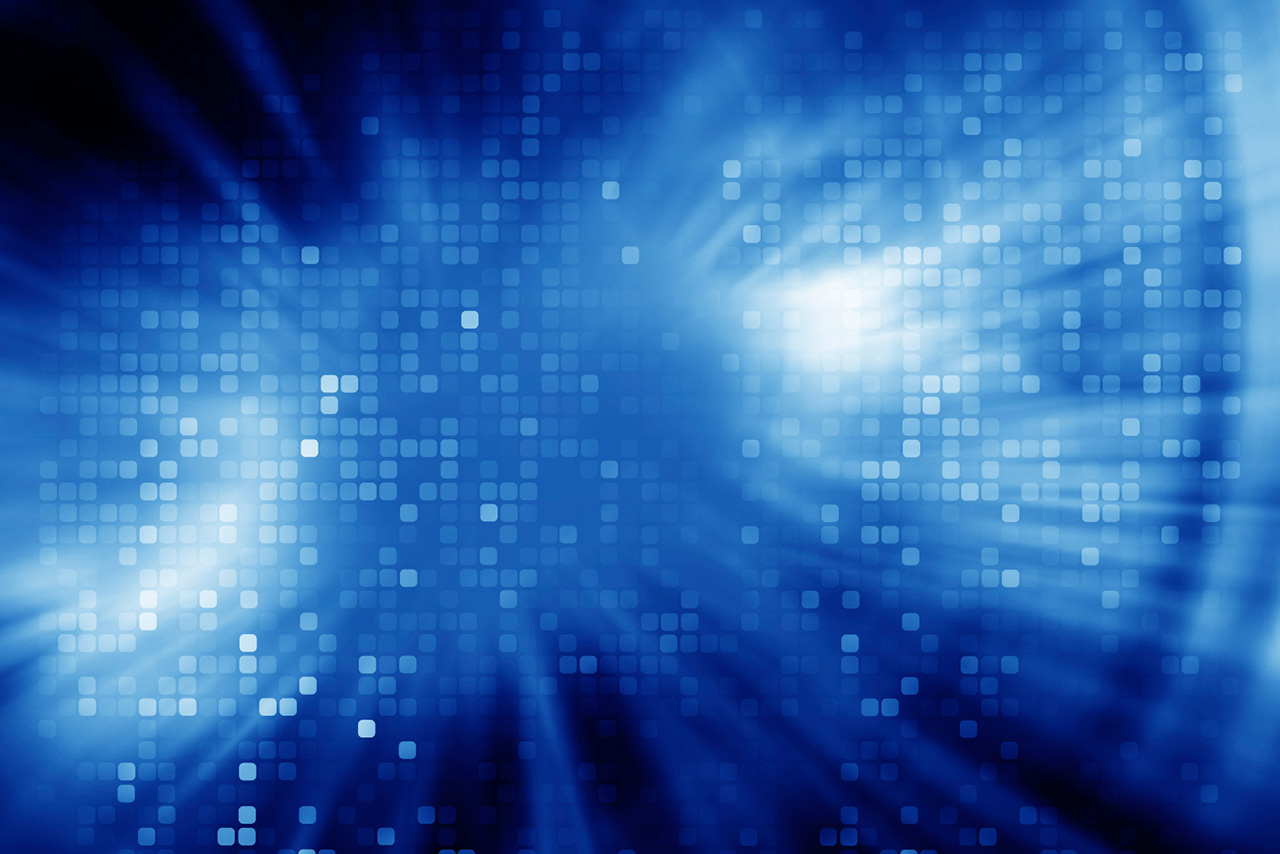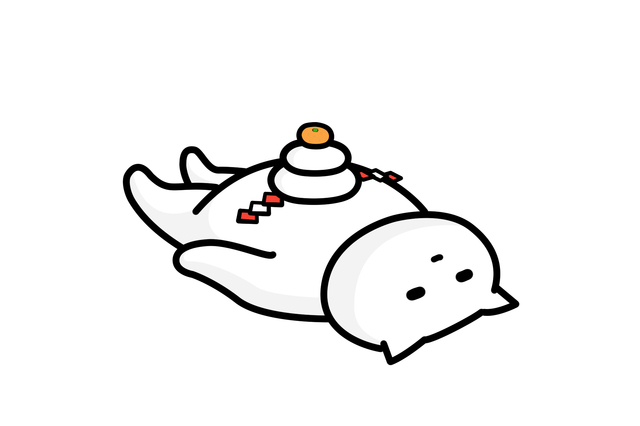現在、企業の経営戦略の賞味期限は、平均2.5年となっている。これが、何を意味するのかに言及してみたい。
企業の経営戦略が平均2.5年となっている。
これは、何を意味するのだろうか?
経営層側からは、「先が読みにくい。来年や再来年初め辺りまでは
読めるが、その先は、読めない」といった感覚ではないだろうか。
現場側からは、「戦略がころころ頻繁に変わる、体制や制度、システムが
できたと思ったら、即、変更となる」というイメージになる。
この経営側と現場側の感覚がコミュニケーションギャップを引き起こす
要因となる。
また、戦略の短期化は、ビジョンの短期化を伴うと言える。
ビジョンに沿って経営戦略が立てられるからである。
とすれば、企業にとって最も安定感のある拠り所は、経営理念となる。
安定した経営理念と、ダイナミックなビジョンと戦略が企業を形成する
ことになる。如何にこの点をデザインしていくかは企業の人材求心力を
左右するものとなる。
興味深いことに、経営戦略の賞味期限と新卒者のリテンションは比例し
ている。(リテンション=定着率の意)
現在、大卒で3年以内に転職する方の比率は30%を超えているのだ。
(最新の数字は、約34.5%)
ということは、企業を選ぶ人材側は、企業の理念に共感している方が70%
を切り、ビジョンや戦略で選ぶ方が30%を超えているとも考えられる。
良質の人材を集め、定着させる上で、経営戦略の描き方が非常に重要性を
増していることがわかる。
人材流動化時代は、経営戦略のデザインで競う時代だと言える。
但し、経営戦略のデザイン以上に必要なのは、経営戦略の評価であるが、
実際、日本企業は、立案系は強いが評価系が弱くなる傾向が強い。
(例えば内部監査人などの人材不足、育成問題を見ると自明の理である)
では、優れた経営戦略をデザインし、実行し、評価できるリーダーはどの
ようにして産出されるのだろうか?
次回は、先進性の時代における有能なリーダー産出について言及してみたい。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社インサイト・コンサルティング 常務取締役 COO(最高業務執行責任者)
個人と組織の成長を実現するために、真に効果的な人材育成のあり方を追求しています。国際競争力を併せ持つ能力開発を志ます。そのためには多様性を強みに昇華させることが肝要と心得ます。
 フォローして槇本 健吾の新着記事を受け取る
フォローして槇本 健吾の新着記事を受け取る