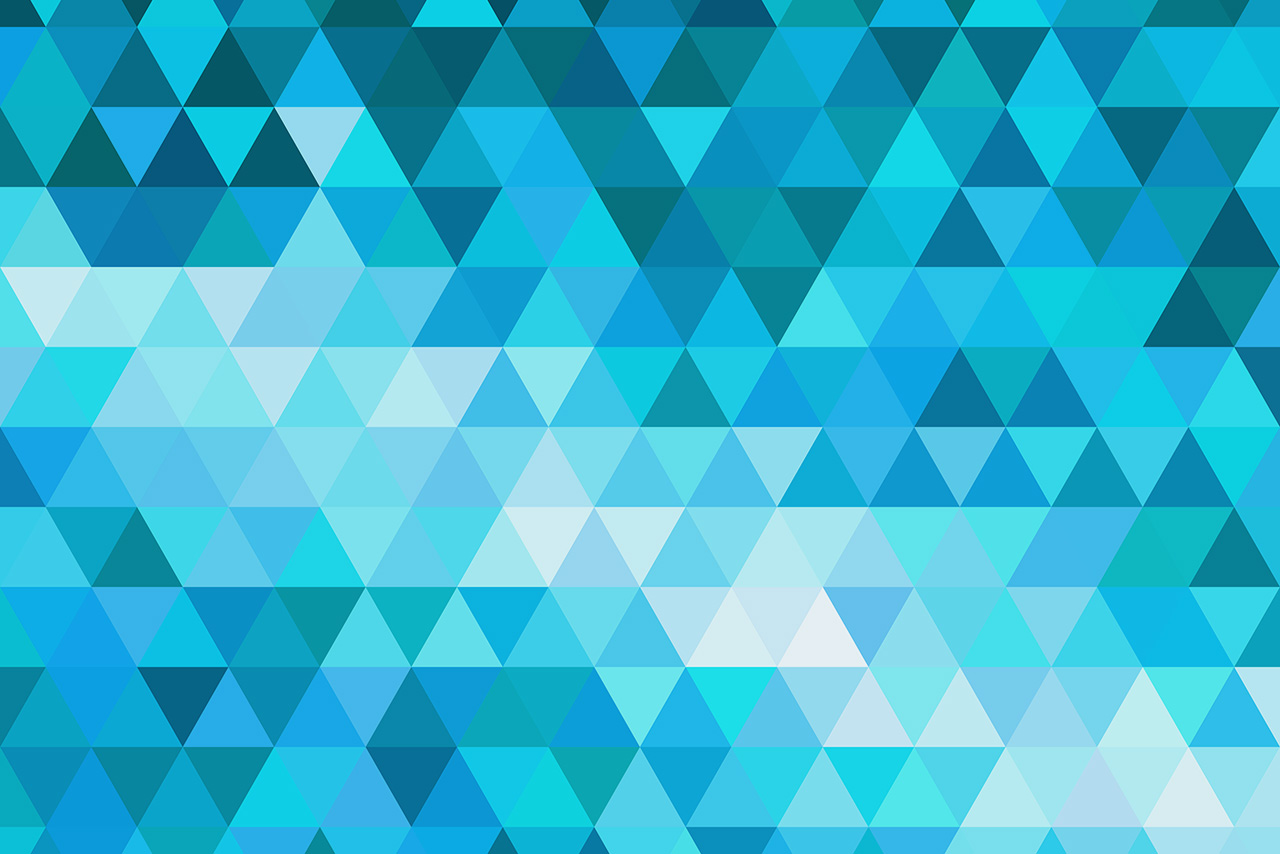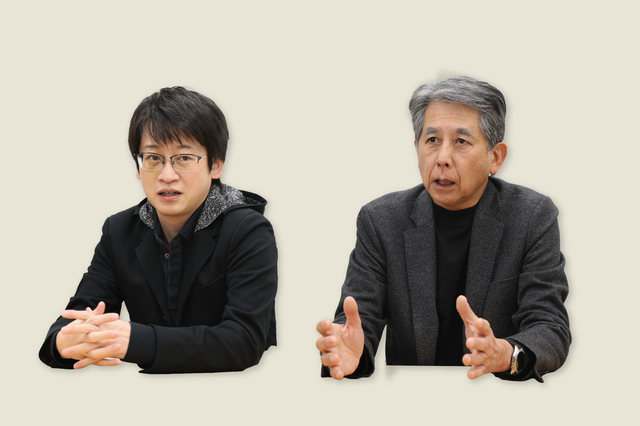「ファシリテーター」って聞いたことありますよね? ・会議を上手く仕切ったり、 ・人前で話して納得と共感を得たり、 ・周りを巻き込んで社内の改革を推し進めたり する人のイメージですが、その一番大事なスキルは何か想像つきますか? それは、頭の中に「階層構造」を持つことなんです。「PFD三層構造」と呼びますが、頭の中で具体と抽象を行ったり来たりする、ファシリテーターの「キモ」とは…
1位 堂々とした話し方や振る舞い
2位 興味深いテーマや内容
3位 適切な長さ
4位 アドリブのうまさ
5位 適切な声量
とのことなのですが、これ全部プレゼンテーション層で、「何を言うか」、「どう言うか」、「どのような態度を取るか」という目に見えるものばかり。
目に見えないところにフォーカスするのがファシリテーター
ところが、プロのファシリテーターというのは違うんです。
意識は明らかにファシリテーション層にあって、「相手の頭にどのようなイメージを植え付けようか」、「そのためには、どんな枠組みで話せばいいのか」、「そもそも、聞き手はどんなタイプの人なのか」などですね。
もちろんこれって目に見えるものではないから、外から見ると一緒に見えますが、結果は全然違っていて、なんと言っても伝わり方が違います。そして、これは私も後から発見して自分でも面白いと思ったのですが、人前で話してもあまり緊張しないんですよね、ファシリテーターは。
だって、ファシリテーター層で考えれば、その場をコントロールしているのは話し手なわけで、テニスで言えばサービスの権利を持っているようなもの。ブレークされない限りはよっぽど優位に試合を進めていくことができるので、緊張する必要がないんですね。
ちなみに、ディレクター層は、たとえば会議の参加者同士のファシリテーション層をすりあわせる、と言うイメージです。たとえば、「Aさんの話している枠組みと、Bさんの話している枠組みはそろっているか?」なんてのをチェックしながら適宜議論に介入<インターベンション>しているわけです。
さて、ここで問題。これまで述べてきたのは、どちらかというとロジカルシンキングによるコミュニケーションの話。
実は、相手の気持ちを動かすと言う心理に重きをおいたコミュニケーションでもPFD三層構造は活きてきますが、今度は、”P”と”F”はそれぞれ何を意味しているでしょうか?(”D”はディレクターのままなのがヒントになりますね)
もしも、これまでコミュニケーションがなかなかうまくいかない人がいたら、ひょっとしたらそれはプレゼンテーション層にしか注目していないからかもしれません。
実際、これまで他の場所で行ってきた「講師養成講座」でも、驚くほど多くの人がコミュニケーションが違ってくると実感しています。
ちなみに、そんな中の最年少が、当社でインターンをやっている23歳のK君。「いやぁ~、卒業発表のとき、役に立っちゃいましたよ~」と、学生でも学べるようになっているのは、「PARLの法則」、「コロンボ・テクニック」など、ビジネスに必要なファシリテーションを軸に体系化されたカリキュラムだから。
興味がある人はファシリテーターの勉強会も開催していますので、ホームページをチェックしてみてください。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13