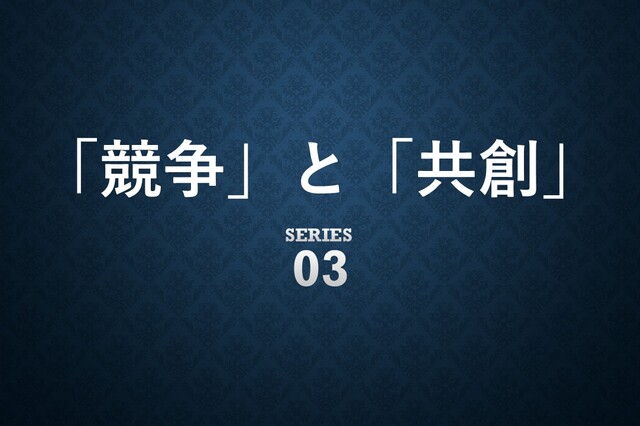西田幾多郎と蓑田胸喜のお話。
植村和秀『「日本」への問いをめぐる闘争 京都学派と原理日本社』(柏書房)を読む。
西田幾多郎と蓑田胸喜のお話。
蓑田胸喜、名前だけは聞いていた、というか、目にしたことのある人。あまり芳しくない文脈の中で。
なので、いわば怖いもの見たさで読んだ感もある。
さて、読後感。
うーむ、どっちもどっちかなあ、という感想。
その思想内容以前に、この時代に、もしリアルタイムで自分が生きていたとしたら、どっちに与しただろうか、というところに興味がわいた。
……どっちも読んでません、という可能性が極めて高いですが。
国語力的に、ちょっとおもしろかったところ。
西田幾多郎が積極的に動いたのか、政権側が求めたのかは不明だが、昭和十八年、東條英機政権に対して、西田が提言を行なった。
陸軍軍務局長をはじめとする政権側の人たちに西田が講話を行ない、その講話内容を西田が文章にして政権側の人に渡したそうな。
《しかし陸軍側に理解不明のため》(p266)
政権側の人が書き直したうえで、「要路に配布」した由。
陸軍側がどうのうこうの、と言いたいわけではない。
コミュニケーション一般の問題として、ちょっとおもしろいな、と思ったわけである。
①難解な内容を難解に表現する
②難解な内容を平易に表現する
③平易な内容を難解に表現する
④平易な内容を平易に表現する
の4つがあるとして、①④はまあ、普通ですね。
③は、しばしば、よくない例とされます。
一見、②がもっともステキに見えますが、では、はたして②は可能なのか?という問題です。
もし不可能であるなら、その「難解な内容」は、そもそも多くの人に理解されることをハナっから断念せねばならなくなる。先の例で言えば、西田の提言が西田の意図どおりに伝わらなかったとしても、それはやむをえなかったわけですね。
もし可能であるなら、その「難解な内容」を平易に表現しないのは、表現する側が多くの人に理解される努力をしていないか、多くの人に理解されることを望んでいないか、あるいは他に理由があるのかもしれませんが、いずれにせよ、多くの人に理解されるのをわざわざ拒んでいるように見えるわけです。
関連記事
2015.07.17
2009.10.31