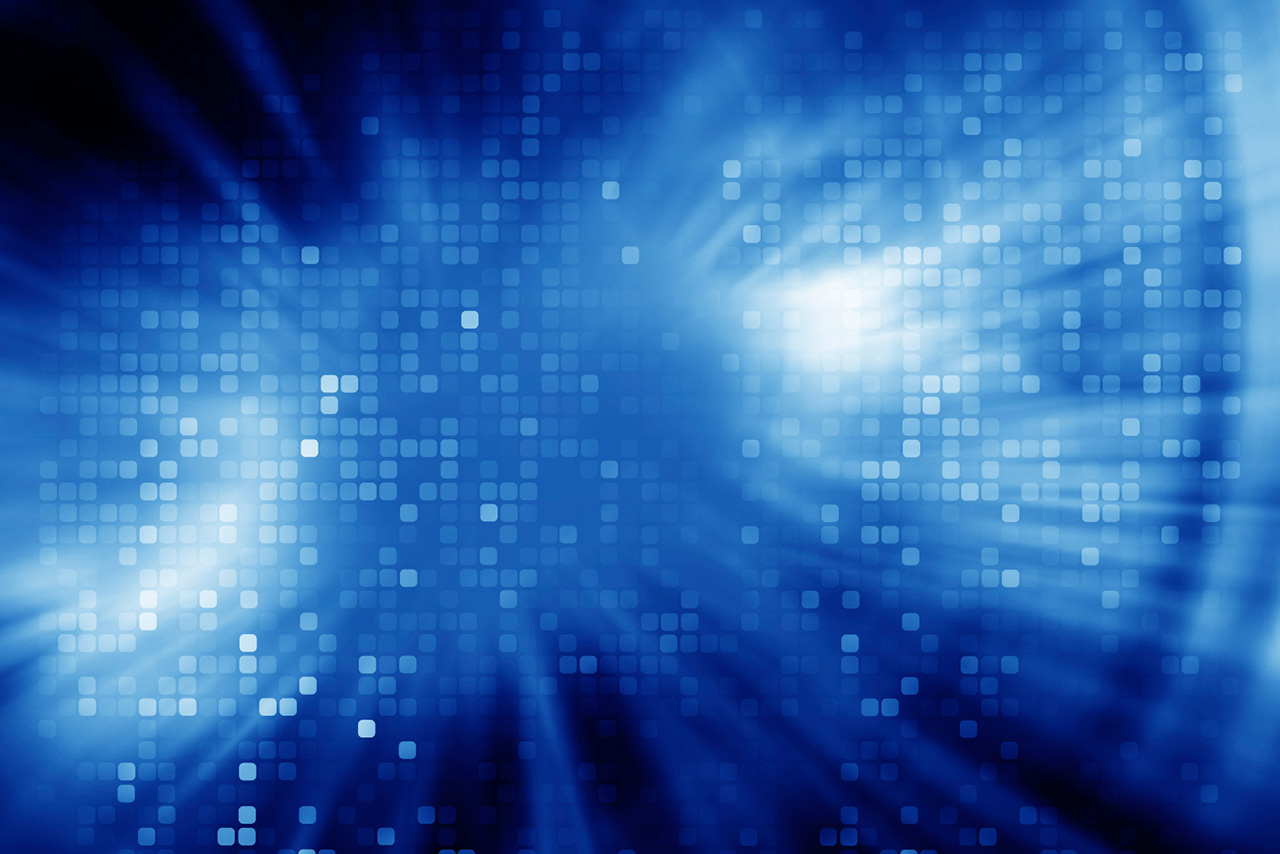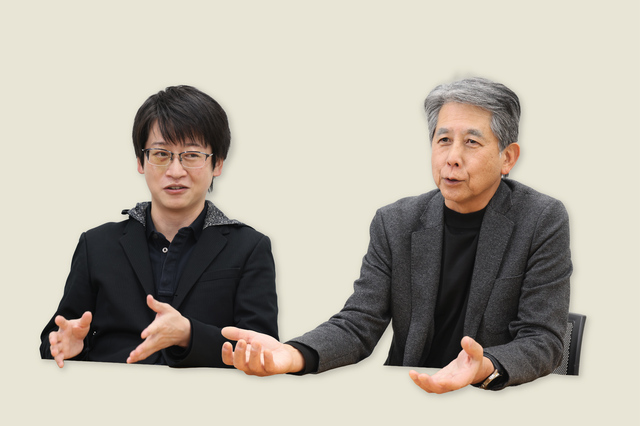B2Bマーケティングの教科書を読みますと、いくつかの興味深い数字が出てきます。「37%と57%」「5.4人」「1/3問題」などですが、これらの数字が何を意味しているか、皆さんはわかるでしょうか。
「購買」というキーワードでWeb等を検索すると、資材などの調達、という意味だけでなく、個人や企業の購買行動のような、マーケティングや営業プロセスの視点での説明も、かなり多く出てきます。
もちろん、モノやサービスを企業を代表して買う立場と、買う人達に売る立場は、全く逆です。ただし、企業として買う立場であれば、その逆であるB2Bマーケティング、B2Bセリングの戦略的、戦術的なプロセスや手法を常に追及しており、バイヤーがそれを知っておくことも、無駄ではありません。
私は前職も含め、コンサルティングという、目に見えないサービスのマーケティングや営業をする立場です。そういう視点から、昨今のデジタルマーケティングの発展や活用も含め、どのような手法やコンテンツを、誰宛てにうつべきかを、常に勉強しています。
そういう中で、今回、いくつかの気づきがあり、ここで紹介していきましょう。
一番強く感じたことは、「企業の近年の購買改革が、B2Bマーケティングのやり方を変えた」ということです。
従来より、私も、B2B営業の方々向けに、企業の購買部に対する、マーケ、営業の戦略や手法を、営業向け研修として、度々ではないですが、伝授してきました。ただし、これらの研修は、私自身の経験を元にしたソリューションであり、体系的なアプローチでり出したものではありません。そういう点からは、営業マーケ部門向けのソリューションとしては、まだまだ、不十分なものでした。
B2Bマーケティングの教科書を読みますと、いくつかの興味深い数字が出てきます。「37%と57%」「5.4人」「1/3問題」などですが、これらの数字が何を意味しているか、皆さんはわかるでしょうか。
まず、57%ですが、ある調査で、一般的なB2B購買プロセスを初めから終わりまで、イメージした時に、どの時点でサプライヤの助言を求めるか、ということ調べた結果になります。つまり、サプライヤの営業パーソンにコンタクトし、直接の提案やアドバイスをもらう前に、顧客は既に、平均で購買プロセスの57%まで、進んでいるということです。
一方で、顧客がソリューションを決め、社内での導入を決める段階は、平均すると全プロセスの37%とのこと。つまり、37%と57%のギャップは、顧客がニースを特定し、優先順位付けや、ニーズを満たすための要件の決定、その要件を満たせる、サービス提供会社候補の決定などであり、それをバイヤー企業は単独で行っています。
従来、B2Bマーケティングでは、早期に顧客のペインを一緒に発見し、ソリューション営業をすることが肝要、とされてきたのですが、今は、そもそも37%の段階や、もっと早期にサプライヤに声がかけられることが、殆どなく、多くの場合、あとはコストで勝負の段階である57%の時点まで、進んだ状況で声がかかっている、ということなのです。
次は5.4人です。近年B2B購買に関する、意思決定に関わる人は平均5.4人であることが、やはり調査で分かっています。従来は部門担当役員がOKであれば、決裁が通る、と言われていましたが、近年、購買案件に関わる人が増え、今までは、関わっていなかったような役割の人達も、かかわるようになりました。
例えば、法務部門の担当役員や、営業・企画部門担当、最新では、サステナビリティ担当まで、幅広い人たちを考慮しなければならなくなったのです。
最後は1/3問題です。ある企業の営業担当が、「うちは必ずお客様が購買先を決めるときに、サプライヤ候補として必ず呼ばれます。でもその時には、必ず3社候補企業があり、うちはその3社の一つであり、最後はいつも価格競争になります。」と言っています。これが1/3問題です。
このように、B2Bマーケティングの世界の従来の常識が、崩れ去ってきています。また、興味深いのは、これらの変革がサプライヤ側の問題ではなく、どちらかというと、買い手側の購買改革によるものだ、ということです。
つまり、サプライヤの最大の競争相手は、ライバル企業の販売力ではなく、むしろ顧客の決断力にあります。そして、問題の本質は、サプライヤが上手く売ることができないのでなく、顧客組織が上手に買えないことにあるのです。
2025年11月11日に、ワンマーケティング株式会社が発表した「BtoB購買プロセス白書2025」によると、上述の数値の傾向は、ますます極化しています。
まず、57%ですが、やや視点は異なりますが、購買プロセス全体の中で、サプライヤとの初回面談時に、購買先候補を、ある程度絞り込んでいる企業が、全体の85%を占めています。(前回2020年調査時は79%)つまり、サプライヤにコンタクトが来たときには、既にある程度、購買候補先は決まっており、その傾向は今後も高くなるということです。
また、1/3問題については、提案を受けた購買先候補は調査によると、平均4.4社であり、購買金額が高くなるほど、提案会社数は増加傾向にあり、より競争は激化していることです。
また、5.4人という意思決定に関わる人数は、全体平均では9.5人と広がっており、これは2020年の6.3人から増加傾向となっています。
このように、特に大企業の、購買意思決定は、限定的な個人ではなく、グループや委員会方式で決定される、また、購買検討と同時に、営業接触前に購買検討が動き出すため、如何にWebサイトなどで、事前に認知してもらう仕掛けが重要、ということが分かります。
一方で、繰り返しになりますが、これは従来の属人的な企業の購買意思決定プロセスの改革による、購買企業側の購買改革によるもので、サプライヤのマーケティング・営業戦略の進化がきっかけになった変革ではない、ということです。
実際に、日本企業の購買意思決定プロセスが改革されたのは、おそらく直近10数年位からでしょう。それまでは、限られたキーパーソンを抑えておけば、サプライヤは、自分たちのモノ、サービスを上手く売ることができていたのです。それに対して、やれ、相見積しろ、サプライヤの総合評価が必要、などの購買改革を大企業中心にこの10年位で、進めてきたのは、紛れもない事実でしょう。
一方で、この先を考えると、行き過ぎた競争主義からの見直し、上流段階でのサプライヤのインボルブによる、最適ソリューションの採用などが、進んでいくと考えます。
ただ、何れにせよ、企業の購買改革が、進む中で、マーケティング、営業の戦略や手法も同時に変わってきており、変わっていく必要があることは間違いありません。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
調達購買コンサルタント
調達購買改革コンサルタント。 自身も自動車会社、外資系金融機関の調達・購買を経験し、複数のコンサルティング会社を経由しており、購買実務経験のあるプロフェッショナルです。
 フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る
フォローして野町 直弘の新着記事を受け取る