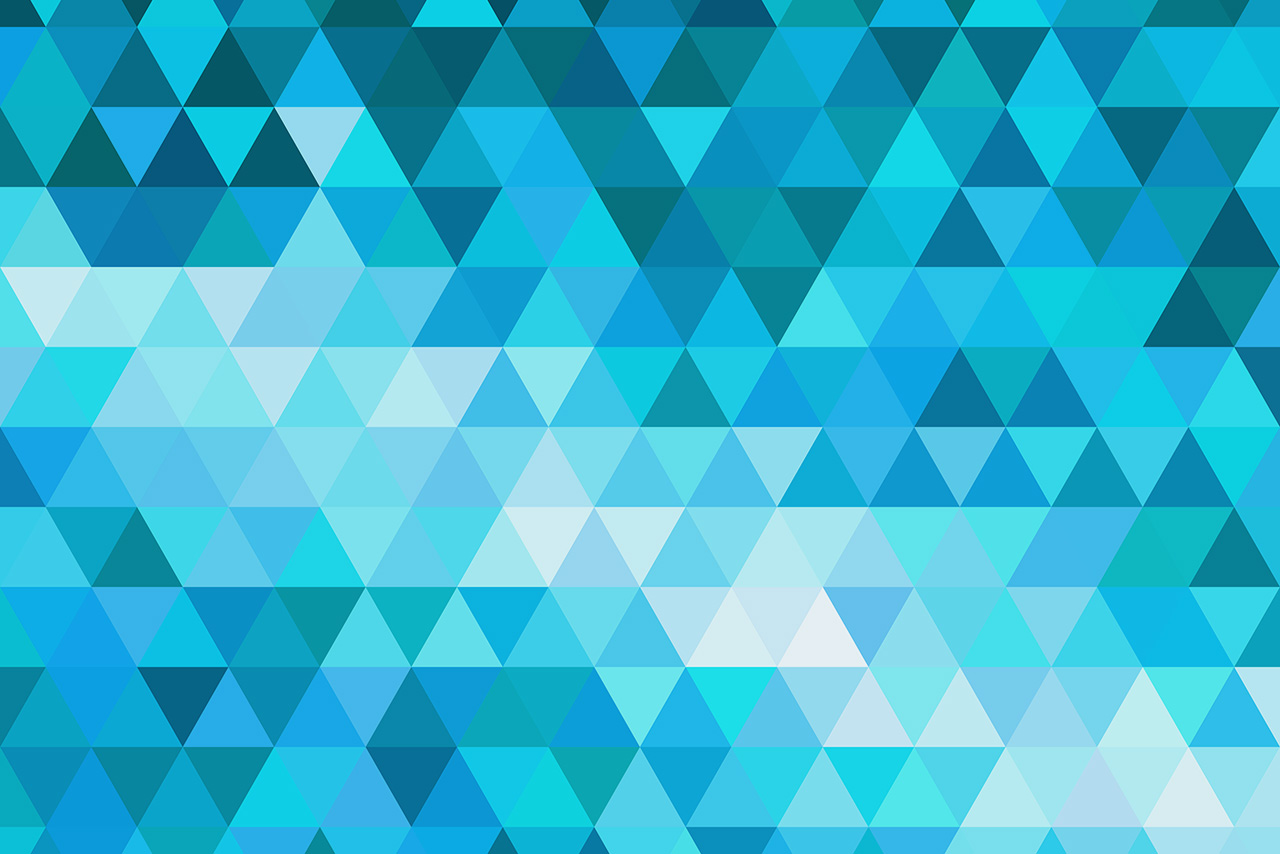2025.08.25
なぜ、あの人には人がついていくのか? ― 徳を宿すリーダーがチームに灯すもの ― 共鳴型リーダーシップ2話
齋藤 秀樹
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
なぜ、あの人には人がついていくのか? 誰もが経験したことがあるだろう。 どれほど理路整然と話しても、人を動かせない上司がいる一方で、 言葉少なでも、人の心を動かすリーダーがいる。 それは、スキルの差でも知識量でもない。 その人の「人格」が放つ信頼の力が、周囲に伝わっているかどうかである。
よく言われるように――
「組織の器以上に、チームは成長しない」
ここでいう“器”とは、リーダーの人格の広さであり、次のような視点を持てているかが問われます:
リーダーの器が狭い場合 リーダーの器が広い場合
自分の成果・評価が最優先 チーム全体の育成・風土づくりを重視
他者の失敗を許容しない 失敗を糧とする挑戦に価値を置く
結果だけを重視し、プロセスを見ない プロセスを大切にし、信頼をベースに任せる
人格あるリーダーは、自分の器に他者の成長や挑戦を包み込める人です。
だからこそ、部下は恐れず意見を出せ、チャレンジできる。
このようなリーダーの下では、静かな退職(心の離脱)は起こりません。
■では、“徳”はどう育てるのか?
徳や人格は、先天的な性格ではなく、「選び続ける姿勢」から育ちます。
以下は、日々の実務に落とし込める“徳を磨く実践法”です。
【徳を育てる3つの実践】
1 「人格の棚卸し」を毎週1回行う
- 今週、自分が誠実でいられなかった場面は?
- 謙虚さを欠いた判断はなかったか?
- 誰かに共感できなかった場面は?
→「できていないこと」を否定ではなく、“磨く余地”と捉える習慣を持つ。
2 「判断の基準」を“正しさ”から“誠実さ”へ
- 相手の立場ならどう思うか?
- この選択は、短期的な得より長期的な信頼につながるか?
3 「自分よりも、チームを前に出す」機会を意図的に増やす
- 会議や報告の場で、自分の成果ではなく部下の貢献を語る
- 賞賛や注目の場を、部下へ譲る
■明日からできること
リーダーの人格は、「特別な研修」ではなく、「日常の選択と関わり」で育まれます。
以下は、明日から職場で実践できる具体行動です。
【実践アドバイス|徳を宿す行動5選】
- 部下の話を“遮らず最後まで聴く”1日1人
- 感情を伝える:「嬉しい」「ありがとう」「悔しい」
- 誤りを認める:「ごめん」「助かった」
- 自分の影響範囲を自覚する:「空気をつくるのは自分だ」と意識
- チームに“意義”を語る時間を持つ:「この仕事が誰に届いているか」
■自己マネジメントの問い(振り返りワーク)
- 自分は“知識や地位”ではなく、“人格”で信頼されているだろうか?
- 「誠実さ」や「利他性」が、自分の日々の選択に表れているだろうか?
- チームメンバーは、自分の在り方に“安心”や“尊敬”を感じているだろうか?
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る