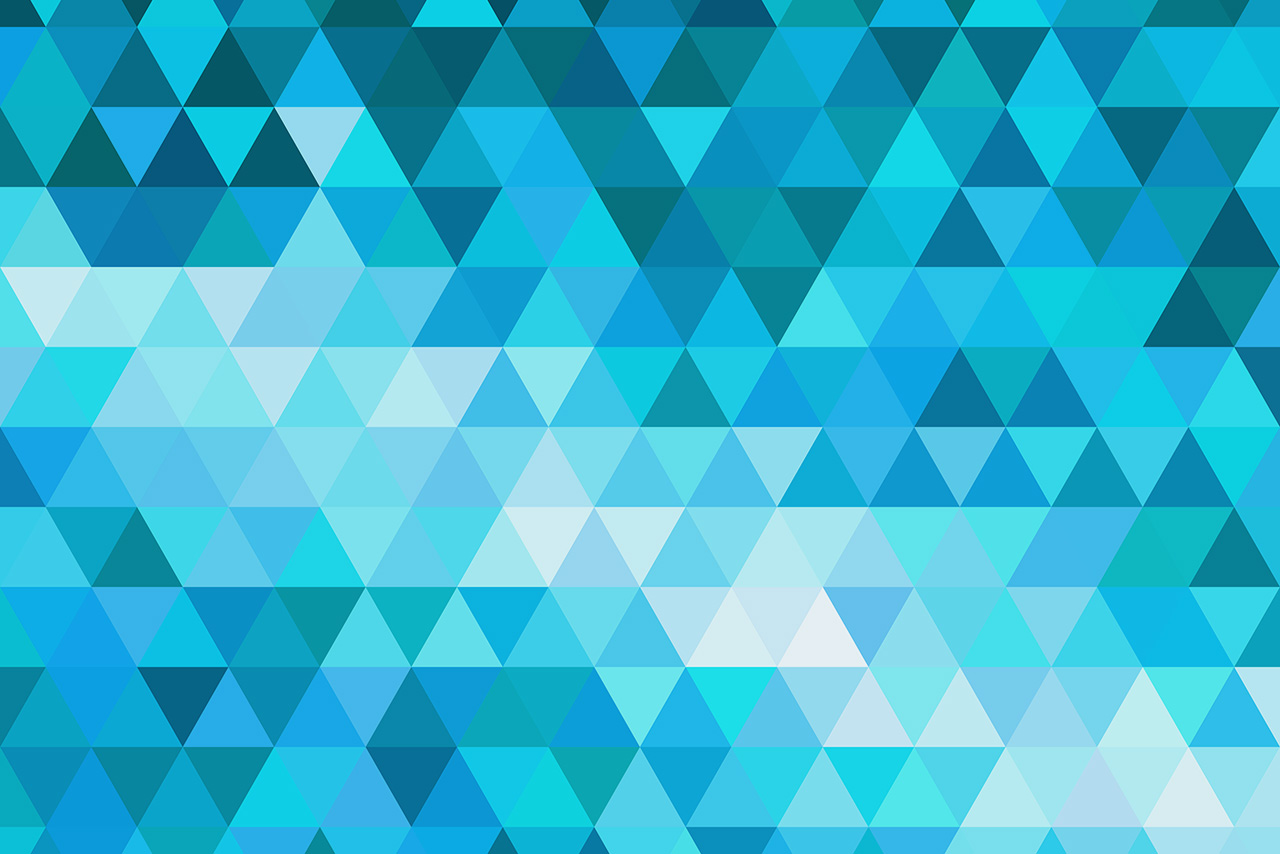今回は、評価制度を構築する際に客観性と主観性をしっかりと使い分ける必要があるということ。そして、その主観性を下に評価する部分については、「誰が評価するのか」が最も重要なポイントになることについてお話します。
悩みのポイントは、いくつかあり、まずもって配属されたお店によって運、不運がすごくあるということです。駅に隣接していて人通りが多くて、お客様が入りやすいお店と、そうじゃないお店とでは、お店自体の成績が大きく変わってくるから、一人ひとりの成績にも差が出てきてしまいます。
さらには、それまでは店長に評価の権限がなく、本部の役員が全部評価をしており、実際の仕事ぶりを評価に反映しようがなかったのです。
お客様が取り組まれたのは、まずもってお店の立地や取り扱い商品などの有利不利の条件を加味して店舗成績の評価をするということ。
この点には究極まで客観性にこだわり、ありとあらゆる数値化を試みておられました。
その上で、店員の評価はいくつかの指標を用意して本部の役員ではなく、身近で観ている店長の目を信じて評価権限を与えたということ。
このように・・・
〇店舗の評価については、あくまでも客観性にこだわりデータ化して不公平感をなくす。
〇各店舗のスタッフの評価は、いくつかの指標は設けるものの、店長の観る目を信頼する。
という二つの観点を持って人事制度を見直していることは、大いに参考になることではないかと思います。店舗の評価に究極まで客観性を担保するかわりに、店舗の中での店長の評価には主観があっても当然だという割り切りの元で設計されています。
【人事部の仕事は人を観ること】
今回、客観性と主観性というタイトルではありますが、同じくらい、「誰が評価するか」ということが重要だということができます。これは人事制度にとって極めて重要なポイントではないでしょうか。
役職に評価権限が付与されているとしたら、誰を偉くするかで社員の運命が左右される重大事ということになります。
そういう点では、少し強引なまとめになるかもしれませんが、『人事部の仕事は「人事制度を回す」ことではなく、人を観ることだ』という言い方もできるのだと思います。
株式会社マングローブ
今野 誠一
毎日ブログ更新中
http://www.bc-mgnet.com/
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
人事制度について
2011.01.18
2011.01.07
2010.12.22
2010.12.15
2010.12.08

今野 誠一
株式会社マングローブ 代表取締役社長
組織変革及びその担い手となる管理職の人材開発を強みとする「組織人事コンサルティング会社」を経営。 設立以来15年、組織変革コンサルタント、ファシリテーターとしてこれまでに約600社の組織変革に携わっている。
 フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る
フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る