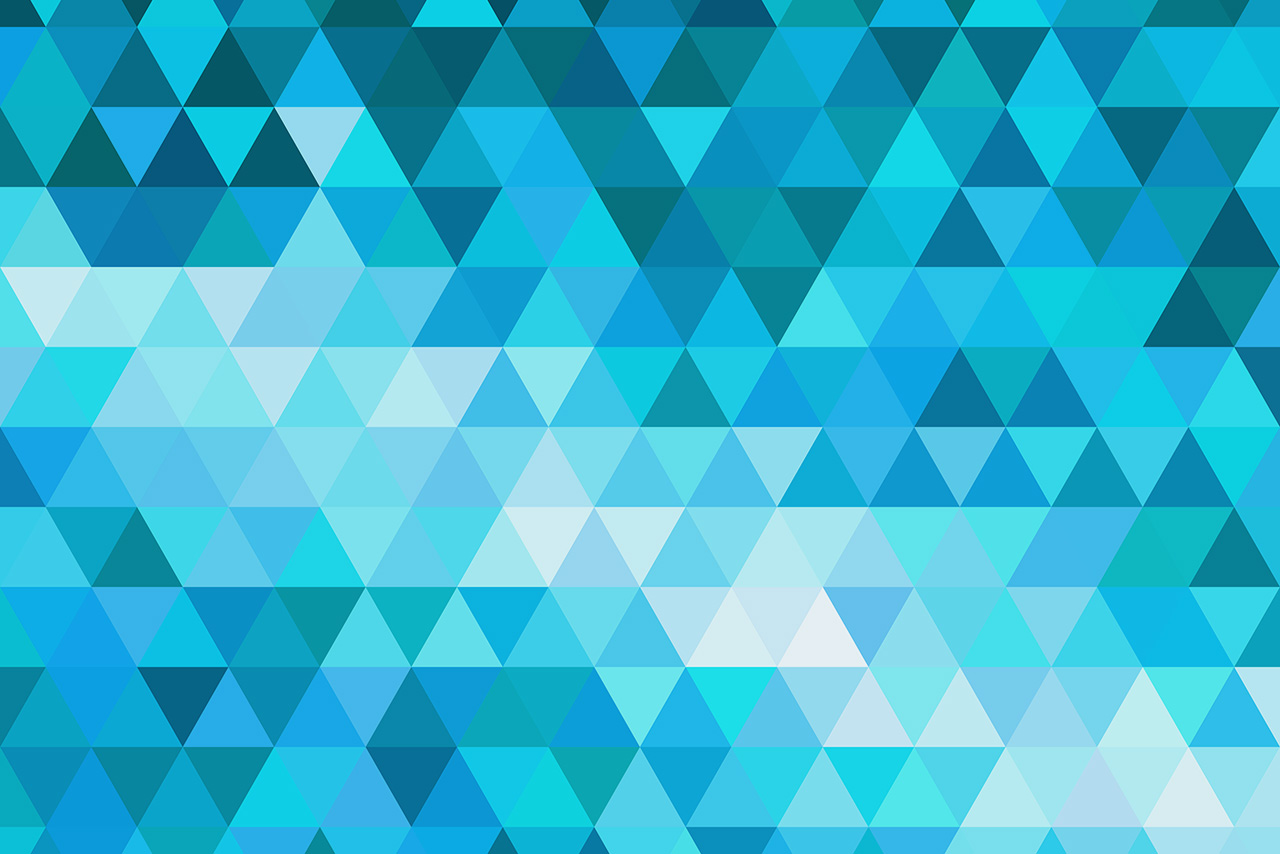今回は、評価制度を構築する際に客観性と主観性をしっかりと使い分ける必要があるということ。そして、その主観性を下に評価する部分については、「誰が評価するのか」が最も重要なポイントになることについてお話します。
なにしろ、人をきちんと観ることができる人、メンバーを預けるに足る人を昇進させることは、ともて大事なことではないでしょうか。
社員の立場に立った時に、どんな人に評価してほしいかという観点も大事です。
私だったら、まずは社員に愛情を持っている人に評価されたいですね。どんなに取り繕っても、社員に愛情あるマネジャーかそうじゃないかはわかるものです。人事制度という会社の仕組みに乗って、ただ単に義務感で評価シートを書いているような人には評価されたくない。
私がリクルートグループの人事部長時代、1500人の評価シートを熟読するのを自分に義務付けていました。一人ひとりに愛情を持って、頑張っている姿を応援するつもりで、育てるつもりで観ている人の評価シートと、そうでない人の評価シートは一目でわかります。
その次は、やはり仕事のできる人に評価してもらいたいということです。成績を上げている人ではなくて、「仕事のできる人」にというところがポイントです。成績を上げている人が必ずしも仕事ができる人とは限らないからです。ラッキーもあれば、人を押しのけて成績を上げている人もいる。短期的に成績が上がっても、それが続かないのが難しいところですね。本当に仕事ができる人は、派手さはないけれども、正直にきちんとすることをして、着実に力をつけようとするから長続きするのです。
私はそういう人に評価してもらいたいですし、そういう人でないと自分がいくら頑張って地道なことをしていてもわかってもらえないと思います。
最後に、会社のことをよく分かっている人という観点も重要です。会社の理念と将来の方向性と、社長が何に価値観を置いているのか、といったことをよく理解している人に評価してほしいですね。そうでないと、自分が会社のためによかれと思って取り組んでいることが理解されずに、とんちんかんな評価をされそうな気がするからです。
【客観的評価と主観的評価との兼ね合い】
この「客観的評価」と「主観的評価」との兼ね合いというものは、よくよく慎重に考えなければなりません。上に書いたことを読むと、私が「評価は主観的でいいんだ」と決めつけているように感じるかと思いますが、そうではありません。
「客観的評価」にこだわるべきところと、「主観的評価」でもいいと割り切るべきところを見極めて設計しなくてはならない、ということです。
ひとつ例を出しますと、お店をいくつも持っていて、販売員の評価を検討していたお客様がいました。従前、お店の店員の評価というものがうまくいかなくて悩んでいたのです。
次のページ【人事部の仕事は人を観ること】
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
人事制度について
2011.01.18
2011.01.07
2010.12.22
2010.12.15
2010.12.08

今野 誠一
株式会社マングローブ 代表取締役社長
組織変革及びその担い手となる管理職の人材開発を強みとする「組織人事コンサルティング会社」を経営。 設立以来15年、組織変革コンサルタント、ファシリテーターとしてこれまでに約600社の組織変革に携わっている。
 フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る
フォローして今野 誠一の新着記事を受け取る