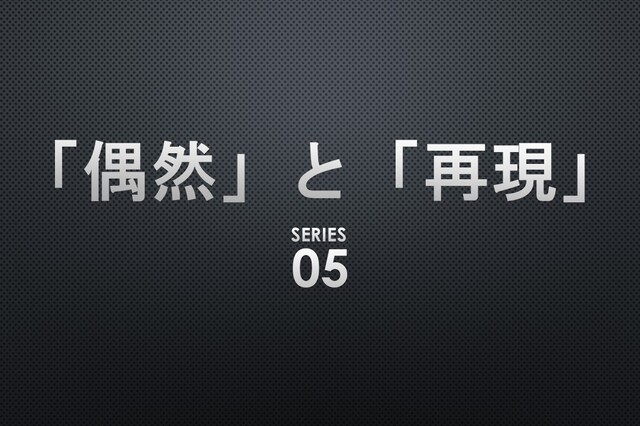ラーメン店など、飲食店のテーブルでおなじみのコショウ「GABAN」。その創業期の営業物語がポータルサイト・exciteのコラムで紹介されていた。そこにはB to Bマーケティングのキモが隠されていたのである。
B to Bでもう一つ重要なことは、DMU(Decision Making Unit:購買意志決定・関与者)を洗い出し、動かすことだ。ギャバンの創業者営業の話には、記事の続きがある。
<シェフのお墨付きを手に、そのレストランが取引する問屋を紹介してもらうことで、取扱店は少しずつ増加。この手法が、1980年代には中国料理店や焼肉店でも行われ、今のように全国のあらゆる飲食店で、GABANのコショウが見られるようになったという>とある。
コショウなどの香辛料はメーカーから飲食店が仕入れる場合よりも、問屋が仲介する場合が多い。その場合、シェフ自身は仕入れを決める立場の人(=Decision maker)であるが、問屋はさらにまだギャバンを認知していないシェフに紹介してくれるという影響者(influencer)というDMUになる。シェフは「美味しい料理を作る」という関心事があり、問屋には「飲食店が喜んで仕入れてくれる商品を取りそろえたい」という関心事がある。DMUがどこにいる誰で、どんな関心事を持っているのかを把握することが重要なのだ。
では、GABANはシェフ達にどのような商品として受入れられたのだろうか。ポジショニングの問題だ。B to Bの場合、B to Cと異なって、どのような要素を訴求すればいいかを二軸のポジショニングマップで検討するよりも、シンプルにして重要なことがある。Q・C・Dの3つの要素をどう訴求するかだ。Q=Quality(品質)、C=Cost(価格)、D=Delivery(納期)である。例えば、日本電産の永守社長は自社のスローガンとして、「確かな技術、値段は高め、しかし納期は半分」といっている。明確なポジショニングを示しているわけだ。
では、GABANはどうだろうか。創業者が説得するだけあって、品質にはじしんがあるところだ。記事にも<1940年代後半から50年代にかけて、日本に流通するコショウの多くには、小麦粉やパン粉が混ざっていた。原因は原料不足。そこで創業者は、食事の洋風化が進めば香辛料の需要も増え、“混ざり物がないコショウは売れるはず”と考えた。そうして1954年、エイト食品(現ギャバン)が設立された>とある。まずは、品質ありきなのだ。価格と納期に関しては記述がないが、恐らくGABANは「品質は最高、価格は高め、納期は普通」のようなQCDのポジショニングなのではないだろうか。
B to Bマーケティングは公開された事例がなく、他社から学べる機会が少ないという声がよく聞かれる。しかし、つぶさに観察すれば、ラーメン店のテーブルでも見つけることができる。そして、そのセオリーを愚直に踏襲することが成功の秘密であったりするのである。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2015.07.10
2015.07.24
有限会社金森マーケティング事務所 取締役
コンサルタントと講師業の二足のわらじを履く立場を活かし、「現場で起きていること」を見抜き、それをわかりやすい「フレームワーク」で読み解いていきます。このサイトでは、顧客者視点のマーケティングを軸足に、世の中の様々な事象を切り取りるコラムを執筆していきます。
 フォローして金森 努の新着記事を受け取る
フォローして金森 努の新着記事を受け取る