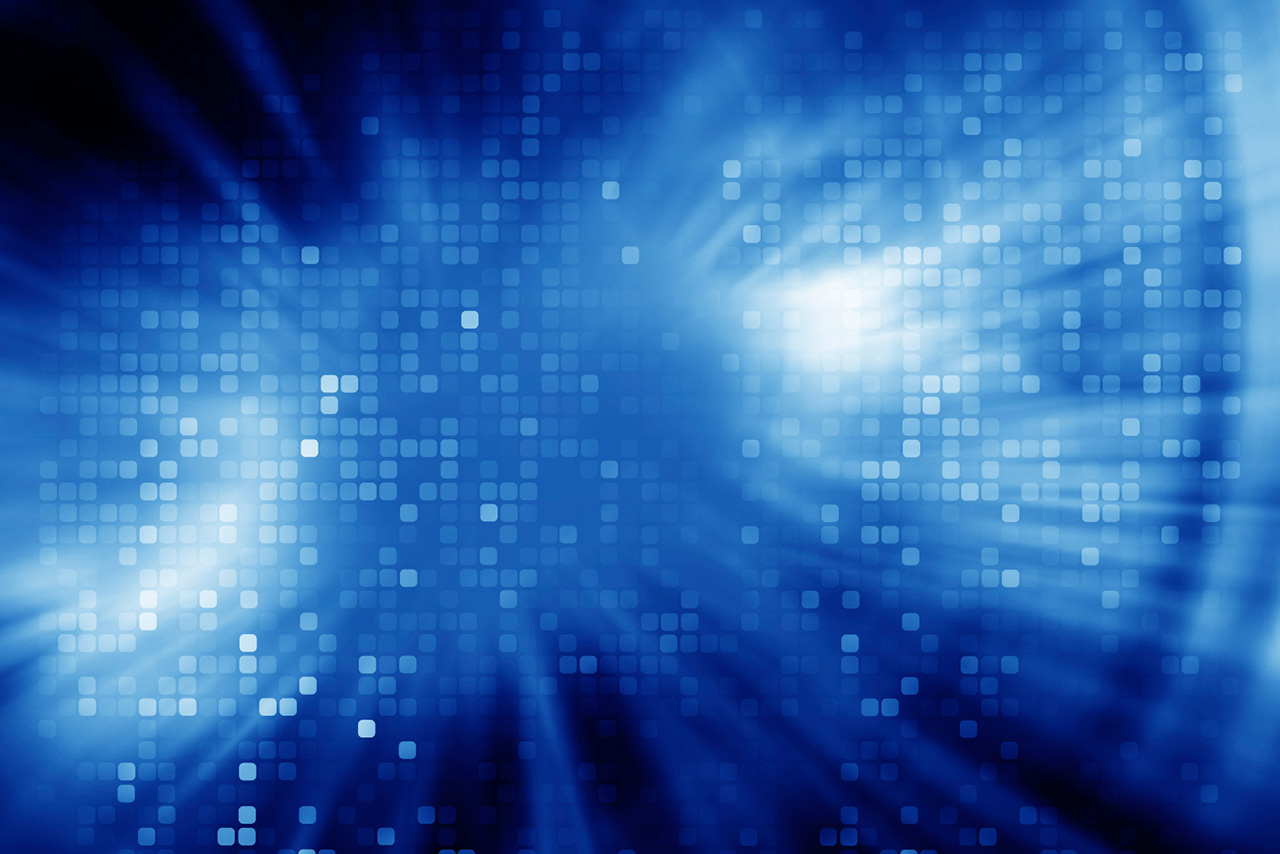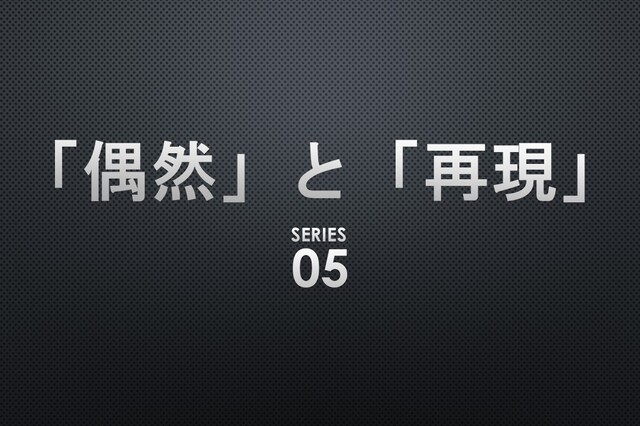大不況の中で、企業はどのように体質改善を図るべきか。これからの時代にあるべきマーケティングの姿を考えます。
どこを切っても不況、不況の「不況和音」(?)
「ニッポンのマーケティングは、どこへ行くのか」なんてタイソーなことを
正月休みに、お屠蘇気分でつらつらと考えていました。
で、結論。 (ハヤッ!)
1人の天才マーケッターより、現場100人のマーケティング志向。
これです。
当たり前だと言われればそれまでなのですが、では実践できているかというと、
まず、ほとんどの企業ではできていない。
一部上場の大企業だろうが、非上場の中小企業だろうが、できていない。
なぜか?
それは、マーケティングが、経営者や専門職のスキルだと考えられていたから。
本当にそうだろうか?
多くのMBAを擁しているであろうビッグ3は、いまやバッド3だし、
カンバンとカイゼンで世界に名を馳せたTOYOTAも急失速している。
どんなにエクセレントなマーケティング戦略も、永遠に輝き続けるわけでは
ない。
消費の多様化ということで、商品は既に少量多品種に対応している。
サービスも「個客対応」が謳われている。One to Oneマーケティングに
必要な条件整備はほぼ整っているのに、組織のマネジメント・スキルだけが
「規模の拡大=利益の拡大」という巨艦主義のまま追いついていない。
現場で小回りの利くマーケティング・マインドが育っていない。
なぜか?
きっと、「マーケティング言語」が足りないから。
「マーケティング言語」とは、小難しい理論や知識のことではありません。
お客様の行動や商品の動きの変化を、同じ概念で語ることのできる
「共通言語」のことです。
メロディを伝えるときは、口ずさむのが一番早い。 (たぶん、音痴でも。)
マーケティング・マインドを伝えるときには、マーケティング用語や理論を
知らなくても、そのコアな部分を伝える「言語」があるべきなのです。
購買行動の8割以上は、無意識(≠衝動)に支配されていると言われます。
また、人は理性で考え、感情で決断すると言われます。
その決断の結果が「顧客データ」です。何よりも雄弁な顧客からの
メッセージです。
こうしたデータという数字やグラフに基づいて会話できるか否かで、
その企業のマーケティング・スキルは大きく違ってくるはずなのです。
ただし、
事件(マーケティング)は、会議室で起きているのではない。
現場(売場や工場)で起きているのです。
現場でマーケティングできなければ意味がない!
100種類の現場があれば、100種類のマーケティングがある。
100種類のマーケティング志向のオペレーションが必要になる。
(当然100種類のマーケッターも必要になるので、INSIGHT NOWは
まさにそのあたりも狙っているのか、な?)
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26