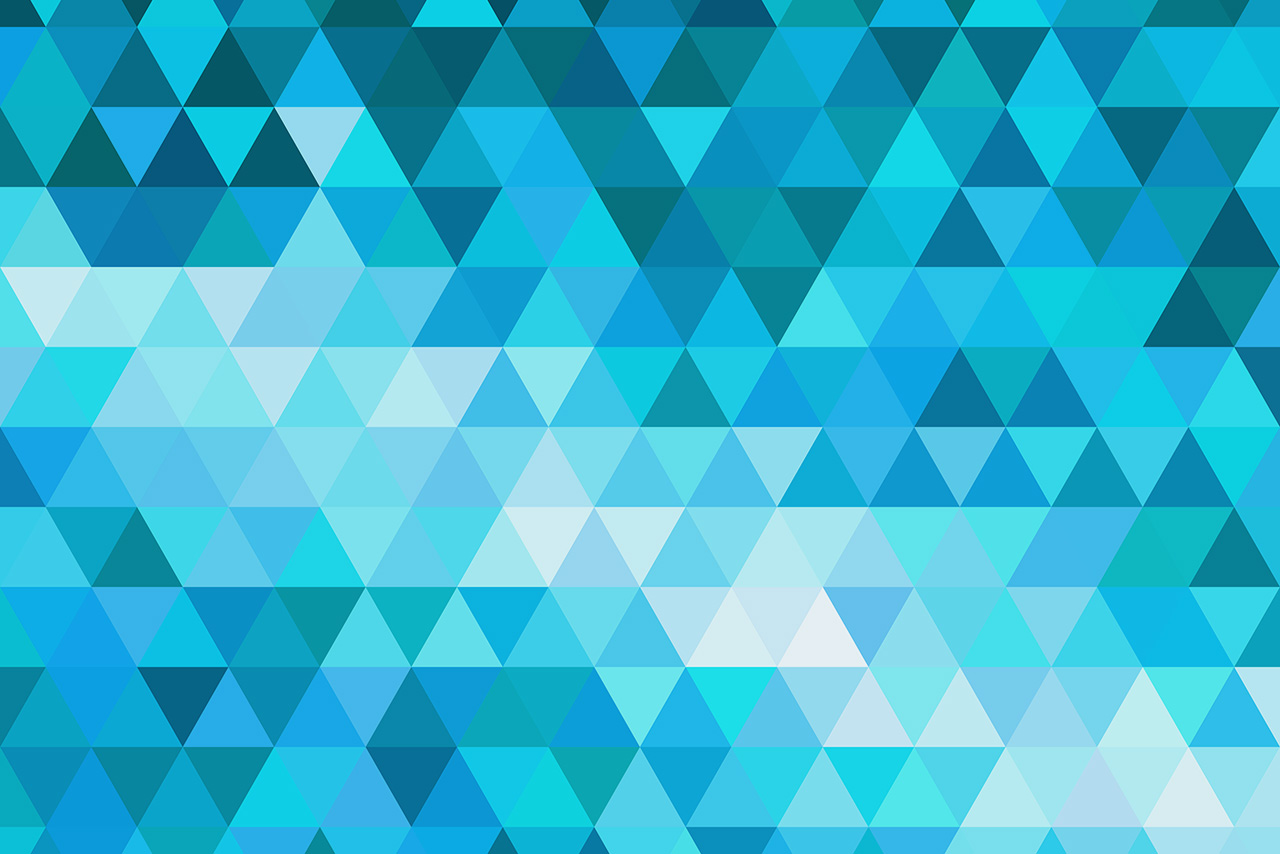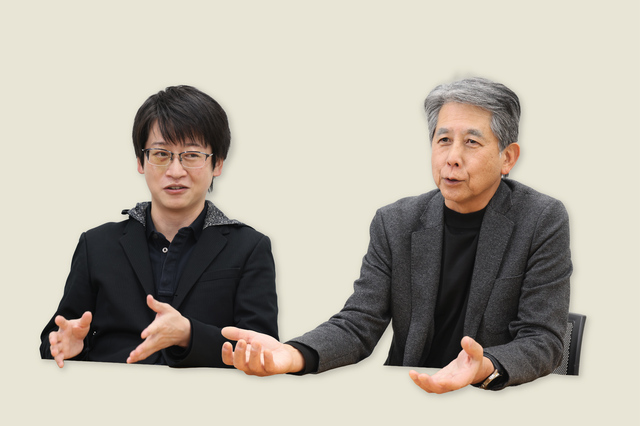NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀スペシャル」で、宮崎駿監督がお話されていた言葉から、「なぜ、これだけのパフォーマンスを出せるのか?」を読み取り、それを若手の人材育成に転用して考えてみる。
******************************
先日、NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀スペシャル」にて宮崎駿監督がこんなことをおっしゃっていた。
自分がこの仕事をしているのは『人に楽しんでもらいたいから』
人に楽しんでもらえてこそ自分の存在の価値があると感じることが出来る。
ハイパフォーマーは、総じて「誰かのために、役にたちたい」という類のことを言う場合が多い。これは、なぜだろうか?
理由は、動物として、人間の「脳」が発する欲求が基幹にある。というのも、脳は、例外なく社会で、よりよく生きたいという欲求を持っているからだ。原始時代から、人は、他人と協力することなく、生きることはできなかった。だからこそ、「①人に愛され(受け入れられ)、②自分に自信をもち、③他人の役にたつ。」つまり、この社会において、他の人とよりよい関係が作れると、幸せを感じられるように脳が創られてきたのである。
この観点から考えると、「他人の役にたてれば、たてるほど、自分が受け入れられ、自分に自信もつく。」という趣旨の宮崎監督の言葉は、いわば、プロセス(=キャリア)を経て醸成された、成果を出せる人材特有の動物的な本能から発せられている言葉であるように私には感じられた。
ところで、上記で、①から③まで番号を振ったが、大切なのは、この順番である。たとえば、本質的に「①自分が愛されない(受け入れられていない)」ということを感じている限りは、②自分自身に自信をもつことはできないし、③他人の役に立とうとは思えないように脳の構造は構成されている。
この論理は、組織内での若手の人材育成に応用できる。宮崎監督がハイパフォーマーになった過程を踏まえて、トレースしてみよう。
例えば、よく、若手人材と話をしていると、「誰かの役にたちたい」という類のことを言う人がいる。だが、話をきいていると、「自分に自信がない」とも言う場合がある。
過激な書き方になるが、この場合、「誰かの役にたちたい」というのは、ウソである。仮に理屈(顕在意識)では、そう考えていたとしても、本能(潜在意識)では、誰かの役にたちたいという欲求は発していない。「誰かの役に立つことで、人に感謝され、自分が満たされたい。」という寂しさを満たす行為として仕事を活用しているだけなのだ。(NLP(神経言語プログラミングの英語訳で、カウンセリング法の一種)では心理ゲームと呼ぶ)
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13