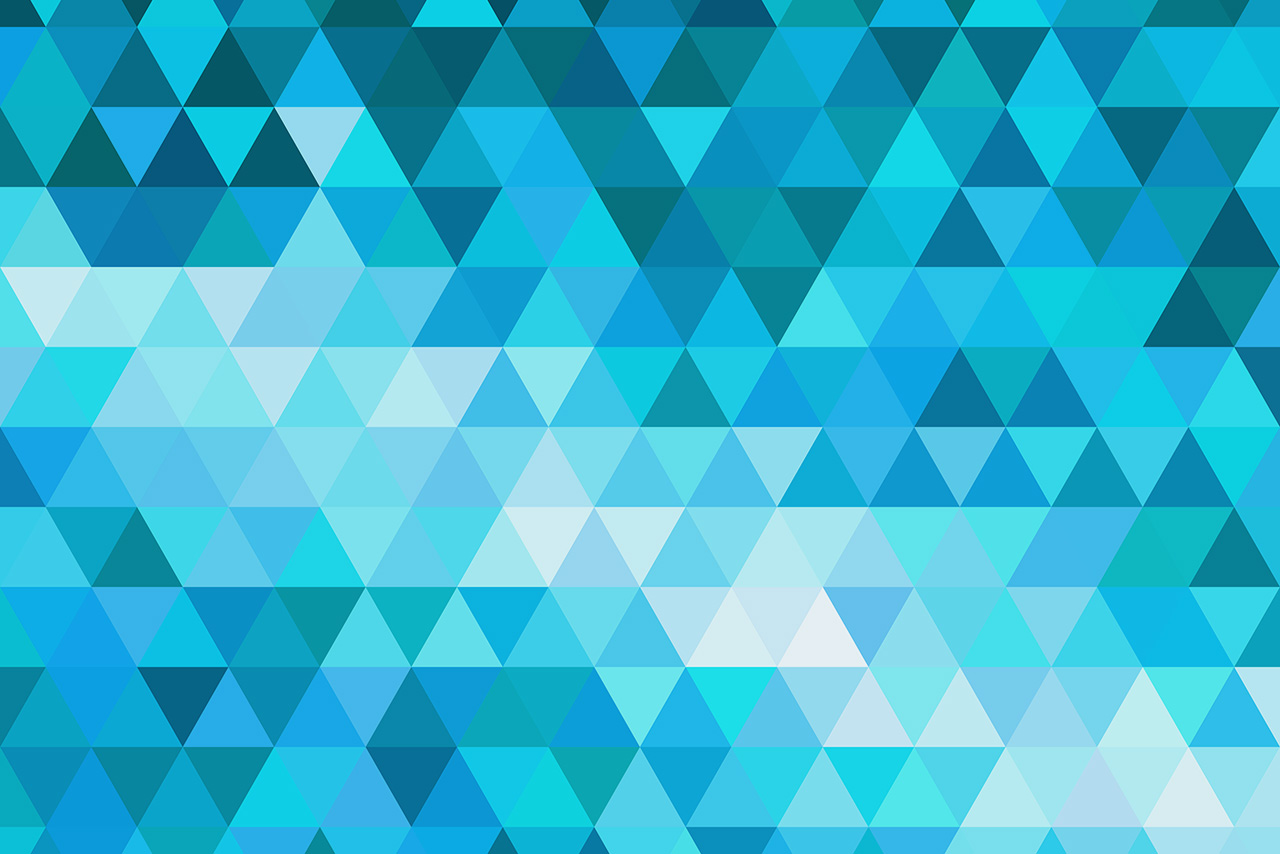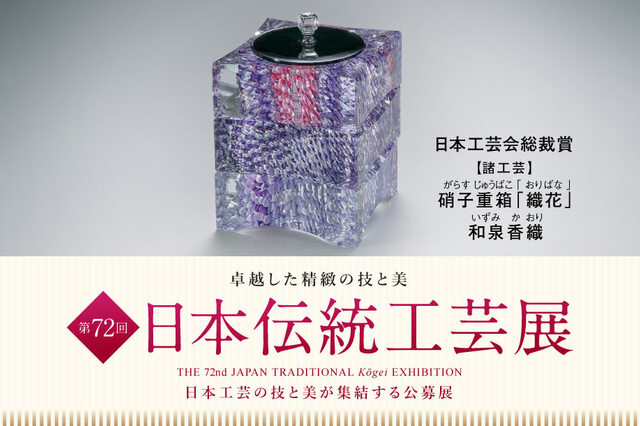2025.09.08
“完璧な正解”が、部下の成長を奪うとき ― 教える力ではなく、育む力が未来をつくる ― 共鳴型リーダーシップ3話
齋藤 秀樹
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
“完璧な正解”が、部下の成長を奪うとき 「部下から質問されたら、すぐに答えられるのが上司の役目だ」 かつての現場では、こうした“指導力”こそがリーダーの資質とされていた。 だが、今この「即答力」が、部下の思考と挑戦心を奪ってしまうケースが急増している。
ここで、部下育成において有効なフレームワークがある。
それが、ラーニングサイクル「Do → Look → Think → Grow」である。
このサイクルは、単なるPDCAではなく、「内省と対話」を核とした成長循環である。
ステップ 意味 上司の問いかけ例
Do 行動したこと 「どんな行動をしたの?」
Look 起きたことを観察・振り返る 「何が起きた? どう感じた?」
Think 背景・意図・価値観を掘る 「なぜ、そう考えたのだろう?」
Grow 気づきから未来を描く 「次はどうしたい?」 「どんな自分を目指したい?」
このサイクルを“対話”のなかで繰り返すことが、
部下の「内省力」×「行動力」×「目的意識」=自走力を育てる。
■実践例:「問いかけ」から部下の成長を引き出す現場
実際に、コーチング型マネジメントで成果を上げた事例をご紹介します。
ケース:入社2年目の営業社員・Sさん(20代)
- 初期は上司の指示待ち。ミスを恐れて積極的に動けない状態だった
- 直属のマネージャーが、「すぐ答えない」「問いで返す」スタイルへ転換
- たとえば「どう提案したらいいですか?」→「君だったら、どうする?」
- 最初は戸惑いながらも、徐々に自分なりの仮説を持ち、行動に繋げるように
- 半年後、自分から改善案や新しい提案を出すように変化
この変化の背景には、「信じて待つ」マネージャーの姿勢と、問いかけが思考の習慣を育てたことがある。
■成果主義とのバランス:「問い」が創る“持続的成果”
「そんな悠長なことより、すぐに結果を出させたいんだよ」
現場マネージャーの多くが、この葛藤に悩んでいる。
たしかに、問いかけには時間がかかる。即効性がないように思えるかもしれない。
だが、ここで立ち止まって考えてみてほしい。
短期的な“正解の模倣”と、
長期的な“自走する思考力”のどちらが、組織にとって価値があるか?
コンサルティング企業McKinsey社のレポートによれば、“自律的に意思決定できる社員が多い企業ほど、長期的な業績が安定して高い”という傾向が明らかになっている。
また、Googleの研究でも、創造性とエンゲージメントが高いチームは、「問いによる探求」を日常的に行っていることが共通点として挙げられている。
つまり、「問いかけるマネジメント」は、
表面的な成果ではなく、“思考の筋力”を鍛え、成果を持続可能にする土壌をつくる手法なのだ。
■育成における「信じる力」がもたらすもの
問いとは、信頼の表現である。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る