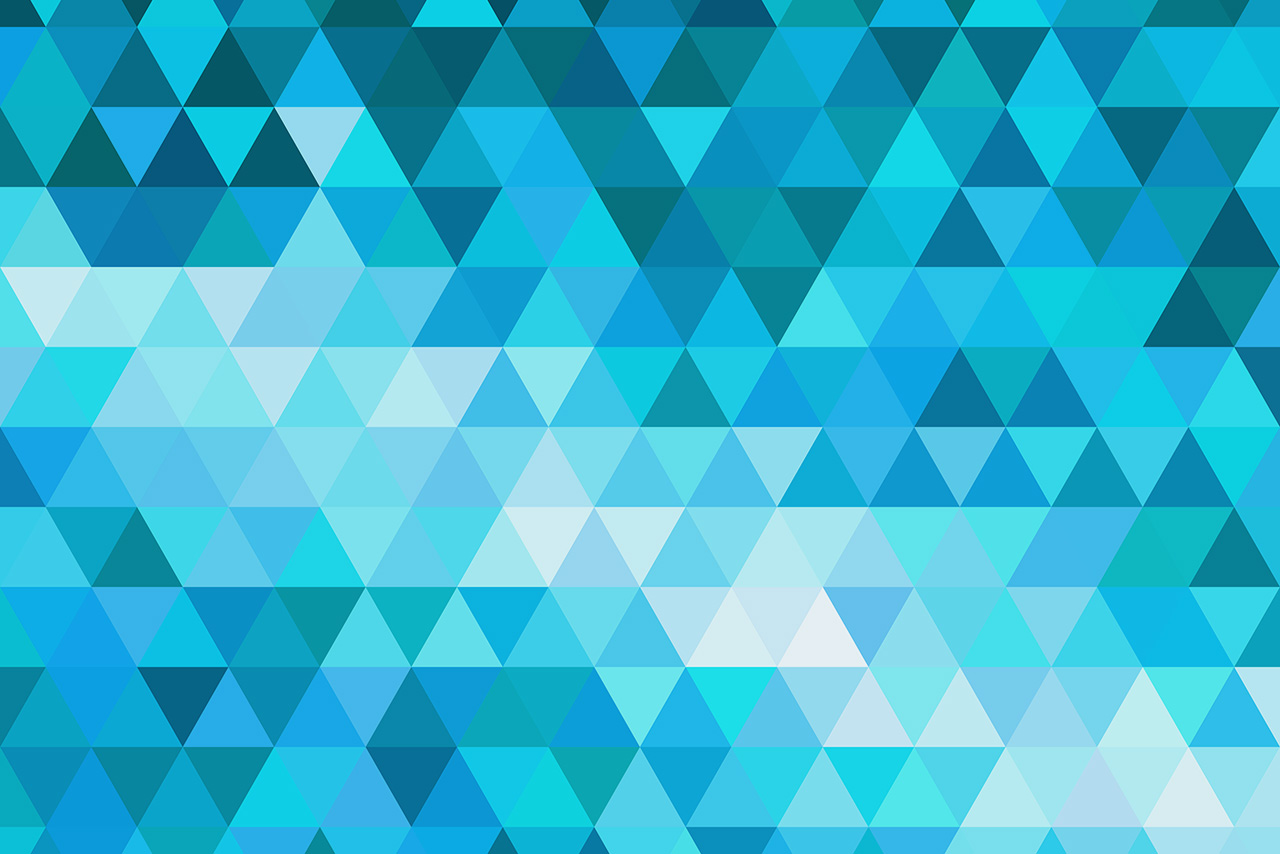2025.08.12
「背中を見て学べ。文句を言わずにやれ」の終焉 ― 支配型マネジメントの終焉と“静かな退職”の増加 ― 共鳴型リーダーシップ1話
齋藤 秀樹
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
これまでの執筆もまとめつつ、「共鳴型リーダー」という新たなリーダー像を念頭にその軸となる土台を5話にまとめました。 1話は支配型マネジメントからの脱却がテーマです。 「強い管理職」の時代背景とその終焉 「背中を見て学べ。文句を言わずにやれ。」 かつて多くの職場で聞かれたこの言葉は、ある種の“美学”として通用していた。高度経済成長期を支えたのは、上からの指示を的確に遂行する従順な社員たちと、強いリーダーシップで指揮を執る管理職だった。
そして、その起点となるのは、リーダー自身の“在り方”である。
【実務アドバイス】
🔹 明日からできること:3つの行動
- 部下に「なぜそれをやるのか?」の意味を毎回伝える
- 日々の声がけに「ありがとう」「嬉しい」を増やす
- 週1回は“雑談”の時間を設け、関係性に投資する
【自己マネジメントの問い】
- 部下が「本音で話せない」空気をつくっていないか?
- 自分は“正しさ”ではなく“信頼”で人を導いているか?
- 「この人と働きたい」と思われる上司でいるだろうか?
■CASE:なぜ、あの職場では“静かな退職”が起きなかったのか?
関東のとあるIT企業。20代社員の離職率が3年連続で30%を超えていたこの会社では、マネージャー層が常に疲弊し、現場のモチベーションは枯渇していた。
そんななか、一人のリーダーだけは別だった。30代半ばの女性リーダーAさんが率いるチームは、社員の在籍年数が長く、離職者もほぼゼロ。エンゲージメントサーベイの結果も毎年トップ。
秘訣を尋ねると、彼女はこう答えた。
「特別なことはしていません。ただ、“この人は信じてくれている”って思ってもらえるように、毎日丁寧に向き合っているだけです。」
さらに続けてこう言った。
「リーダーが“圧”で人を動かすと、最初は従ってくれても、最後は心が離れる。でも、“想い”で人を巻き込むと、自分のことのように動いてくれる。」
それはまさに、“支配”ではなく“共鳴”で導くリーダーの姿だった。
■DATA|「静かな退職」が増える職場と減る職場の違い
Gallupが示す重要な示唆のひとつに、「職場の70%の空気は、直属の上司が決める」という統計がある。実際に、エンゲージメントが高いチームの上司は以下のような特徴を持つ:
項目 低エンゲージメント上司 高エンゲージメント上司
指示の出し方 命令・管理型 対話・目的共有型
関係性のあり方 業務中心の接触 感情的なつながりを重視
フィードバックの頻度 トラブル時のみ 定期的・肯定を含む
組織の語り方 数値・KPIのみ ビジョンと意義の両方
仕事の意味づけ “やらねばならない” “やりたいからやる”
離職率 高い 極めて低い
Gallupはさらに、「最も離職に影響するのは“給与”よりも“上司”である」という分析も提示している。
つまり、“静かな退職”は会社全体の風土だけではなく、上司ごとのマネジメント次第で「起こるチーム」と「起こらないチーム」に分かれるのだ。
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役 一般社団法人日本チームビルディング協会 代表理事
富士通、SIベンダー等において人事・人材開発部門の担当および人材開発部門責任者、事業会社の経営企画部門、KPMGコンサルティングの人事コンサルタントを経て、人材/組織開発コンサルタント。
 フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る
フォローして齋藤 秀樹の新着記事を受け取る