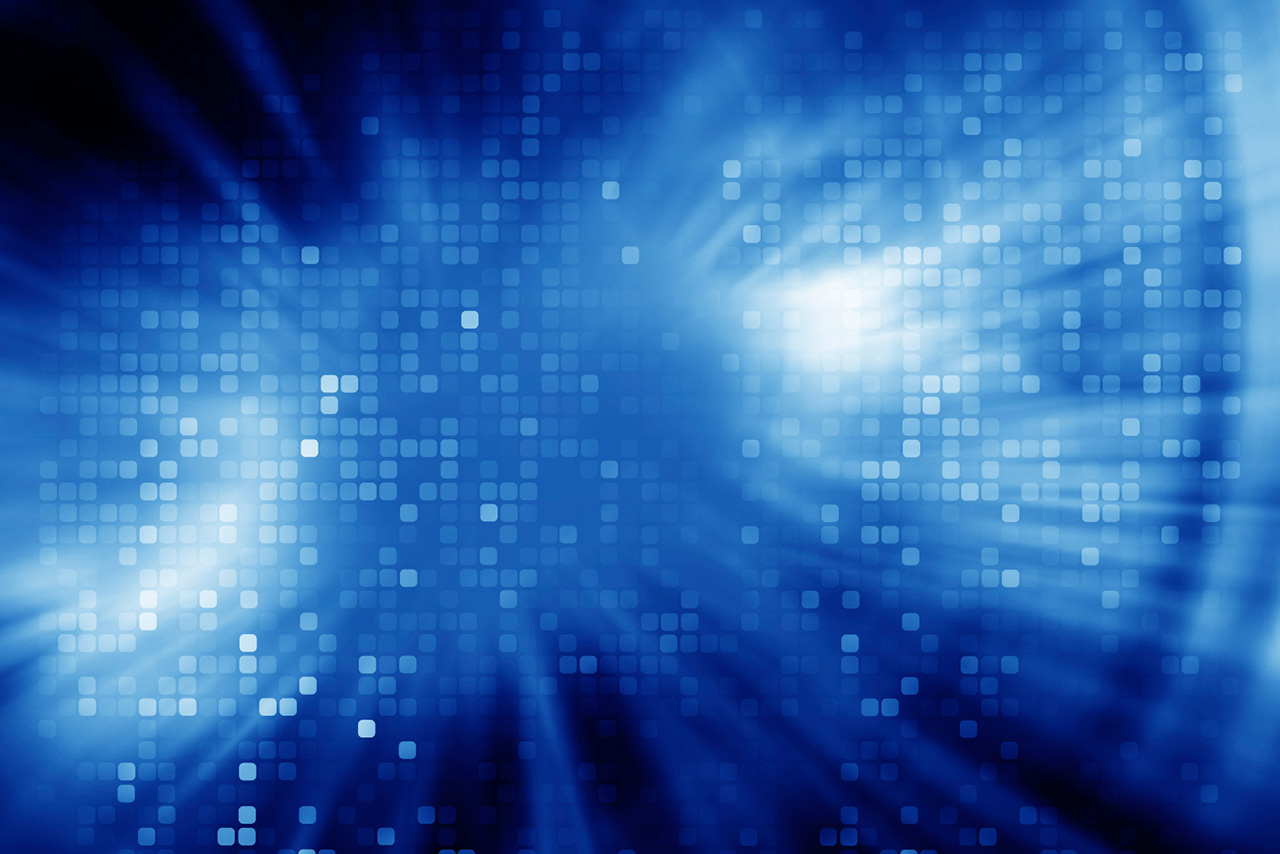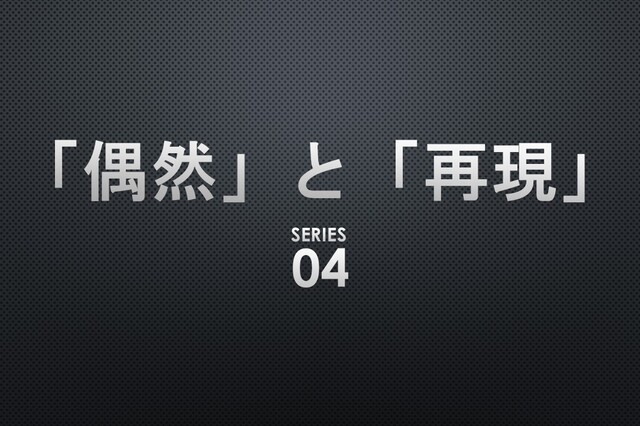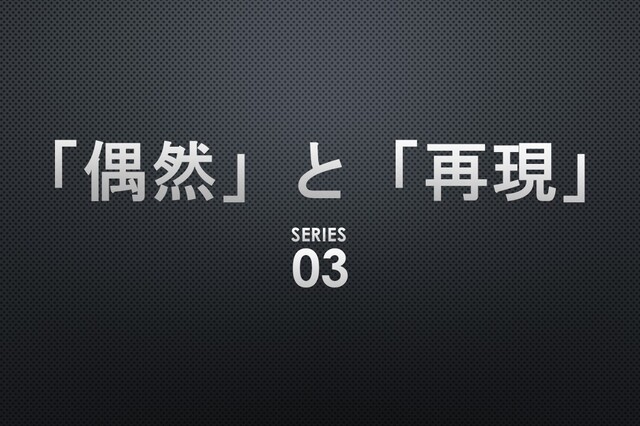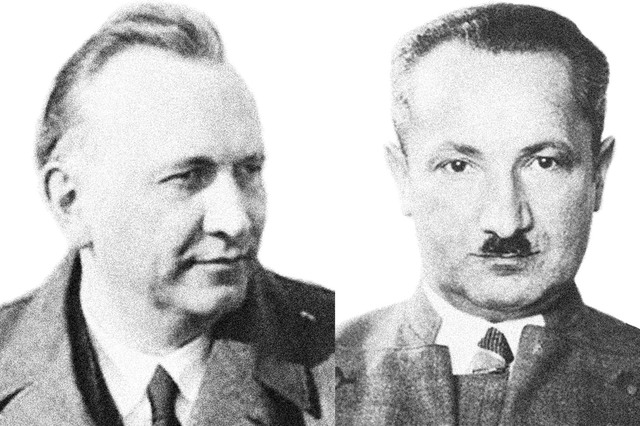安倍首相の突然の辞任劇は、モチベーションが多様化する中で、その点を意識した効果的なコミュニケーションがリーダーには求められることを痛感させるものとなった。 しかし、多様なモチベーションを意識した効果的なコミュニケーションとはいかにして実現できるのであろうか?
記事によると「若者たちは携帯を自分の一部とみなしているようであり,それが手元にないとパニックを起こすことさえある」と説明している。
人から孤立するのを恐れて,多くの若者がいつでもどこでも携帯電話をオンにしているのである。
「携帯に着信がないと,不安やいらいらを感じ,だれからも必要とされていないと感じ始める」のである。
そのような不安に駆られて,たいていは必要ないのに,すべての着信メールにすぐ返信するのが習慣になってしまう。
もちろん,携帯電話にはメリットはあることは承知の上である。
実際,緊急時には極めて有用である。
普段でも,バランスの取れた使い方をすれば必ずしも悪いものではない。
しかし,携帯電話「中毒」になると通常のコミュニケーション能力が損なわれかねない,と述べる専門家もいる。
デイリー・ヨミウリ紙によると,大阪のある中学校教諭は,携帯電話のために「子どもたちが,表情やしぐさや声の調子などから相手の気持ちを読み取る力を失いつつあるのではないか」と心配しており,「その結果として,子どもたちは攻撃的になり,人の気持ちを意に介さないようにもなっている」とのことである。
今日よく聞かれるもう一つの表現として,「データ転送」という言葉がある。
これは,情報を電子的に伝達することを指している。
それなりに評価された役割があるとはいえ,これは完全な意味での良いコミュニケーションではない。
なぜだろうか。
人は機械にではなく,人間に最もよく反応するからである。
データのやり取りをする場合,顔の表情は見えない。
視線を合わせることも,身振りもない。
実は、それらが多くの場合,会話を形成し,感情を伝えるのである。
向かい合って会話する場合,これらの要素が言葉を補い,意味をはっきりさせることが少なくない。
電子的なやり取りでは,こうした大いに理解を助けるものが、テレビ会議などの手段を改めて使わなければ、どれも使えないのである。
テレビ電話で多少改善されたとはいえ、人気の携帯電話の場合も同じことが言える。
実際に向かい合って会話する場合でさえ,往々にして,話し手の考えていることがそっくり伝わるわけではないのだ。聞き手は自分なりに言葉を聞いて処理し,間違った意味を付すこともある。
まして、話し手が見えない場合,こうしたことの起きる危険ははるかに高くなるであろう。
では、現代のハイテク化された空間の中では、表情を失う危険があることに注意しながら、効果的なコミュニケーションを心がけて、組織崩壊のリスクを回避していこう。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26
株式会社インサイト・コンサルティング 常務取締役 COO(最高業務執行責任者)
個人と組織の成長を実現するために、真に効果的な人材育成のあり方を追求しています。国際競争力を併せ持つ能力開発を志ます。そのためには多様性を強みに昇華させることが肝要と心得ます。
 フォローして槇本 健吾の新着記事を受け取る
フォローして槇本 健吾の新着記事を受け取る