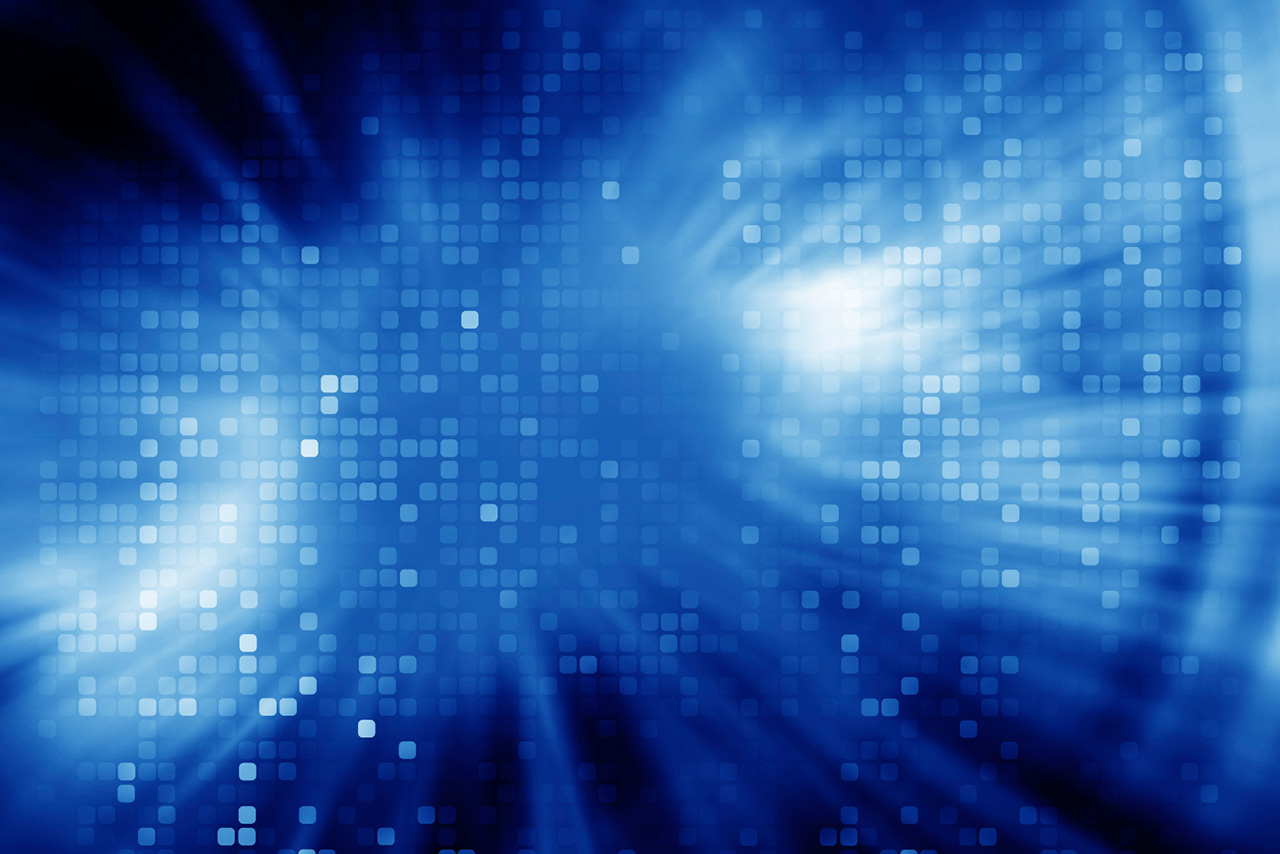「これがなくなったら、人間が生きていけいない」というものは何かと問われたら、あなたは何と答えるだろうか?かのアインシュタインは、「もし、ハチが地球上からいなくなると、人間は4年以上生きられない」と予言した。
格やレンタル料金が4割~5割値上がり、人手で受粉する農家も増えており、生
産コストは上昇傾向にある。当然これらのコスト増大は、消費者価格に転嫁せざ
るをえなくなる。これまでも収益力の低さに悩まされていた農家では、廃業に追
い込まれるケースも出てくるだろう。また、こうした経済面での影響だけでな
く、十分な受粉がなされず、でこぼことした形で緑色のまま成長が止まる「奇形
いちご」も生まれている。
この状況をみて、農林水産省は大きく2つの対策に着手した。一つは各県や関
係団体と連携した、ミツバチの需給調整システムの構築である。県単位で園芸農
家から、不足蜂群数の申告を受け、養蜂家からの調達を仲介するとともに、 日
本養蜂はちみつ協会や専門共有業者を介して県を超えてミツバチの供給を行うも
のだ。もう一つは、園芸農家への経営支援である。一定の自助努力を前提に、政
策金融公庫や農林漁業セーフティーネット資金の活用をしやすくする。これらの
対策は、経済的な観点で市場の安定化に短期的には寄与すると考えられる。初期
調査から2週間で対応策を発出した初動の速さも非難には当たらない。しかし、
構造的に需給バランスを調整するような効果は期待できないことは誰の目にも明
らかである。同時に、農林水産省はアルゼンチンからミツバチを生む女王バチの
輸入の検討も行っていくと発表した。しかし、「アフリカ化」と呼ばれる気性が
荒くて攻撃性の強いハチが日本の養蜂家の手に負えるのか懸念する農家も多い。
さらに、日本の生態系に適応し、病原菌に侵されていないかを検閲できたと言い
切ることは難しいと指摘する専門家もいる。要は、動植物の移動に伴う影響は必
ずしも、人間の予想や想定の範囲に収まるものではなく、日本の養蜂に適したハ
チを特定することもそれを正しく選出することも難しいということだ。ハチは、
機械の部品と同様には規格検査できないのである。
では、このミツバチ不足にどう向き合えばよいのだろうか?日本でのミツバチ
不足がCCDであるとの確証はないが、CCDの原因仮説を見ていくと我々が対峙す
べき問題の本質が見えてくる。CCDの原因としては、「①ミツバチの栄養失調
説」「②遺伝子組み換え作物説」「③新型ダニ説」「④電磁波説」「⑤農薬説」
などが挙げられる。但し、いずれも断定できるほど強力な根拠とはなっておら
ず、10年以上前から指摘されていた言説であることから、ここ数年での急速な
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2009.02.10
2015.01.26