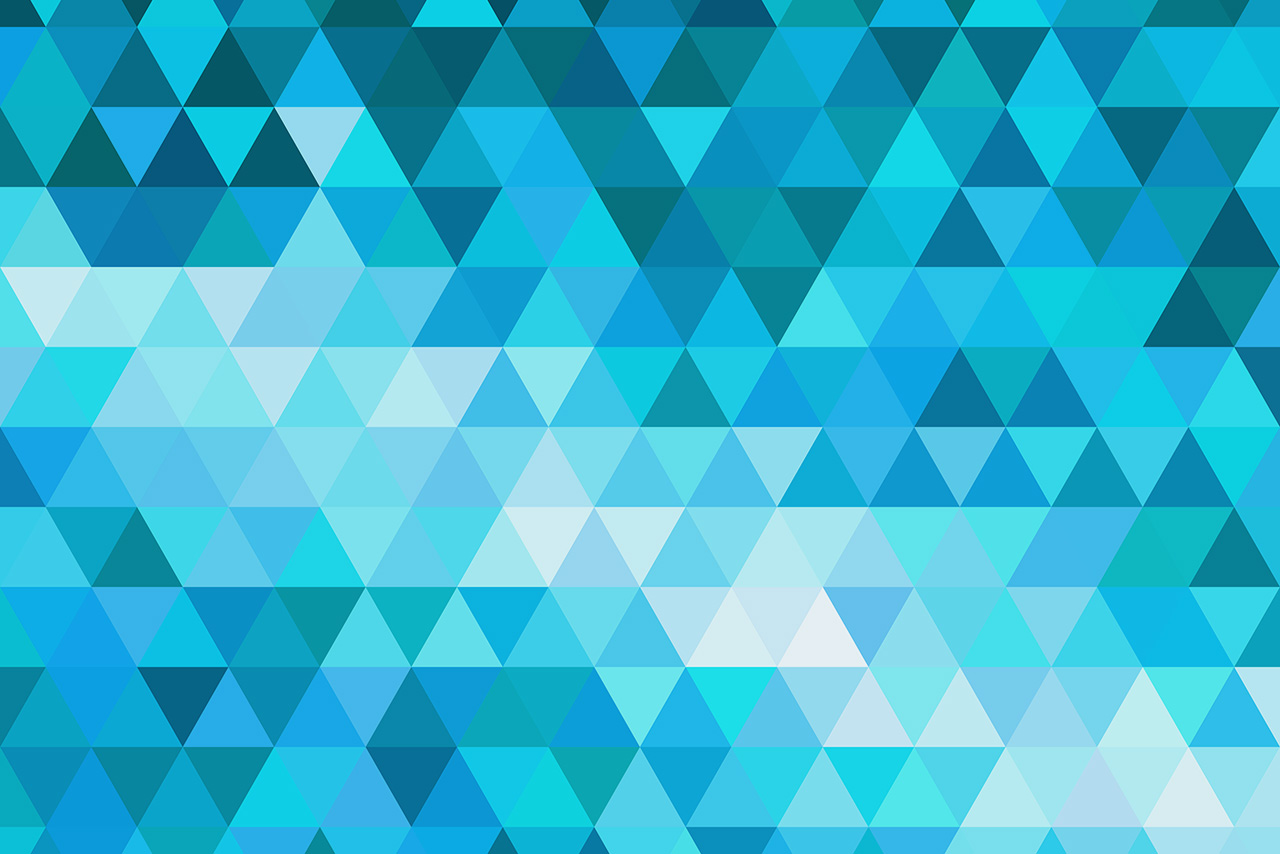自分って周りはどう見ているのでしょう。360度評価をすることで「つもりの自分」と「周りから見た自分」を比較すると思っても見なかった事実を突きつけられます。でもそこで終わってはもったいない。
今日ある会社で話をしている中でこんな話題になりました。
担当者「採用検査で代表されるように、自己申告型の検査は自分をつくろう
ことが出来るので弊社では一切信用していません。」
- それはそうですね。正直に答えた場合は
それなりにそのときの意識が反映されるのですが。
例えば「あなたはいつも前向きですか」という問いに対し
「いつもそう、たまにそう、たまにそうでもない、いつもそうでもない」
の中から受験者は答えを選びますね。
順風満帆なら「いつもそう」に○を付けますし、
調子がよくない時は「たまにそうでもない」につけてしまう
かも知れません。
おっしゃる通り、自分をよく見せようと思えば
「いつもそう」に○をつけることも可能です。
更に質問によっては自分自身はそうしている「つもり」の時もあります。
「あなたは他者の意見を尊重していますか」という問いに対し、
自分は「している」と思っているが、
実際はできていない人もいるわけです。
担当者:「そうなると御社で提供されている360度評価はいいですね。
複数の他者評価は否定のしようもないし、対象者の行動を浮き彫りに
しますからね。ガツンとやるにはいいですね。対象者がどう変わったかも
わかりますしね!」
ところが、360度評価はそんなに甘くありません。
だって評価者が他人だからと言って、その人の評価が正しいとは
限りません。怖い上司の部下は後が怖いので本音をつけないかも
知れません。
ある仕事で一緒だった人はその仕事での印象しかない
場合もあります。もしよくない印象だったら最悪です。
本当は別の側面もあるはずなのに。
評価基準の問題もあります。甘い人と辛い人。
かく言う私も他人の評価は滅多に満点はつけません。
これらの問題に対しては、評価者の数を多くする、
極端な評価は省く、などいくつかの方法を駆使して、
客観性を担保するようにしています。
ところが、問題はもっとあるのです。
仮に自己評価と他者評価に差があったとしましょう。
360度のような他者評価ではその差(上記のような課題はあったとしても)
がはっきり分かるところがポイントです。
問題は一般的な360度や他者評価だけでは
なぜその差が起きたのかが分からないのです。
弊社の検査では「なぜ」を本人の意識とEQ能力の高低から推測します。
なぜについての、例え話です。
私の先輩が昔ゴルフを手ほどきしてくれました。20年ほど前です。
二人とも当時アメリカ駐在員だったので公営ゴルフ場の
プレー代は一回10ドルで済んだのです。
決して贅沢をしていた訳ではありませんよ。
ところがろくに練習もしていないのでボールが前に飛びません。
次のページ自己評価と他者評価は一致
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13

横井 真人
産業能率大学 教授
個人と組織のパフォーマンス向上を研究。人の行動をスキル、知識、行動意識、感情能力、価値観等の要素に分解し、どの要素が行動に影響を与えているかの観点からパフォーマンスを分析。職場のコミュ二ケーション、リーダーシップ、チームビルディング、ファシリテーション、ソリューション営業、マーケティング等の具体的施策に視点を活用する。
 フォローして横井 真人の新着記事を受け取る
フォローして横井 真人の新着記事を受け取る