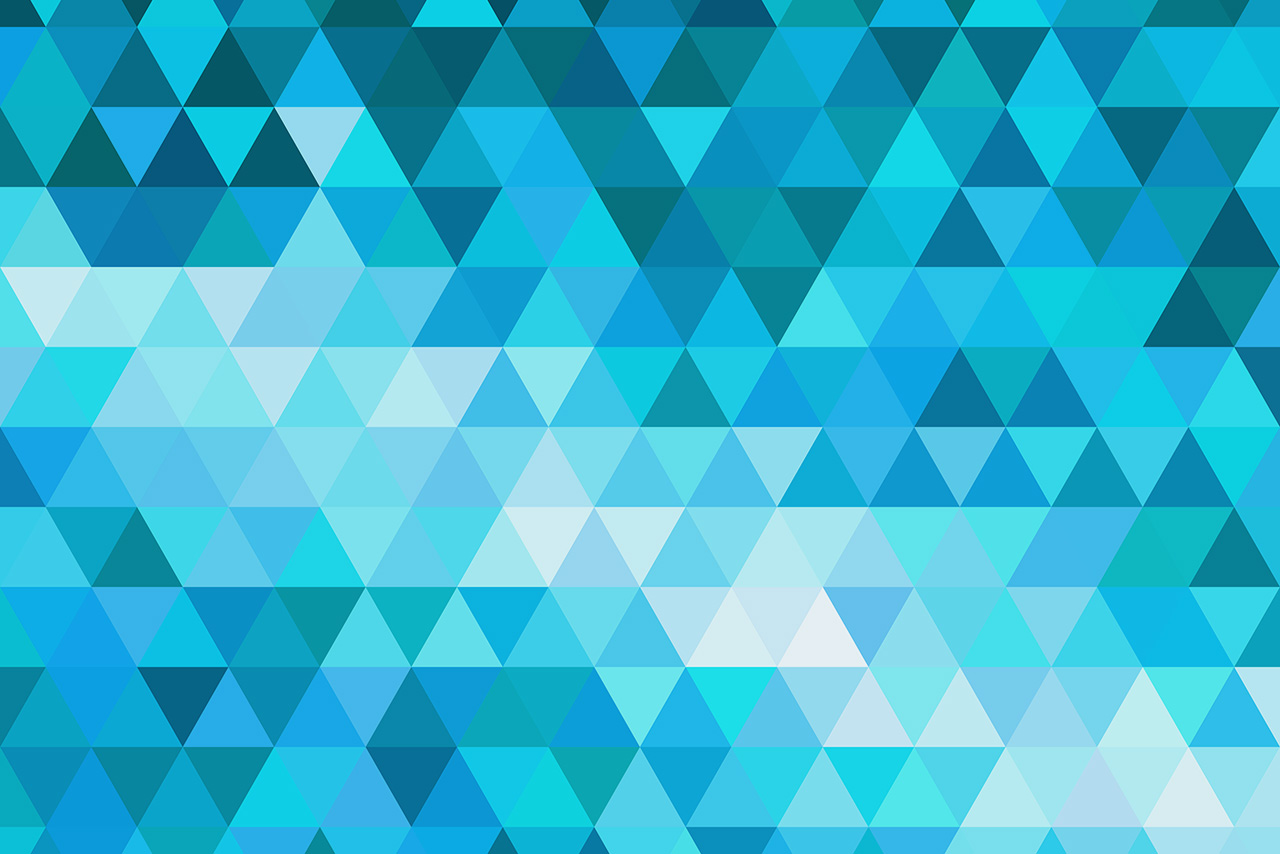人間にはお互いを分かり合い、コミュニケーションを円滑にとるための細胞があります。しかしデータベースがデータなくしては機能しないように、細胞の能力を活かすには経験知が必要なようです。
周知の通り、小説のほとんどは登場人物の心理描写です。
背景があり、事件があり、主人公が何かを感じ、考え、
行動します。作者によってこの描写のテクニックや
視点が異なります。これこそが人の気持ちを理解する
ための「言葉」と「状況」の疑似体験の宝庫なのです。
自分だけでは明確に言語化できなかった自分の気持ちを
描写を読むことによって「言葉」で表現できるようになります。
「嬉しい」にも、「悲しい」にも実はニュアンスの異なった多様な
表現方法とそれぞれの感情を生む状況があります。
このような疑似体験とそれに付随する言葉の数々が
脳の中に蓄積され、それが他者への「共感」につながり、
共感に基づいた相手への配慮へ結びつくのです。
次回につづく
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13

横井 真人
産業能率大学 教授
個人と組織のパフォーマンス向上を研究。人の行動をスキル、知識、行動意識、感情能力、価値観等の要素に分解し、どの要素が行動に影響を与えているかの観点からパフォーマンスを分析。職場のコミュ二ケーション、リーダーシップ、チームビルディング、ファシリテーション、ソリューション営業、マーケティング等の具体的施策に視点を活用する。
 フォローして横井 真人の新着記事を受け取る
フォローして横井 真人の新着記事を受け取る