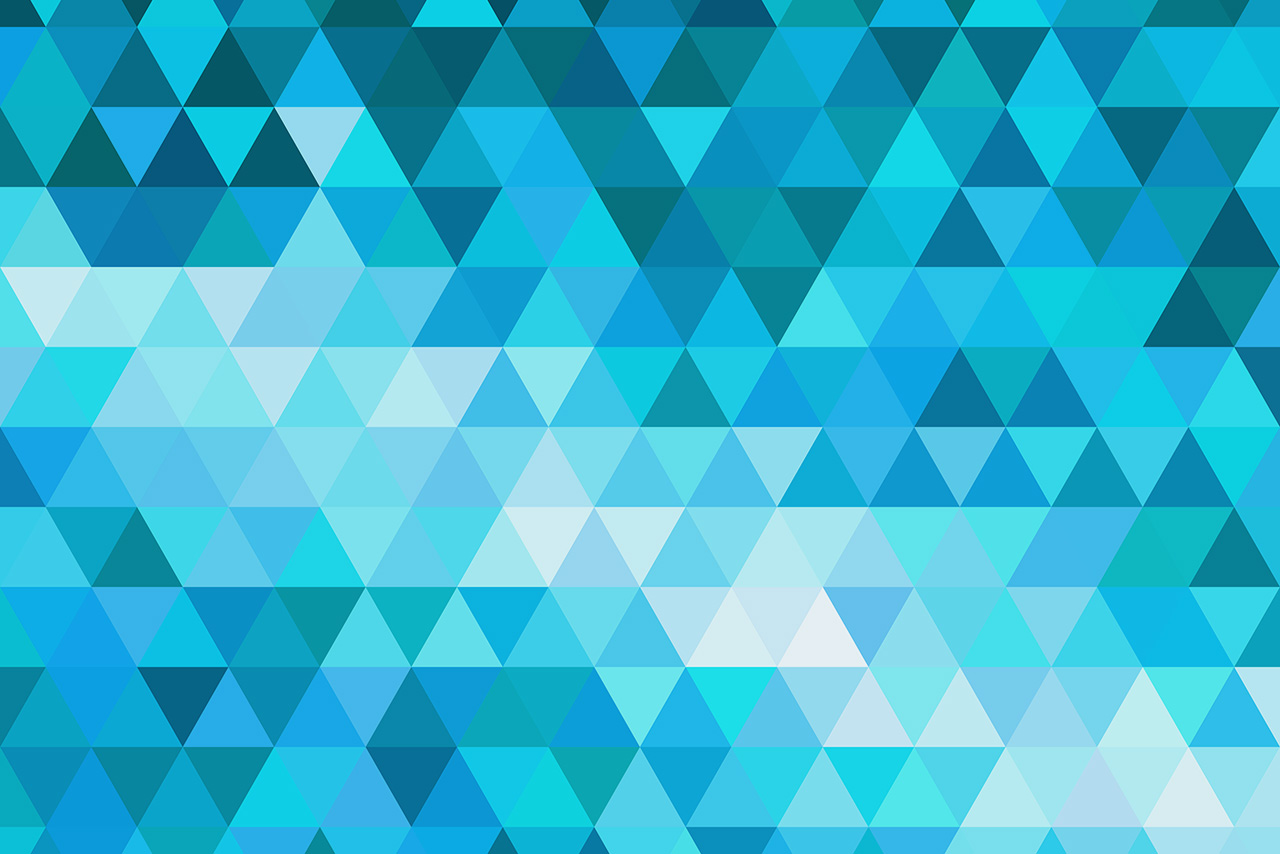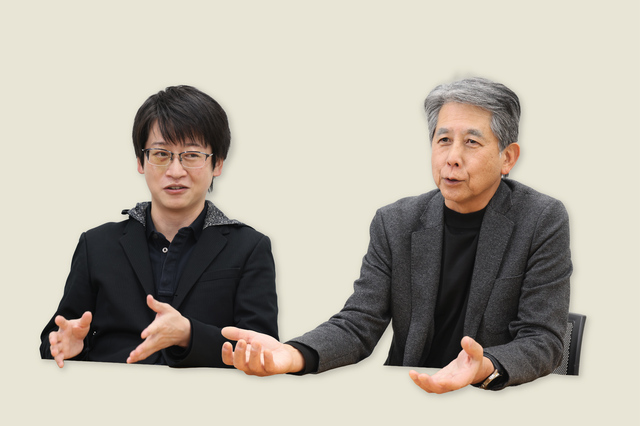NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀スペシャル」で、宮崎駿監督がお話されていた言葉から、「なぜ、これだけのパフォーマンスを出せるのか?」を読み取り、それを若手の人材育成に転用して考えてみる。
抽象化すると、元来、仕事は、どんな職種であれ、「誰かに、なにがしかの、価値を提供する」ことで、対価を得るという活動である。これは、言いかえれば「③他人の役に立つ」ということに他ならない。
であらば、本当の意味で、組織が、スタッフをハイパフォーマーとして育成したいと考えるのならば、本心から「自分は受け入れられているし、自分に自信をもてる」状態に導線を引いてあげることが必要となる。
具体的には、2つのことが、必要だと、私は思う。
1つめは、研修などを通じて、本人がガムシャラに目の前のことをやるような啓蒙をしていくこと。結局、人に愛され、自分に自信をつけるには、「力」をつけ、「成功体験」を創るしかない。何かをやりとげると、脳には、快楽物質であるドーパミンが流れるようなシナプス結合ができる。平たくいうと、成功体験を一度作ると、再現性が高くなり、それが、①と②の欲求を満たす呼び水となるのだ。
2つめは、「環境」を整えること。例えば、若手人材がどれほど、がんばっても、「上司が、結果だけしか見ない。褒めない。」などという環境では、自分や、お客様の役にたつ・・・ではなく、「怒られないようにやる」という恐怖を行動の起点とした「自分殺し」の行動しかとらなくなるはずだ。(「コーチング」の本に、「部下を伸ばしたければ、承認(褒める)することをを覚えましょう」という類の話が書いてあるが、褒めるべき理由は、脳の構造から考えるとここにある。)
また、別の例をあげると、どれほど成果を出そうとも、それに報いるだけの金銭がバックされることが明確に可視化されていなかったり、自分のビジョンを描けるキャリアパスが整備されていないといった人事制度が未整備の場合も、「会社は、私たちのことを愛していない」と、①が満たされないことになるであろうから、制度の整備も必要であろう。
ここで、宮崎監督の話にもどすがー
おちまさとさんの著書で読んだが、宮崎監督は、一日、ものすごい量の仕事量をこなし、その集中力たるやすさまじいらしい。 また、ウィキによると、若いころに「アルプスの少女ハイジ」の作品制作を担当したらしいのだが、その中で、大きな役割を担ったときに、最高平均視聴率が26.9%という、成功体験を作っている。そして、インタビューなどを読むと、最高の作品を作るための環境整備として、製作費等についても、非常にこだわりがあるらしい。
やはり、若い時代から目の前のことを一生懸命にやり、成功体験を創り、自分のこだわりを発信できる環境を創ってきたからこそ、
自分がこの仕事をしているのは『人に楽しんでもらいたいから』
人に楽しんでもらえてこそ自分の存在の価値があると感じることが出来る。
・・・こういうことを本心から言えるのではないだろうか。
そんなことを、テレビをみながら、私は感じたのだった。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13