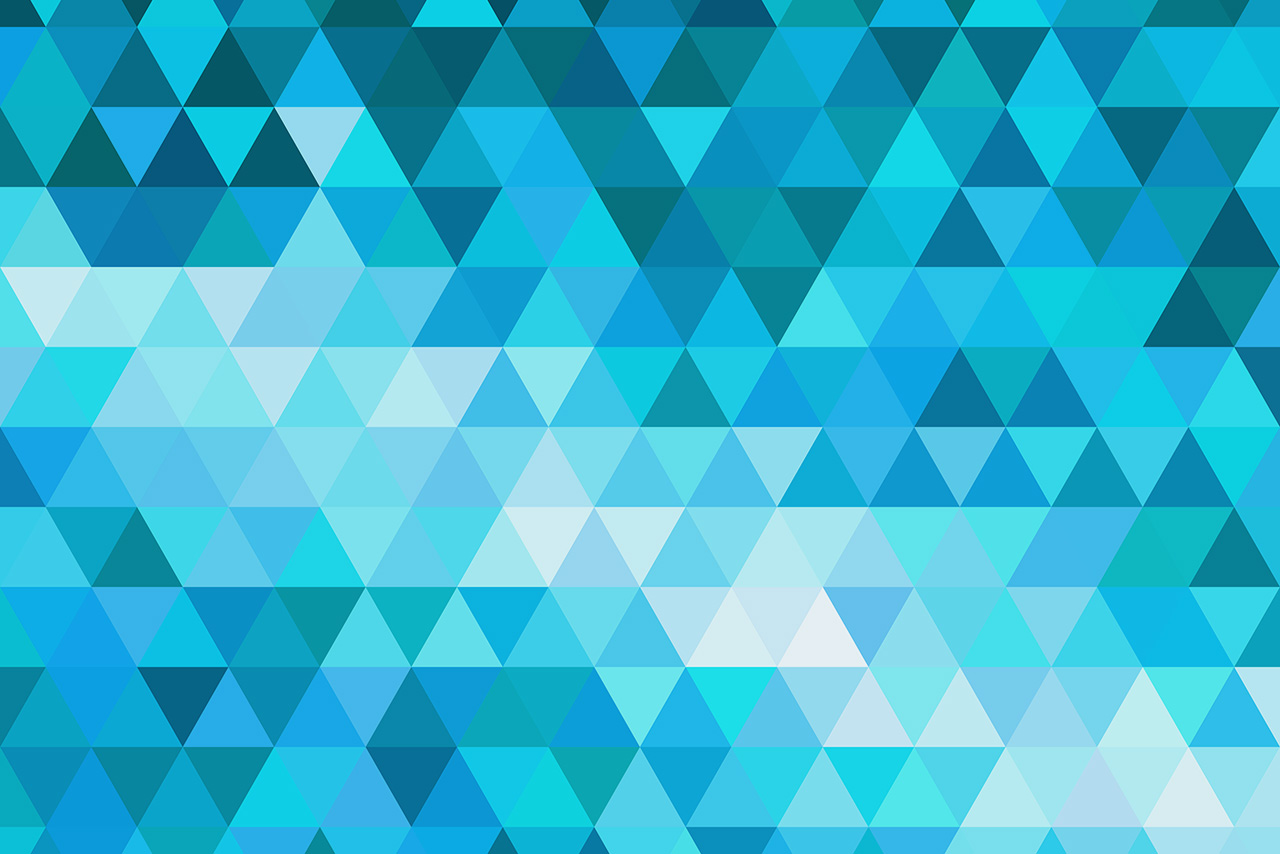グローバル化が叫ばれてしばらく立ちますが、道のりは険しいですね。国籍も言語も常識も、目的や理想も異なる人達と本当にうまくやっていけるのでしょうか?言語なんて一要素でしかありません。
実は相手が外人でなくても本質的に同じ事象はもっとあるのではないでしょうか。派遣の子は話がわからないから会議に入れなくてもいいや。あの部署は面倒くさいから事後報告にしておこう。話が「通じる」のは「言語」の問題もありますが、それは共通意識や前提・期待値に共通するものが多いからなのです。でも「通じない」からこそコミュニケーションをとる努力が必要なんですけどね。
英語はブロークンでも外国人から信頼を得てしまう伝説の海外駐在員はどの会社にもいることでしょう。秘訣はなんでしょう?
テレビの「ウルルン滞在紀」を見ていると滞在するタレントさんの語学力はおしなべて大したことはありませんが、ブラウン管(液晶画面?)から伝わってくるホームステイ先の家族との打ち解け具合には結構差があるように思えます。そこには意識のあり方や感情のやりとりの差が存在するのではと思います。
ダイバーシティーマネジメントと言ってしまえば簡単ですが、他者の気持ち、その背景を考え、理解しようとする姿勢が「差の受容」の根幹となり、信頼関係につながるようです。言語が通じないからこそ表情や姿勢、目の動きで推し量るしかないのですから。一言で言えばEQが必要になります。
後日、あのシンガポール女性に声をかけたとき、
「昨日Sさんが私をお昼に誘ってくれました、元気がなさそうで心配なんだけどと。ご飯を食べながら個人的にいろいろ意見を聞いてくれたんです。その時出たアイディアがグッドだから課長に2人で相談しに行こうと言ってくれて、ちょっと嬉しかったです」と言っていました。
道は遠いですが一歩ずつですね。
次回へつづく。
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
 会員登録
(無料)
会員登録
(無料)
-
 ログインはこちら
ログインはこちら
関連記事
2010.03.20
2015.12.13

横井 真人
産業能率大学 教授
個人と組織のパフォーマンス向上を研究。人の行動をスキル、知識、行動意識、感情能力、価値観等の要素に分解し、どの要素が行動に影響を与えているかの観点からパフォーマンスを分析。職場のコミュ二ケーション、リーダーシップ、チームビルディング、ファシリテーション、ソリューション営業、マーケティング等の具体的施策に視点を活用する。
 フォローして横井 真人の新着記事を受け取る
フォローして横井 真人の新着記事を受け取る