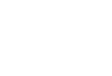/カントは、理性の限界とともに実践の領域を発見した。しかし、そこでは、現実との対決が待ち受けており、ばらばらの自己定立が人々の同一性を打ち壊す。ヘーゲルは、ここに、学習し発展していく世界理性という新たな神を見たが、フォイアーバッハやマルクスは、唯物論としてモノの支配と人間性の疎外を疑い、共同体による革命の必要性を説いた。だが、キルケゴールは、カントに戻って、神は理性の限界の向こうに置き直し、それを支点として、他人とは異なる生き方、単独者としての実存を問うた。/
2.フィヒテ(1762~1814)

しかし、実際に革命が起き、それが戦争になると、そうかんたんな話ではなくなる。フィヒテは、カントの思想を引き継いだものの、実際の実践は、自由ではなく、まして、もはや普遍立法などという純粋な状況ではない、という現実に直面する。というのも、未経験の世界とはいえ、それは純粋に何もない自由な沃野ではなく、そこにかならず自分と対立するものが現前と存在しているからだ。
そこで、フィヒテは、むしろ、自分と対立するものを克服していってこそ、その克服の仕方において自分が独特のものとして定立する、つまり、「事あしらい(タートハンドルンク)」こそが自我を作る、とした。
たとえば、営業で断られる。断られたから、諦める、というのも、一つの答えだ。だが、答えは、それ一つではない。断られたから、断った理由を聞き出す、という答えもある。それどころか、断られたから、また訪問する、という答えだってある。つまり、答えは問題にあるのではない。自分にある。問題にぶつかったときこそ、自分がどういう人間であるか、答えを出すことになる。
ああしたい、こうしたい、という自我の意志は、ただ観念的なものにすぎない。これに対し、自然な世界は確固たる重さを持って実在し、自我の意志に立ち塞がる。そして、これでいい、と、観念が実在を統合したとしても、さらに世界は、その外側に広がっており、自我の実践にとっても、世界は永遠に掌握しえない永遠の地平線となる。
3.シェリンク(1775~1854)

一方、シェリンクは、スピノザの汎神論やライプニッツのモナド論を踏まえて、奇妙な全体主義的観念論を唱える。すなわち、彼によれば、実在としての全体的自然から観念としてのモナド的自我まで、質として連続で、実在性と観念性の量的相違にすぎない、という。たとえば、植物がある、野菜がある、食料がある、食堂がある、食券がある、カネがある、は、一連の存在の質的な帯を成す。
したがって、すべての存在はもともと一体であり、汎神論的で均一な絶対的「同一者」こそが、万物の本質として存在する。だが、彼によれば、フィヒテの言うように、個々の存在は、この絶対同一者の中で、自分勝手に自己定立して、これらが元の同一者を否定する。
実際、最初、フランスで革命が起こったときには、世界中の民衆が同じ自由・平等・博愛をめざして立ち上がった。ところが、いざ新政権を打ち立てるとなると、それぞれがかってにばらばらの構想を言い出し、むしろ革命を押さえつけようとし始める。まして諸外国に至っては、フランスに対して反革命の戦争を起こすことになる。
哲学
2020.06.27
2020.07.27
2020.08.15
2020.10.21
2020.12.04
2020.12.08
2021.03.12
2021.04.05
2021.07.29
大阪芸術大学 哲学教授
美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。
 フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る
フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る